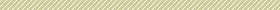【法政大学最新講義録】社会人のための経営戦略
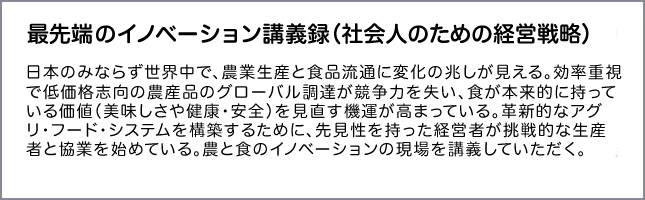
「農産物グローバル調達の終わり:農と食はローカルに回帰する」[1]
法政大学経営大学院
イノベーション・マネジメント研究科
教授 小川 孔輔
<飽食の時代が終わりかけて>
日本人の食生活を豊かにしてきた原動力は、近代的な食品スーパーマーケットの成長と飲食店チェーンの普及である。わたしたちの学びのモデルは、20世紀初頭の米国で発明されたマスマーケティングの仕組みとチェーンストアの理論だった。先頭を走っていた米国のフードシステムでは、農産物や加工食品の鮮度を保つために、冷蔵・冷凍技術を発展させ、鮮度保持剤や食品の保存剤を開発した。そして、小麦やトウモロコシなどの穀物や野菜を大量に効率よく生産するために、農薬と化学肥料を大量に投入する農法を開発した。
農業生産の技術革新を担ったのは、モンサント(Monsanto)やシンジェンタ(Syngenta)のようなグローバルに事業を展開する農業コングロマリットである。米国は国土が広くて物資の輸送距離が長いので、農産物の品種選択で重視される基準は、輸送効率と廃棄ロスの削減効果だった。カーギル(Cargill)やドール(Dole)などの米国の食品メジャーが、農産物のグローバル調達を加速させこともそれに拍車をかけた。
生産と調達がグローバルになった結果、耕地面積当たりの収量が多くて品質が安定している品種、すなわちF1品種(交雑種)やGMO(遺伝子組み換え作物)が世界中で栽培されるようになった。単一品種を大量に栽培できるほうが、低価格で農産物を供給できたからである。ただし、効率重視の近代農法によって失われたものもある。それは、野菜や果物などが本来的に備えているはずの美味しさや香り、栄養価などである。
わたしたちがいま食べている野菜や果実は、消費者の都合ではなく、どちらかといえば流通の都合で選ばれている。しかし、飽食の時代は終わりかけている。日本人一人当たりのエネルギー摂取量の推移を見ると、それは一目瞭然である。ピークだった1961年、日本人の一人当たりコメ消費量は、現在の2倍の年間約117.4kgだった。現在(2014年)のコメの消費量は当時の半分(55.2 kg)を下回っている(図表1)。
農産物や食品に求められているのは、いまや価格より価値である。たとえば、日本のエンゲル係数は、2005年を底(22.9%)に、2014年には24.0%まで上昇している(図表2)。一部の経済学者は、この現象を高齢化が原因だと分析している。しかし、食全体に占める外食や中食(惣菜)の割合が増加していることを見れば、エンゲル係数が上昇している本当の原因は容易に説明ができる。消費者は、食に関して低価格や簡便さだけを求めているわけではない。美味しさや鮮度などの付加価値を求めているのである。
戦後の70年間、わたしたちがお手本にしてきた米国流のフードチェーンは、流通コストと生産効率を優先するシステムだった。その仕組みを根本から見直すべき時期に差し掛かっている。
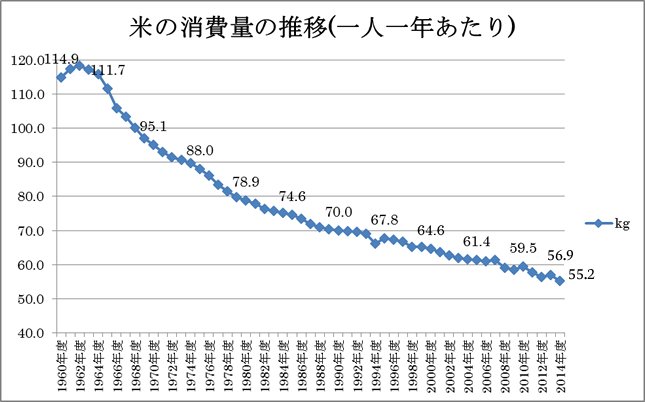 図表1 日本人一人当たりのコメ消費量(~2014年)
図表1 日本人一人当たりのコメ消費量(~2014年)
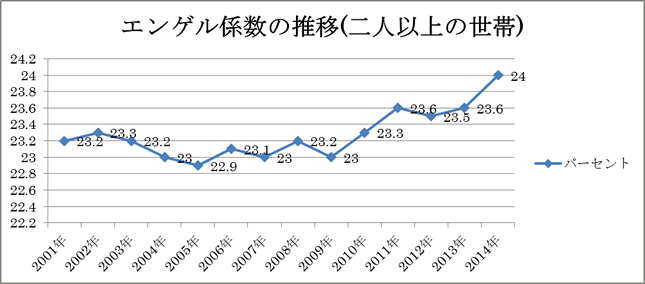 図表2 日本のエンゲル係数の推移
図表2 日本のエンゲル係数の推移
<モノが運びにくくなったことの意味>
日本のフードシステムにとっての問題は、物流費と人件費の高騰である。モノが運びにくくなったいま、逆説的ではあるが、その土地で生産された生鮮品を地域内で消費することが経済的にも利にかなうようになっている。
食品の長期保存と長距離輸送という条件を外していいのなら、野菜や果物の品種選択の基準はちがってくる。生鮮品を地域内で、しかも即時に加工して販売できる流通の仕組みがあれば、コストと人件費をかけて農産物を遠くまで運ぶ必要はなくなる。そうなれば、日本の食品流通から消えかけていた「美味しさ」(+旬と鮮度)という価値観を復権させることができる。
長距離輸送が優勢な社会では、農産物を効率よくパッケージングする都合から、サイズや形状が不揃いのナスや曲がったキュウリを流通させることができない。しかし、域内に加工センターがあって、ひと昔前のように短距離輸送がふつうになれば、農産物の流通加工に関する手続きもちがってくる。従来は非規格品としてロスになっていた農産物も、廃棄せずに流通させることができるからである[2]。フランス政府は、将来の食料不足とCO2の削減を見越して、農産物の廃棄ロスに対してペナルティを課す制度を新たに作っている。
競争力の源泉が、大量に安く作れて安価に運べる「価格基準」ではなく、多少は高くても美味しさと鮮度を重視する「価値基準」にシフトすることの意味は大きい。グローバルに展開する食品小売チェーンでも、地域対応を強化する必要が出てくるようになる。
地域の食材が重視されれば、生鮮品のローカルな品揃え力が食品小売業の差別化のカギになる。野菜では、F1種やGMOではなく、在来種(自家増殖可能な品種)が、肉魚では従来の流通では市場化できなかった特産品(数量限定の希少品)が脚光を浴びることになるだろう[3]。
<食のグローバリゼーションは反転する>
農産物を生産する側の都合も、地域内での生産と流通を支持している。
TPP(環太平洋パートナーシップ協定)が世間の注目を集めて、世界の食料供給システムでは自由貿易がこれまで以上に推進されると一般には信じられている。しかし、農産物の生産と流通に関するグローバルな環境変化を冷静に眺めてみると、そのトレンドはすでに反転しつつあることがわかる[4]。
農産物の生産には、3つの天然資源が必要である。人間の労働力と動力機械を除いた究極のインプットは、「水」と「光」と「種子」である。
穀物や野菜を加工して遠くに運ぶために必要な化石燃料は、元をたどれば太陽の恵みに由来している。たとえば、大根やキャベツなどの重たい野菜は、なるべく遠くに運ばないことが、無駄なエネルギーを消費しないための賢い選択である。実際に、これまで適地適作で栽培されていた重量野菜が、近年は消費地の周辺で作られようになっている。
亜熱帯モンスーン地帯に位置しているおかげで、日本は年間を通して降雨量が多い。水資源が潤沢であるから、日本人は希少資源としての水の存在を意識することがない。しかし、世界の三大穀倉地帯(アルゼンチン、北米、ウクライナ)には、ひたひたと干ばつが押し寄せてきている。農業生産では水が最も希少な資源になりつつあることは、米国農務省のレポートからも明らかである[5]。
この先はどう考えても、東南アジアや中南米、アフリカの人口爆発を補うほどに、「グリーン革命」(農業部門の生産性向上)が進行しそうにない。世界を覆う水不足と気候変動の影響を考慮すると、21世紀の中盤にかけて、わたしたちは絶対的な食料危機に備えなければならないことになる。農業大国のフランスがすでに意識しているように、国家としての新たな課題は、穀物と野菜・果物の供給不足と大幅な価格上昇である。
グローバル調達が機能するのは、農産物が供給過剰の状態にあるという特殊な条件が満たされるときである。人類の歴史を振り返ってみれば、戦争や飢餓の時代が一般的である。飽食の時代は例外なのである。
<タネは土を記憶する特性を持っている>
農産物の生産にとって三番目のインプットは、種子(タネ)である。ふだんあまり意識することはないが、種子の品種選択は、思いのほかにわれわれの日常生活に対するインパクトが大きい。
農作物の栽培において、どのタイプの種子(「固定種」「F1」「GMO」:詳細は後述)を選ぶかは、農業技術の選択と食品流通システムの設計に深く関係している。自然農法で有名な青森県在住のりんご農家、木村秋則氏の話を読んでいただければ、その理由の一部が理解いただけると思う[6]。
あるとき、木村氏は、山の樹々や草花たちが肥料も農薬も使わないのに立派に育っている様子を見て、「山の土ならば何でも育つはずだ」と考えて、山から土を持ってきて稲の苗を植えてみた。ところが予想に反して、稲はほとんど育たなかった。それでも一応、穂が出て30粒くらいのタネモミがとれたので、翌年はタネモミを同じ山の土に植えてみた。今度は立派に育って、一年前と比べて10倍の収穫量になった。
木村氏がこの経験から得た結論は、「タネには土を記憶する力がある」だった。在来種(「固定種」とも呼ばれる)の特徴は、タネが自然にその土地(光と水)になじんでいくことである。多くのタネのなかから、その土地との相性がよい系統だけが残っていくからなのだろう。在来種のタネには、本源的に進化の多様性が埋め込まれているらしいのだ。ただし、種子が栽培環境に反応してしまうから、在来種のタネは形質が一定しないという欠点を抱えている。
F1品種やGMOのタネは、その点では形質的に優勢である。栽培環境に関係なく、栽培効率が高くて形や味が一様になるからである。ただし、そこには欠点も潜んでいる。一見してどの土地でも良好に育つように育種されているF1の種子は、環境(土、光、水、その他の環境)に依存しないようデザインされている。そのため、環境が激変したときに生き延びる冗長度をもっていない。
両方のタイプの種子を比較すると、「経済的な効率」(均質性と安定性)と「リスクに対する適応力」(多様性と適応力)とがトレードオフの関係にあることがわかる。
<コスト効率優先の標準化や規格化は優位性を失う>
タネの話を長々と書いてきたが、近代的な農産品の生産と流通において、在来種は不利な立場に置かれてきた。米国のフードビジネスが、輸送がしやすい形質をもった作物(品種)を好んだことは冒頭で述べた通りである。失敗がなく栽培できて形も均一な品種のほうが、効率的に輸送できるからである。野菜におけるF1種子の隆盛と、大豆や小麦などの穀物GMOの技術開発が、食品スーパーやファストフードビジネスの成長に弾みをつけたことはまちがいない。
しかし、いまや在来種が見直され始めている。なぜならば、食材の冷蔵・冷凍技術の発達で加速された遠距離輸送と在庫保管によって失われるものもあるからである。たとえば、香りや舌触り(テクスチャー)のよさがそれである。野菜や果物や魚がもっともおいしいのは、自然に収穫できる時期にその場ですぐに食べることである。そのうえで、食材にはなるべく余計な手を加えないことがいちばんなのである。
その一方で、輸送費が高騰していることで、農産品を遠くまで運ぶことの経済合理性が失われている。世界中どこでも入手可能な食材を使った低価格商品は、もはや競争の武器にはならない。コスト効率が優先される標準化や規格化は、相対的な優位性を失っている。
<米国人の味覚に変化が起こっているようだ>
本家本元の米国における食の状況を見てみよう。
米国人もそのことに気がつき始めている。なぜならば、おいしさが何たるかを知り始めたからである。米国における地域支援型農業(CSA:Community Supported Agriculture)や有機農産物の普及は、そうした消費環境の変化を反映したものである。
筆者が米国に留学していた約30年前(1982~1984年)、米国人は食事を「エネルギー」(炭水化物、糖分、脂質)や「建材」(アミノ酸、タンパク質)や「ビタミン、サプリ」(微量補助要素)としてとらえていたように思う。彼らにとって、「誰とどこで食べる」が大切であって、「何を食べるか」についてはわりに無頓着だった。
ところが、健康や肥満の問題もあって、米国人もいまは食事に気を使うようになった。低カロリーで低脂質の豆腐や魚、米に関心が向いている。ナチュラル系スーパーのホールフーズ・マーケット(Whole Foods Market)やトレーダー・ジョーズ(Trader Joe's)の店頭には、そうした商品があふれている。
なるべく素材の良さをそのまま生かした食事を摂るようになれば、人間の舌の感度はよくなるものだ。マクドナルドのハンバーガーのように、脂っこいシーズニングや合成甘味料などを使用しなくなり、食材のおいしさをそのまま楽しめる。味に対する価値観の転換である。
<日本発の食材流通の仕組みは、在来種から生まれた>
日本での食糧事情のほうはどうだろうか?
もともと旬と素材のよさにこだわってきた日本の食は、米国のファストフードビジネスの移植によって変質を遂げてきた。規格化しやすい食材を、セントラルキッチン(調理工場)で加工して店舗に運ぶ。その提供システムがいま壁に突き当たっている。たとえば、日本マクドナルドのハンバーガー事業の不調は、食の提供システムが時代のニーズに合わなくなってきた典型的な事例である[7]。
以下では、従来とは逆の動きを志向して顧客の支持を得ている3つの事例を紹介する。どの事例に関しても、なるべく地域内で農産品を調達しようとする考え方は共通である。そして、偶然にも、どのケースもタネは在来種を活用している。
東京都の西部(羽村市)に、食品の品質にこだわるユニークな小売チェーンがある。筆者が「日本のホールフーズ・マーケット」と呼ぶナチュラル&オーガニックSMの福島屋(福島由一社長 下写真 六本木一丁目 アークヒルズ店店内風景)である[8]。

消費者の安心・安全ニーズに応えるため、同社はSPA(製造小売業)を志向しており、加工食品も独自の基準で品揃えする。自然栽培や国産有機農産物をベースにするなど、「大変安全性に優れている商品」は赤、外国産有機農産物による食品や原材料にこだわるなど「安全性に配慮されている商品」は緑、「一般的な商品」は白の印(ラベル)で表示している(1割が赤、7割が緑)。一部の麺類は、系列工場で小麦粉から生地を練り上げてつくる。小麦やコメ、野菜の栽培方法(自然栽培)や品種(在来種優先)にこだわるのは、たとえば、青森で「菊芋」や「藍」などの在来種を栽培している農業者を支援するためである。そして、採算性や販売効率よりも、おいしさと食材の安心・安全を重視しているからである[9]。
同様な取り組み事例として、埼玉県都比企郡幾川村にある、とうふ工房わたなべ(渡邉一美社長)を2番目に紹介する。同社は、国産大豆でつくった豆腐やがんもどきだけを、工場併設の店舗で直売している。日販100万円は、単独店舗としては日本一の豆腐屋である。二代目経営者の渡辺一美さんは、学校給食グループとの取引がきっかけで、輸入原料でつくる豆腐のSMへの卸売をやめ、国産の素性のわかる豆腐に特化した。原料の一部は地元栽培の「小川青山在来」という品種で、有機栽培農家の金子美登氏(全国有機農業推進協議会理事長)らが地元で古くから栽培されていた在来種を復活させたものである。
同じように、その土地の在来種(たとえば、「藤沢かぶ」)を発掘して料理に使っているシェフがいる。山形県鶴岡市在住の奥田政行シェフである。奥田シェフは、イタリア料理店「アルケッチャーノ」や「山形サンダンデロ」で、自身が発掘してきた地場野菜の種子を使った料理を提供している。小川町の有機農家の金子さんも、山形のシェフ奥田さんも、古くから地元で栽培されていた在来種を発掘して食のイノベーションに挑戦している。
これは、米国渡来の食べ方、つまり「規格化された単品料理を標準的で品質が揃った大量の食材で加工・調理して提供する」という食の提供方式に対するアンチテーゼである。そのため、いま日本全国で地元産の在来種を集めて保護しようとする運動が活発になっている。そのために、毎年8月に東京丸の内の中央郵便局(KITTE)で「にっぽん伝統野菜フェスタ」が開催されている(図表3)。主催者がぐるなび(東京都/久保征一郎社長)で、農水省が伝統野菜を守る会を後援している[10]。また、和食に欠かせない日本の代表的な在来種であるワサビの保護運動も始まっている[11] 。
<図表3> にっぽん伝統野菜フェスタ(2015)の出展リスト
- ●山形県鶴岡市(だだちゃ豆)
- ●山形県酒田市(平田赤ねぎ)
- ●八百五商店(福井県・吉川なす)
- ●野菜のカネマツ(長野県・松代青大きうり)
- ●天龍農林業公社(長野県・ていざなす)
- ●江戸東京野菜コンシェルジュ協会(東京都・東京うど)
- ●内藤とうがらしプロジェクト(東京・内藤とうがらし)
- ●埼玉県深谷市(白なす)
- ●warmerwarmer(愛知県・十六ささげ)
- ●百姓隊(宮崎県・佐土原なす)など
<米国でも、食はファストからスローへ> [12]
最後に、筆者が米国のショッピングモールで観察した光景を紹介して本稿を終えたい。
昨年10月の初めに、南米視察ツアーの帰途、ジョージア州アトランタのホテルに宿泊した。アトランタ国際空港は、発着数と利用者数が世界一である。交通の利便性が高いことから、ビジネスやショッピングのためにアトランタにはたくさんの人が集まってくる。市の中心部には、米国最大級のショッピングモールがあって、3つの高級百貨店(ニーマンマーカス、グルーミングデール、メイシーズ)が核テナントして入店している。
さて、空港到着後に、そのレノックス・スクウエアを視察することにした。わたしがもっとも興味を持ったのは、フードコートの様子だった。マクドナルドの店舗を観察したかった。ところが、案内板にゴールデンアーチを見つけることができなかった。驚いたことには、バーガーキングやタコベルなどのファストフード店も入店していない。

日曜日の昼過ぎである。フードコートのカウンターにはたくさんの人が並んでいた。メキシカン料理のチポトレ、日本に上陸したばかりのチキンサンドのチックフィレイなど。どの店も、食材のナチュラルさやヘルシーさを訴求している。また、注文を取ってから商品を手渡すのでなく、顧客に具材を選んでもらう方式を採用していた。カウンター前には長蛇の列ができていたが、列に並んで静かに自分の番が来るのを待っている。
ファストフード発祥の地で、食がスローに変わっていく光景に遭遇することになった。マクドナルドに代表されるファストフードビジネスが、チポトレ(上写真@レノックスモール)のようなスローなコンセプトのレストランに駆逐されはじめていた。
アメリカでも、低価格や利便性を重視するだけでなく、食べ物が本来的に持っている価値(美味しさや健康)を大切にする考え方が定着しはじめている。その様子を見てしまったのである。
参考文献
[1] 本稿は、小川孔輔(2016)「生鮮食品調達網の構築:飽食の時代の終焉と食糧危機、食品小売業にとって農業へのアプローチは不可欠に」『食品商業』(1月号)と、小川孔輔(2015)「「ローカル市場に潜むナチュラル&オーガニックの可能性」『DIAMOND Chain Store』(12月1日号)をもとに書かれている
[2] 松尾雅彦(2014)『スマート・テロワール:農村消滅論からの大転換』学芸出版社。自らのカルビーでの経験(国産ポテトを使用したチップスなどの開発)を通して、地域農産物の経済自給圏を確立することが、日本の農業を救う道であると説いている。
[3] たとえば、東京都羽村市の食品スーパー福島屋の取り組みが標準的になるだろう。近代チェーンストア理論では、販売機会ロスを出さないために、商品の店頭在庫が途切れないようにと教えてきた。しかし、地域産で希少な農産品に関しては「売り切れ御免」のMD(商品政策)でもよいことになる。福島徹(2014) 『福島屋:毎日通いたくなるスーパーの秘密』日本実業出版社。
[4] TPPと日本の農産物貿易政策についての正当な批判(日本の農業が過保護であるという主張には根拠がない)については、鈴木宣弘(2013)『食の戦争:米国の罠に落ちる日本』(文春新書)が参考になる。
[5] 「米農務省、干ばつで小麦ベルト地帯に「自然災害地域」宣言」(ロイター、2013年10月9日)。
[6] このエピソードは、木村秋則(2015)『タネは記憶する』(農業ルネサンス編集)、『自然栽培(第4号)「タネの秘密」』(東邦出版)を要約したものである。
[7] 小川孔輔(2015)『マクドナルド 失敗の本質』東洋経済新報社。
[8] 福島徹(2014)『福島屋:毎日通いたくなるスーパーの秘密』(日本実業出版社)
[9] 小川孔輔(2014)「食のイノベーション③ :素性のわかる食材流通の仕組みへの挑戦」『(日経MJ。
[10]大竹道茂(2009)『江戸東京野菜 物語編』(農文協)
[11]山根京子(2015)「講演録:世界から愛される和食に不可欠なワサビの危機」(法政大学小川研究室)
[12]この節は、以下のエッセイを元に書かれている。小川孔輔(2016)「観天望気:米国でも、食はファストからスローへ」『AFCフォーラム』(1月号)。
- 法政大学経営大学院 イノベーションマネジメント研究科教授 小川 孔輔(おがわ こうすけ)
1951年 秋田県生まれ
1974年 東京大学経済学部卒業
1978年 東京大学大学院社会科学研究科経済学専攻(博士課程中退)
法政大学経営学部教授を経て2004年より法政大学経営大学院イノベーションマネジメント研究科教授(現在に至る)。法政大学産業情報センター所長、法政大学経営学部長、日本マーケティング・サイエンス学会代表理事等を歴任。日本フローラルマーケティングを創設、同協会会長に就任(現在に至る)。その他、農水省や経産省の委員会座長等の他、トヨタ自動車、大正製薬、サントリー、伊藤忠商事など企業コンサルティングや企業との共同プロジェクト実績も多数。おもな著書に『マクドナルド失敗の本質』(2015年東洋経済新報社)、『CSは女子力で決まる!』(2014年生産性出版)、『しまむらとヤオコー』(2011年小学館)、『ブランド戦略の実際<第2版>』(2011 年日経文庫)などがある。
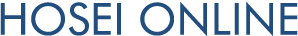




 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【読売新聞と法政大学】
【読売新聞と法政大学】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【読売新聞と法政大学】
【読売新聞と法政大学】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【読売新聞と法政大学】
【読売新聞と法政大学】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【読売新聞と法政大学】
【読売新聞と法政大学】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【読売新聞と法政大学】
【読売新聞と法政大学】 【読売新聞と法政大学】
【読売新聞と法政大学】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【読売新聞と法政大学】
【読売新聞と法政大学】 【読売新聞と法政大学】
【読売新聞と法政大学】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【読売新聞と法政大学】
【読売新聞と法政大学】 【読売新聞と法政大学】
【読売新聞と法政大学】 【読売新聞と法政大学】
【読売新聞と法政大学】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【読売新聞と法政大学】
【読売新聞と法政大学】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【読売新聞と法政大学】
【読売新聞と法政大学】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【読売新聞と法政大学】
【読売新聞と法政大学】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【読売新聞と法政大学】
【読売新聞と法政大学】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【読売新聞と法政大学】
【読売新聞と法政大学】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【最新講義録】
【最新講義録】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【最新講義録】
【最新講義録】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】 【法政ヒストリー】
【法政ヒストリー】