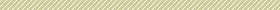気候変動リスクの時代に生きる
社会学部社会政策科学科 田中 充 教授
 田中 充教授
田中 充教授
顕在化する気候変動のリスク
21世紀の日本は、経済社会の根幹に関わるさまざまな課題に直面しています。環境問題はその一つです。中でも気候変動※1は私たちの生活や健康に深刻な影響をもたらす問題であり、その解決に向けて、各国の利害を超えた国際協調による長期的な対策の実施が求められています。
具体的な気候の状況を見ていきましょう。気象庁が2019年1月に発表した「2018年の日本の気候」によると、昨年は記録的な高温となり、東日本の年間平均気温は1946年の統計開始以来最も高く、埼玉県熊谷市では7月23日に41・1℃という観測史上第1位を記録しました。高気温の傾向は世界でも生じており、最近4年間の世界の平均気温は1891年の統計開始以降、最高記録の第1位から第4位までを独占しています。
確かに昨年は異常気象が頻発しました。7月には、約10日間の記録的豪雨により岡山、広島、愛媛を中心に土砂災害や河川氾濫が発生し、死者263人、行方不明者8人※2という甚大な被害が出ています。こうした記録的な大雨の背景には、地球温暖化に伴う気温上昇と水蒸気量の増加があると気象庁は分析しています。
高気温による熱中症被害も拡大しています。2018年6月〜9月には熱中症患者として9万5137人が搬送され、死亡者は1518人に達したと報告されています。気候変動は、まさに私たちの身近な災害リスクとして、生命や暮らしを脅かす重大な要因になっているのです。
将来の気温上昇と気候変動の予測
気候変動に関わる政府関係者、国際的な専門機関、研究者などがこの問題について調査し提言する国際組織として、「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)があります。IPCCは、各国の専門家が集まり、気候変動の現状やその影響、将来の動向などについて科学的知見を収集・分析し、報告書を作成しています。報告書は、最新データに基づく分析結果を集約したものであり、現時点で最も信頼性のある科学的見解が取りまとめられています。国連や各国政府は、報告書を気候変動政策の立案・推進の科学的根拠として活用しています。
IPCCが公表した第5次評価報告書では、21世紀の気候は、複数ある「排出シナリオ」のいずれにおいても、各地の気温が確実に上昇し、多くの地域で熱波が頻繁に発生し、長く続き、極端な降雨がより強く頻繁となる可能性が非常に高いと述べています。その予測によると、21世紀末の世界の平均気温は2000年前後から最大4・8℃上昇するとしています。過去100年間の地球平均気温の上昇が約0・73℃、国内での上昇が約1・19℃という観測結果を踏まえると、今後100年の気温上昇とそれに伴う気候変動が大変深刻な状況になることが容易に推測されます。
排出シナリオが示す気候変動の深刻化
排出シナリオとは、将来社会の気温の動向を予測するに際し、今後の温室効果ガス排出量に関して複数のケースを設定して気温上昇の程度を予測しようとする手法です。IPCCでは、社会の諸活動から排出される温室効果ガスに着目して、排出量が最大となる「高位参照」に加えて排出量に応じた「高位安定化」「中位安定化」「低位安定化」という4ケースを設定して試算しました。
例えば最大の排出量を考慮した高位参照シナリオでは、先述のように100年後に気温は最大4・8℃上昇すると予測されます。このことは、気温が必ずその数値に上昇することを意味するわけではありませんが、現時点の科学的知見に基づくと、対策努力が不足して排出量が増加していく場合には、こうした気温上昇に至る可能性が十分にあることを示唆していると理解できます。この結果、例えば海洋などへの影響を見ると、2100年に海水面は最大で約1・1メートル上昇し、沿岸部の湿地の2〜9割は消滅する、1年当たりの沿岸の浸水被害は現在の百〜千倍に増えるなどとしています。
昨年の西日本豪雨や今年の台風15号による千葉県の被害、台風19 号による全国各地の被害など、今日でも各地で気象災害が頻発している状況を踏まえると、将来の気候変動リスクは甚大なものになることが心配されます。
気候変動への対応「緩和」と「適応」
気候変動に対して効果的な対策が急がれています。対策の基本は、原因物質である温室効果ガスの排出量を削減し、大気中の温室効果ガス濃度の上昇を抑制し、安定化することです。このような対策を「削減策」または「緩和策」といいます。削減策は、特に化石燃料の消費が拡大し、排出量が急増している中国やインドなど、経済発展が著しい国々の協力が不可欠ですが、各国の諸事情から実効ある対策の実施は期待できません。また、世界第2位の排出国である米国は、現政権の下で気候変動対策に距離を置いています。最大限の削減策が求められるにもかかわらず、国際的にはその実施は立ち遅れ、この間にも温暖化は進展し、気候変動の影響はさらに拡大しています。
このような状況下で注目される対策が「適応策」です。適応策とは、地球温暖化と気候変動の進行を前提とし、人間活動や社会システムを調節して、気候変動の影響をできる限り回避・軽減しようとする対策です。実際、夏に気温が上昇し、熱中症が懸念される地域では、抵抗力が弱い高齢者を中心とした熱中症対策など、人口構成や産業構造、立地状況などの地域特性に即したきめ細かな対策の実施が必要になります。
研究成果を社会に還元し政策に実装する
私は、こうした気候変動の影響とその対策のあり方について2000年代前半から本格的に研究を開始し、その成果の一端を取りまとめた業績で先般、学会論文賞を受賞することができました。気候変動問題は今日的な課題であり、研究の歴史が浅く、解明されていない事象や知見が数多くあります。その意味では、いまだ多くの研究課題やテーマが存在する分野であるといえます。
特に期待されるのが、このような研究成果を社会に還元し、広く気候変動政策の立案・推進などに活用していく「社会実装」です。幸い、私たちの研究成果は政府や地方自治体の温暖化対策行政に活用される機会が増えてきています。今後も、研究成果の進展とともに、その成果の実装をさらに進めていきたいと考えています。
※1 気候変動:ここでは、大気の平均状態である気温、降水量などの気候が長期的なスケールで変動することを指す。
※2 総務省消防庁2019年8月20日発表
(初出:広報誌『法政』2019年11・12月号)
- 社会学部社会政策科学科 田中 充
Mitsuru Tanaka
専門は環境政策論。1952年生まれ、東京大学理学部・同大学院理学系研究科修了、理学修士。川崎市勤務を経て2001年4月より社会学部教授、2014 〜2015年度社会学部長。現在、環境アセスメント学会会長、中央環境審議会委員の他、東京都、神奈川県などの環境審議会委員を務める。主な著書に『気候変動に適応する社会』(技報堂)、『地域からはじまる低炭素・エネルギー政策の実践』(ぎょうせい)など。
<教員・研究紹介>新着記事
<教員・研究紹介>
バックナンバー
全ての記事を見る▼
2020.8.11 公開
 グローバル教養学部(GIS)
グローバル教養学部(GIS)
John MELVIN(ジョン・メルヴィン)
止まらない、観光産業の「持続不可能な」成長
The Unstoppable,Unsustainable Growth of Tourism
NEWS
- 2025.2.7 【第8回自由を生き抜く実践知大賞】課題解決に貢献する研究賞「アーバンデータチャレンジ2023 金賞」
- 2025.1.31 人間環境学部金藤正直教授ゼミナールの学生が株式会社エイチラボとオーガニックルイボスティーを開発・販売
- 2025.1.29 「開かれた法政21」学術・文化奨励金授与式及び懇親会を実施しました
- 2025.1.27 「観世寿夫記念法政大学能楽賞」「催花賞」の贈呈式を開催
- 2025.1.24 法政大学と滋賀県が就職協定を締結しました
- 2025.1.17 健康スープでSDGsを実践するイベントを開催しました
- 2025.1.10 第20回デジタルコンテンツ・コンテスト表彰式を開催しました
- 2024.12.24 「法政大学元総長 清成忠男先生 お別れの会」を挙行しました
- 2024.12.23 2024年度(第8回)「自由を生き抜く実践知大賞」表彰式を開催しました
- 2024.12.20 輪島塗救出プロジェクト・チャリティーイベントを開催しました
- 2024.12.20 多摩キャンパス開設40周年記念×第40回多摩シンポジウム「社会課題解決にチャレンジするソーシャル・イノベーター」
- 2024.12.19 3大学共催学生参画型「データサイエンス・アイデアコンテスト2024」開催報告 ~ 『人生100年時代のキャリア形成』~
- 2024.12.18 Team Ethical:100円モーニング企画を実施しました
- 2024.12.17 全国大学生マーケティングコンテストで法政GIS福岡ゼミから出場したチームが7年連続優勝!
- 2024.12.16 アメリカンフットボール部が甲子園ボウルで激闘 2年連続準優勝しました!
- 2024.12.13 「関西大学×法政大学 SDGsアクションプランコンテスト2024」で法政大学現代福祉学部佐野ゼミとスポーツ健康学部吉田ゼミ有志によるチームが大阪・関西万博賞他2賞を受賞
- 2024.12.9 体育会サッカー部から6人がJリーグ加入内定!合同記者会見を開催しました
- 2024.12.4 法政大学が学生の社会的起業を支援するプログラム 「チェンジメーカーズラボ in 多摩(たまらぼ)」最終報告会を開催 最優秀賞はバス通学を便利にする学生×飲食店をつなぐアプリの開発
- 2024.12.3 第43回多摩キャンパスコンサートが5年ぶりに大ホールで開催されました
- 2024.12.3 人間環境学部設置25周年記念祝賀行事を実施しました
- 2024.12.3 法政大学と加賀市が連携に関する協定を締結
- 2024.12.3 2024年度第20回デジタルコンテンツ・コンテスト入賞・入選作品が決定しました
- 2024.11.29 Team Ethical:八百屋/HTLプロジェクト フードドライブ企画を開催しました
- 2024.11.25 2024年度企画展「へび・知るんじゃ展〜からまる信仰と畏れ〜」
- 2024.11.18 受験生向け大学案内動画(2024年公開)
- 2024.11.15 法政大学 次期総長候補者にコー・ダイアナ(グローバル教養学部教授・常務理事・副学長)を選出 2025年3月31日に就任
- 2024.11.14 2024年度SIC教育プログラム「チェンジメーカーズラボ in 多摩(たまらぼ)」DEMO DAYを開催しました
- 2024.11.12 法学部の廣瀬・土山ゼミの学生が「公共政策フォーラム2024 in 会津若松」 において日本公共政策学会長賞(最優秀賞)を受賞しました
- 2024.11.8 理工学研究科の在学生が第8回抗酸菌研究会で第8回抗酸菌研究会奨励賞を受賞
- 2024.11.7 法政大学が「SDGs WEEKs 2024」「DIVERSITY WEEKs 2024」を11月18日(月)〜11月30日(土)に開催 無料生理用品配布の試行など20以上のプログラムを実施
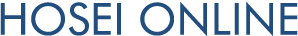




 生命科学部 応用植物科学科
生命科学部 応用植物科学科  キャリアデザイン学部 キャリアデザイン学科
キャリアデザイン学部 キャリアデザイン学科 現代福祉学部 臨床心理学科
現代福祉学部 臨床心理学科 デザイン工学部都市環境デザイン工学科
デザイン工学部都市環境デザイン工学科 人間環境学部人間環境学科
人間環境学部人間環境学科 社会学部社会政策科学科
社会学部社会政策科学科 キャリアデザイン学部キャリアデザイン学科
キャリアデザイン学部キャリアデザイン学科 理工学部応用情報工学科
理工学部応用情報工学科 情報科学部ディジタルメディア学科
情報科学部ディジタルメディア学科 社会学部メディア社会学科
社会学部メディア社会学科 人間環境学部人間環境学科
人間環境学部人間環境学科 現代福祉学部福祉コミュニティ学科
現代福祉学部福祉コミュニティ学科 スポーツ健康学部スポーツ健康学科
スポーツ健康学部スポーツ健康学科 文学部心理学科
文学部心理学科 生命科学部応用植物科学科
生命科学部応用植物科学科 国際文化学部国際文化学科
国際文化学部国際文化学科 経営学部経営学科
経営学部経営学科 経済学部経済学科
経済学部経済学科 理工学部経営システム工学科
理工学部経営システム工学科 法学部国際政治学科
法学部国際政治学科 キャリアデザイン学部キャリアデザイン学科
キャリアデザイン学部キャリアデザイン学科 情報科学部ディジタルメディア学科
情報科学部ディジタルメディア学科
 人間環境学部人間環境学科
人間環境学部人間環境学科 生命科学部環境応用化学科
生命科学部環境応用化学科 デザイン工学部都市環境デザイン工学科
デザイン工学部都市環境デザイン工学科 社会学部メディア社会学科
社会学部メディア社会学科 スポーツ健康学部スポーツ健康学科
スポーツ健康学部スポーツ健康学科 現代福祉学部福祉コミュニティ学科
現代福祉学部福祉コミュニティ学科 社会学部社会政策科学科
社会学部社会政策科学科 情報科学部コンピュータ科学科
情報科学部コンピュータ科学科 国際文化学部国際文化学科
国際文化学部国際文化学科 理工学部応用情報工学科
理工学部応用情報工学科 経営学部経営学科
経営学部経営学科 生命科学部応用植物科学科
生命科学部応用植物科学科 文学部史学科
文学部史学科 経済学部経済学科
経済学部経済学科 理工学部創生科学科
理工学部創生科学科 デザイン工学部建築学科
デザイン工学部建築学科 スポーツ健康学部スポーツ健康学科
スポーツ健康学部スポーツ健康学科 現代福祉学部福祉コミュニティ学科
現代福祉学部福祉コミュニティ学科 人間環境学部人間環境学科
人間環境学部人間環境学科 キャリアデザイン学部キャリアデザイン学科
キャリアデザイン学部キャリアデザイン学科 生命科学部環境応用化学科
生命科学部環境応用化学科 社会学部社会学科
社会学部社会学科 経営学部市場経営学科
経営学部市場経営学科 情報科学部ディジタルメディア学科
情報科学部ディジタルメディア学科 国際文化学部国際文化学科
国際文化学部国際文化学科 経営学部市場経営学科
経営学部市場経営学科 理工学部電気電子工学科
理工学部電気電子工学科 文学部哲学科
文学部哲学科 経済学部経済学科
経済学部経済学科 生命科学部応用植物科学科
生命科学部応用植物科学科 現代福祉学部福祉コミュニティ学科
現代福祉学部福祉コミュニティ学科 法学部法律学科
法学部法律学科 GIS(グローバル教養学部)
GIS(グローバル教養学部) デザイン工学部都市環境デザイン工学科
デザイン工学部都市環境デザイン工学科 スポーツ健康学部
スポーツ健康学部 経営学部経営学科
経営学部経営学科 文学部英文学科
文学部英文学科 日本統計研究所所長 経済学部経済学科
日本統計研究所所長 経済学部経済学科 法科大学院(専門職大学院 法務研究科) 弁護士
法科大学院(専門職大学院 法務研究科) 弁護士 情報メディア教育研究センター所長/デザイン工学部システムデザイン学科
情報メディア教育研究センター所長/デザイン工学部システムデザイン学科 野上記念法政大学能楽研究所所長
野上記念法政大学能楽研究所所長 大学院理工学研究科生命機能学専攻
大学院理工学研究科生命機能学専攻 大学院理工学研究科システム工学専攻/理工学部経営システム工学科
大学院理工学研究科システム工学専攻/理工学部経営システム工学科 大学院公共政策研究科(サステイナビリティ学専攻)/人間環境学部
大学院公共政策研究科(サステイナビリティ学専攻)/人間環境学部 大学院(連帯社会インスティテュート運営委員長)
大学院(連帯社会インスティテュート運営委員長) 経営大学院(専門職大学院 イノベーション・マネジメント研究科 イノベーション・マネジメント専攻)
経営大学院(専門職大学院 イノベーション・マネジメント研究科 イノベーション・マネジメント専攻) 人間環境学部人間環境学科
人間環境学部人間環境学科 キャリアデザイン学部キャリアデザイン学科
キャリアデザイン学部キャリアデザイン学科 国際文化学部国際文化学科
国際文化学部国際文化学科 現代福祉学部福祉コミュニティ学科
現代福祉学部福祉コミュニティ学科 社会学部メディア社会学科
社会学部メディア社会学科 経営学部市場経営学科
経営学部市場経営学科 理工学部機械工学科機械工学専修
理工学部機械工学科機械工学専修 スポーツ健康学部スポーツ健康学科
スポーツ健康学部スポーツ健康学科 生命科学部応用植物科学科
生命科学部応用植物科学科 経済学部経済学科
経済学部経済学科 社会学部社会学科
社会学部社会学科 文学部哲学科
文学部哲学科 情報科学部ディジタルメディア学科
情報科学部ディジタルメディア学科 法学部法律学科
法学部法律学科 デザイン工学部建築学科
デザイン工学部建築学科