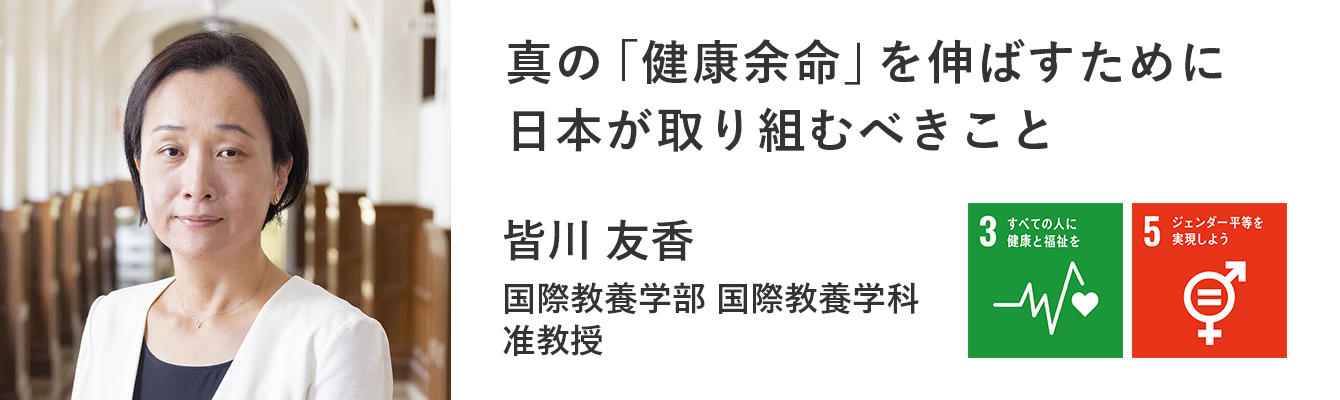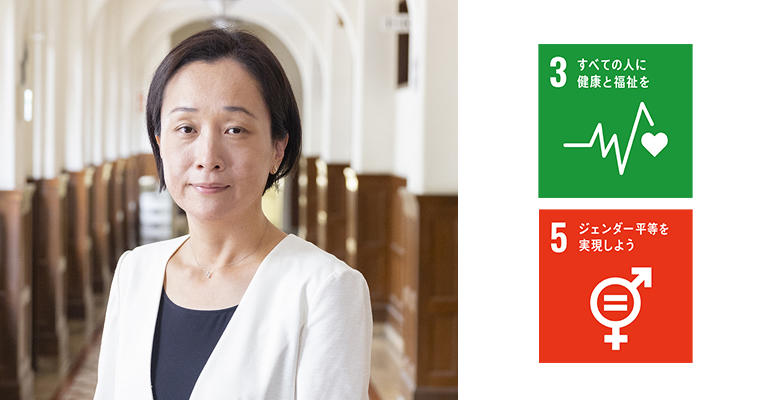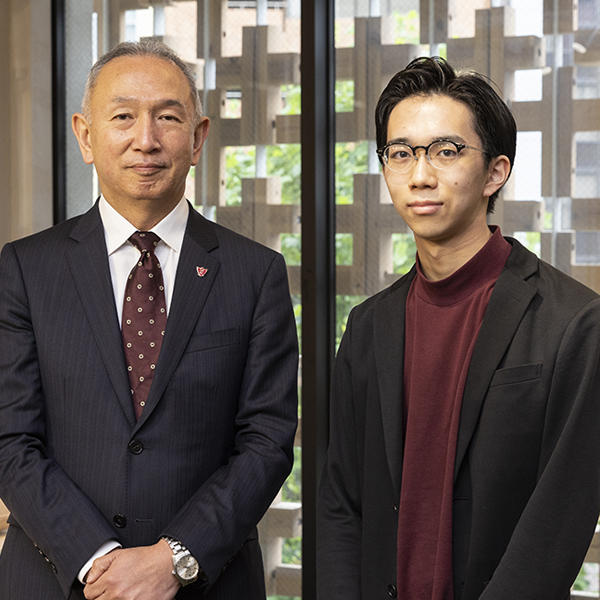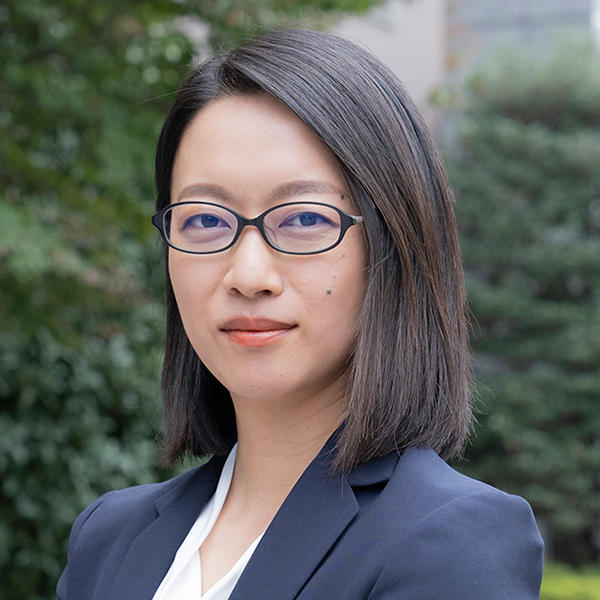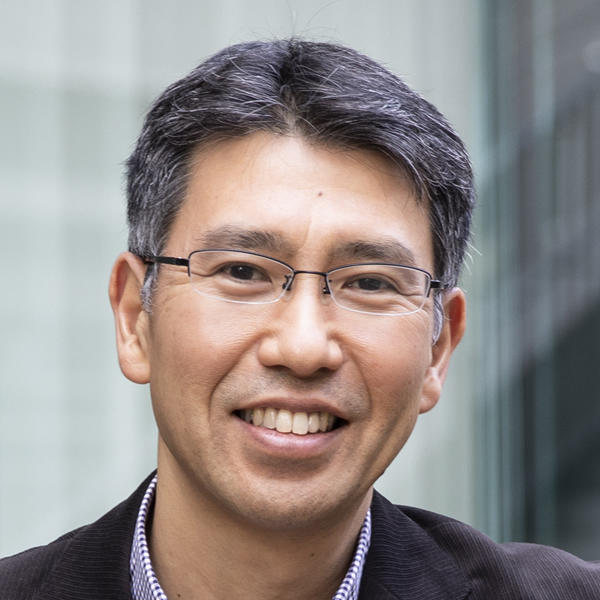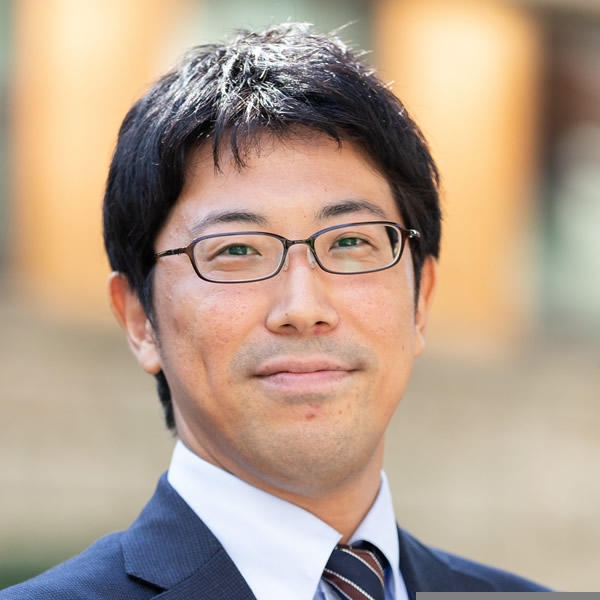読売新聞オンライン タイアップ特集
上智大学の視点
~SDGs編~
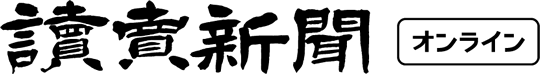
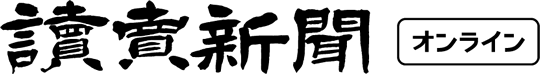
「SDGs」は、2015年9月に国連総会で採択された「持続可能な開発目標」の略称。2030年を達成期限とする、各国が取り組むべき17の目標とその具体的な評価基準169項目が定められている。そこで、上智大学のSDGsにかかわる取り組みを、シリーズで紹介する。

真の「健康余命」を伸ばすために
日本が取り組むべきこと
COVID-19が気づかせたSDGsの意味

米・疾病予防管理センターはこの8月、2021年のアメリカ人の平均寿命が2年連続で低下したと発表しました。その主要因が新型コロナウイルス感染症(以下、「COVID-19」)による死者の急増であることは言うまでもありません。
さらにパンデミックが始まった2020年のデータを見ると、白人に比べてヒスパニックおよびアフリカ系アメリカ人の寿命の短縮幅が大きいことが分かりました。私の専門である社会人口学の観点からは、これによりアメリカ社会における差別・分断の存在があらためて示された、とみることができます。社会・経済的地位の低い人たちは、仕事を思うように休めず、保険もなく、感染した家族を隔離できる住環境もないなど、予防することも十分な治療を受けることも難しいため、COVID-19による死亡率が高くなっていると考えられるのです。(ただし21年の結果では、白人の寿命の短縮幅のほうが大きく、その原因は別途究明する必要があります)
SDGsの17の目標のうち、ゴール3は「すべての人に健康と福祉を」です。そもそもSDGsは国連が主導する取り組みなので、どうしても国家間の協力・支援で解決すべき問題、例えば、COVID-19ワクチンを複数回分容易に確保できる先進国が、貧しい途上国に必要分を回すために何をすべきか、といった問題と結びつけて考えがちです。しかし実は、ワクチンを自国で開発し、大量に確保している先進国の代表たるアメリカにとって、このゴール3はまず自国内での達成に注力すべき目標だったのです。
翻ってここ日本では、パンデミックという異常事態に対し一時的な医療崩壊状態は防げずにいるものの、国民皆保険制度はなお維持され、希望者へのワクチン接種もまずまず公平に行われており、ゴール3はほぼ達成されているかに見えます。しかし私は、他のゴールとも関連する大きな問題を、COVID-19が浮かび上がらせているのではないかと思うのです。
「健康」のジェンダーギャップ

出生・死亡・移動の3要素がどう関係しあって国・地域の人口に変化をもたらすかを研究する学問が人口学です。視点の違いにより生物人口学・政治人口学・歴史人口学などに枝分かれしていますが、社会・経済的要因に注目するのが、私が専門とする社会人口学です。
私が特に関心を持っているのは人の健康状態。ある人がこの先生きられるであろう年月=平均余命のうちで、健康に暮らせる期間=健康余命をいかに伸ばすか、という視点で研究を進めています。
日本政府が公表する健康余命の推計には、主に厚生労働省の「国民生活基礎調査」の結果が用いられるのですが、健康状態を定義する際、疾病の有無や、健康状態の日常の動作への影響に主眼が置かれています。しかし、病気や障害による支障があっても生活に満足している人と、診断された病気や障害がなくても日々不満や苦しさを感じている人の、どちらが「健康」だと言えるのか----そこで、より主観的・包括的な視点から、いわば満足度・幸福度を含めて「健康」を捉え直し、健康余命を算出・活用しようという流れが強まっています。
そんな新しい目で日本社会を眺めてみると、どうなるでしょう。
SDGsの中でわが国が達成から最も遠いのは、ゴール5「ジェンダー平等を実現しよう」です。世界経済フォーラムが発表するジェンダーギャップ指数(2022年版、1.000が完全平等)を見ると、総合で0.650(対象146カ国中116位)、とりわけ「政治」分野の0.061が足を引っ張っています。ところが「健康」分野は0.973、ほぼ平等という評価。果たして本当でしょうか?
家庭内の性別役割分業が今なお根強く維持されているこの国では、働く女性は、男性と同じ仕事をこなしたうえで、家に帰ると家事・育児の多くを負担しなければなりません。それによるストレスや疲労が彼女たちの「健康」を、病名はつかないけれど、どれほど損ねていることか。
そしてCOVID-19は、日本でも問題を浮き彫りにしました。子供の健康を守るための休校・休園といった措置が、働く母親に多くの負担を強いたことで、彼女たちの実情に改めて注目が集まったのです。
それでもこの国に、「健康」についてのジェンダーギャップはないと言えるでしょうか? あるいは、前述のゴール3はすでに達成され、男性・女性ともに身体・精神的に健康な状態にあると、私たちは胸を張れるのでしょうか?
後の「コーホート」のためにやるべきこと

私自身、小さな子を持つ母親ですから、先に述べたことはまさに実感しています。といっても、私が籍を置く上智大学国際教養学部は、同僚教員の多くが外国人、または外国で学位を取得しており、私のような立場の女性に対する理解がある、とても恵まれた職場なのです。働く母親の多くは、私よりはるかに過酷な環境の中で、もっともっと「健康」をむしばまれているに違いありません。
社会人口学では、ある年に生まれた集団を他と区別する「コーホート」(日本語では「世代」に近い)という考え方を重視します。その集団に属する人々が、一生という「線」の中で、大きな社会の変化やイベントという「点」をどのようなタイミングで経験し、それが価値観や行動パターンにどのような影響を与えるか、そして他のコーホートとの間にどのような違いが生まれるかを分析・考察するのです。例えば、ウクライナ侵攻についてのロシア人の世論調査結果からは、1991年のソ連崩壊という一大イベントを何歳で経験したかが、各コーホートの意識に非常に大きな影響を与えていることが、はっきりと読み取れました。
さて、あるコーホートは当然先立つコーホートをじっと見て、その影響も受けて価値観を形作ります。ゆくゆくは専業主婦になることを望む若い女性が増えているという調査結果がありますが、仕事と子育ての両立に苦労する先輩コーホートの姿を見ているのですから何の不思議もありません。
でも私は、学生たちにあえて自分の子育てについて話すようにしています。緊急事態宣言下でオンライン授業だった時には、後ろから聞こえてくる子どもの声や足音から、学生たちは仕事と家庭を両立させる難しさを感じたことでしょう。ただ、それであきらめてしまう人ばかりでなく、自分もやってみよう、そして男性も女性も「よりよく、より健康に」生きていくために現状を変えなければ、と前向きな意識を持つ人も必ずいると信じています。
日本をSDGs後進国へと落ち込ませないためにも、彼女ら・彼らを動かすべく、発信を続けていきたいと思っています。
2022年10月3日 掲出

-
皆川 友香 国際教養学部 国際教養学科 准教授
1979年京都市生まれ。
2004年上智大学外国語学部ロシア語学科卒業。2008年ハーバード大学大学院ロシア・東欧・中央アジア地域研究専攻修士課程修了。2013年テキサス大学オースティン校大学院社会学専攻博士課程修了。博士(テキサス大学)。
早稲田大学高等研究所を経て、現在、上智大学国際教養学部国際教養学科准教授。
専門は社会学・社会人口学。日本、およびロシア・旧ソ連諸国を対象に、社会・経済的属性にみる健康格差のメカニズムについて研究している。アメリカ人口学会、アメリカ社会学会、日本人口学会、家族社会学会等に所属。
上智大学では、社会人口論、社会調査法、量的分析手法、日本社会論等を担当している。
[広告]企画・制作 読売新聞社ビジネス局
上智大学の考える未来
上智大学の視点 ~SDGs編~
ニュースを紐解く