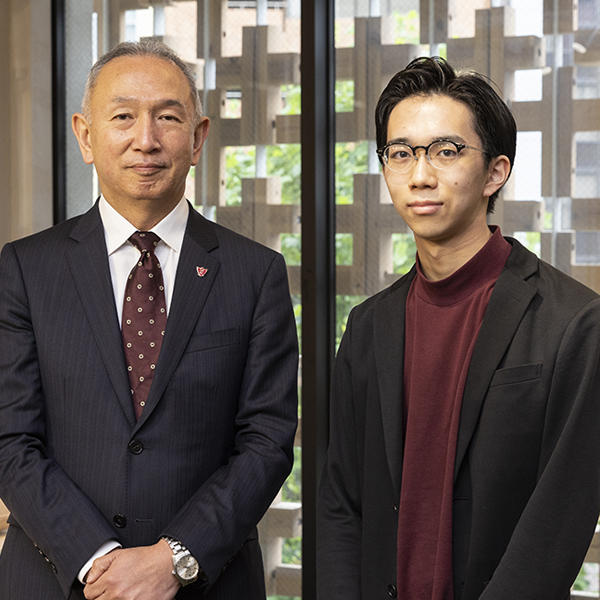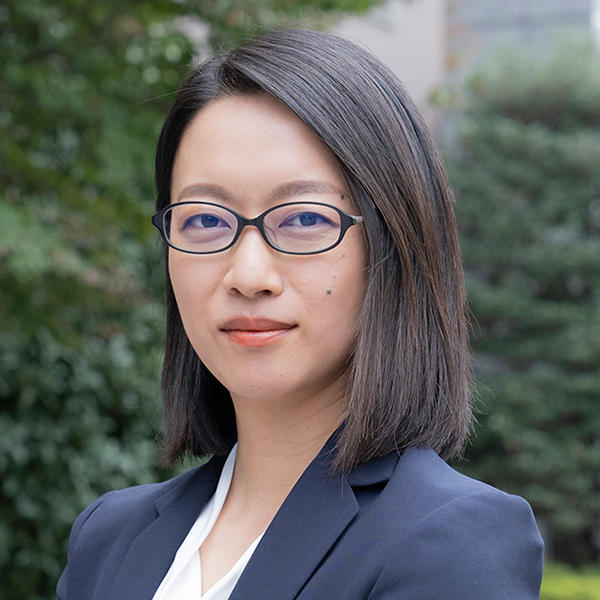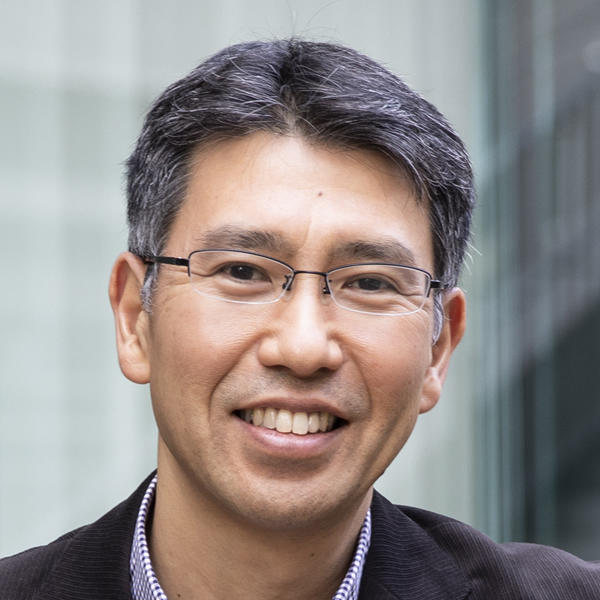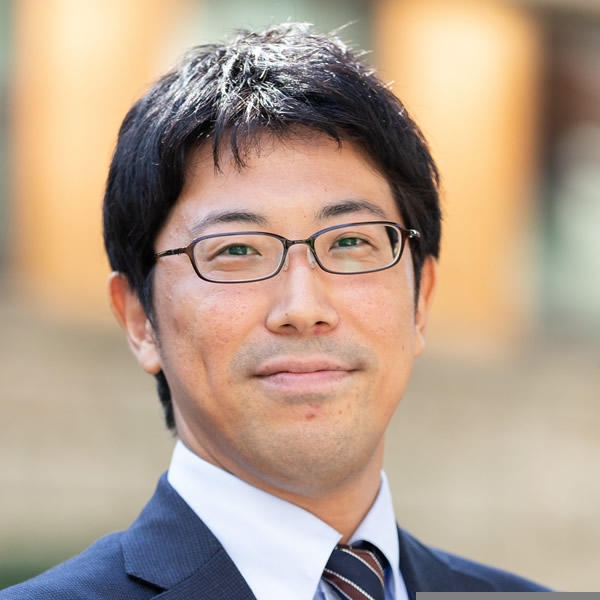読売新聞オンライン タイアップ特集
ニュースを紐解く
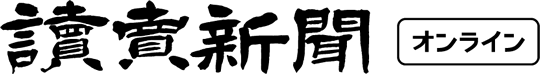
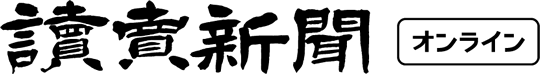
いま、世界で、日本で何が起きているのか。
政治、経済、教養、科学など話題のニュースを上智大学の教授が独自の視点で解説します。

現代の「祭り」が抱えるジレンマ
受け入れてうまくつきあう工夫が必要
芳賀 学 総合人間科学部 社会学科 教授
生活が変われば祭りも変わる

2018年は終盤に、「祭り」に関連する2つのニュースが話題となりました。1つは、秋田の「なまはげ」などいくつかの地域の行事が、「来訪神 仮面・仮装の神々」としてユネスコの無形文化遺産への登録が決まったこと。もう1つは、東京・渋谷のハロウィン・イベントで、軽自動車を横転させた若者たちが逮捕されたこと。いずれも単純にメデタシメデタシとはいえない出来事であると、私は思っています。
まず後者の問題を取り上げますが、そもそも祭りの重要な機能は、「非日常性」の提供です。ほとんどの人間にとって、社会に完全に適合することは不可能ですから、日常生活の中で必ずストレス、「憂さ」のようなものが溜まってくる。これは昔も今も変わりません。それらが爆発・暴走しないよう、適度にガス抜きし生きている実感を得るための非日常の時間/空間が必要となるのです。
したがって祭りは、日常の中で大切にされる価値をあえて否定するような、それらとは正反対の要素――たとえば静穏に対して喧噪、安全に対して危険、節約に対して浪費など――を必然的に含みます。ただし、一方で、祭りも「正常」な社会生活の一部ですから、それらの要素は一定のルールのもとでコントロールされます。
私たちの日常生活は時代とともに変化するので、その裏返しである非日常も当然変化することになります。それまで非日常だったものが日常に組み込まれてしまう、あるいは、それまで許されていた非日常が許されなくなる、といったことが起こると、それに伴って祭りも変化するわけです。
こうした変化は今に始まったことではありません。たとえば徳島の阿波踊りも、400年といわれるその歴史の中で少しずつ変化し、現在のような踊り方になったのはここ半世紀ほどのことと言われています。
ただ近年に特徴的な変化として、祭りの地域からの「離陸」という現象が、各地で急速に進んでいることは確かです。
「祭りは盛り上がれればいい」にも一面の真実あり

もともと祭りは地域共同体のもの、地域の中で行なわれ、地域の人が参加し、地域の人が観るものでした。ですから、許される非日常の範囲――たとえば騒音とか、喧嘩とか、器物の損壊とか――については自然に了解ができていましたし、それを越えてハメをはずし過ぎた若者には、大人や長老が叱りつけるといった形でコントロールも可能でした。
しかし、人の移動が盛んになるにつれて、まずは祭りの観客に地域外の人間が増えていきます。これが「離陸」の第一段階で、一部の祭りでは古くから進んでいましたが、第二次大戦後に日本の有名どころの多くの祭りが経験するところとなりました。
さらに80年代以降は、全国の多くの祭りで参加者やパフォーマーにも地域外の人間が取り込まれるようになっていきます。そして最後には、祭りの舞台までもが地域を飛び出し全国各地に拡がるものが現れました。阿波踊りや高知のよさこい祭りはその典型で、最近は沖縄のエイサー、岐阜の郡上踊りなどがそれに続きつつあります。
一方、東京などの大都市には、そもそも地域共同体に属していない住民がたくさんいて、この人たちも前述のような意味で非日常を欲しています。むろん都会では、連日様々なイベントが開催されて、一定の非日常が常に提供されています。しかし、それらはやがて日常の一部と化してしまい、人々はそれとは異質な非日常を求めるようになる。そして、他の地域から「輸入」される祭りや、例えば渋谷のハロウィンのような、これまでにない形の祭りが、それに応えるものとなります。
こうした祭りは、当然地域文化や宗教的伝統などとは切り離されています。これに対して、「盛り上がれれば何でもいいのか」と疑問を感じる人もいるでしょう。しかし、長い伝統を持つ祭りも、参加する人たちは、まず第一に盛り上がりを、つまり非日常を求めて参加してきたわけで、それが本来の祭りの姿であり、「伝統」とはそれが長年続いてきた結果なのだと思います。
「厄介」を排除しても解決にはならない

ただし、このように地域を「離陸」した祭りや新たに創りだされた祭りは、かつての地域の祭りのように、必ずしもその場の全員が非日常性を受け入れ、共有しているわけではありません。その結果、参加者や観客の非日常と、周辺住民や一般社会の日常を無理やり同居させることになり、そこに何らかの軋轢が生じることは多くの場合避けられないのです。
では、たとえばドームや公園など閉鎖された空間に祭りを隔離すればよいのでしょうか。おそらくそれでは、一般的なコンサート程度に非日常性が薄められてしまい、異質性を求める参加者や観客を満足させることはできなくなるでしょう。また、非日常性を社会から強制的に排除しすぎれば、それが「地下に潜る」形で実現され、いよいよコントロールが効かなくなるおそれさえあります。
私は、今は過渡期であって、解決策は見つかるはずだと考えています。問題を起こす祭りを、厄介者として安易に排除するのではなく、それが果たしてくれる大切な機能をうまく生かせるように、社会全体で知恵をしぼるべき時です。
一方、冒頭に掲げたもう一つの出来事、祭りや行事の世界遺産化は、別種のジレンマを抱えています。
周知のとおり、地域の伝統文化の中には、過疎化などにより元々の共同体だけで維持することが困難なものもたくさんあります。世界遺産にすることで観光資源としての価値を高め、伝統の維持、ひいては地域の存続につなげようという考え方は十分に理解できます。
ところが、祭りをはじめ、庶民の間で育まれた伝統文化は、そこに、例えば「性」にかかわる表現のようなきわめて猥雑なもの、非文明的とマイナスに評価されかねない要素が含まれる場合も少なくありません。世界遺産として胸を張り、多くの観光客を呼ぶためには、このような不都合な要素を徹底的に排除すること、いいかえれば自らの手で伝統文化を変質させることも場合によっては必要となります。
まるごと滅びさせるよりは一部でも生き残らせるべきであるのか、あるいはそのまま保存していく方法が他にあるのか、そもそも保存すべきかどうかも含めて、こちらもまた、簡単には答えの出ない問題です。この点でも私たちの知恵がまさに今試されているのです。
2018年12月26日 掲出

-
芳賀 学(はが まなぶ)総合人間科学部 社会学科 教授
1960年東京都生まれ。1984年東京大学文学部社会学科卒業、1987年東京大学大学院社会学研究科修士課程修了、1990年同博士課程満期退学。社会学修士。
東京学芸大学教育学部助手を経て、1994年4月上智大学文学部社会学科専任講師として着任。1999年4月同助教授、2005年4月総合人間科学部社会学科助教授、2006年4月より現職。
2009年4月から2013年3月まで大学院総合人間科学研究科委員長、2017年4月から総合人間科学部長。
専門は宗教社会学、文化社会学。現在は、祝祭の現代的変容に関する研究に取り組んでおり、現代日本社会における新たなコミュニティの可能性について模索している。日本社会学会、日本宗教学会、関東社会学会、「宗教と社会」学会などに所属。
主な著書に、『若者の現在』(全3巻・共編著、2010年~2012年)、『本を生みだす力』(共著、2011年)、『仏のまなざし、読みかえられる自己』(共著、2006年)などがある。
[広告]企画・制作 読売新聞社ビジネス局
上智大学の考える未来
上智大学の視点 ~SDGs編~
ニュースを紐解く