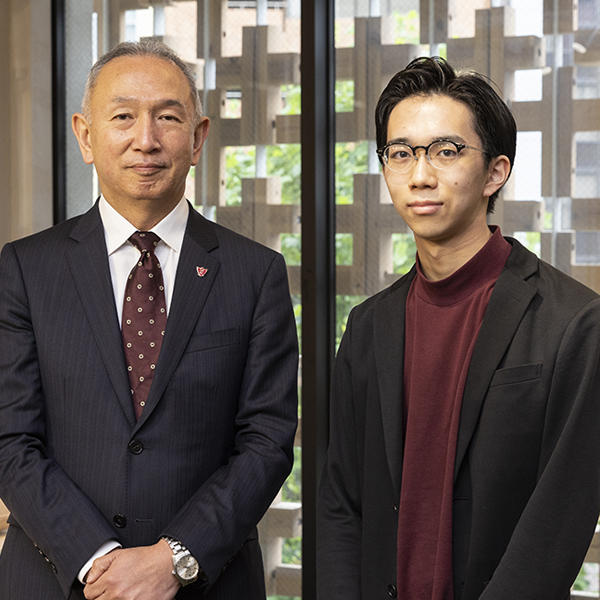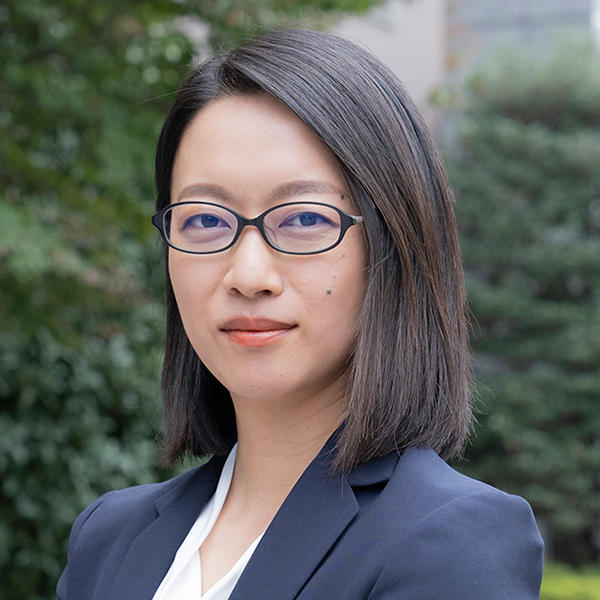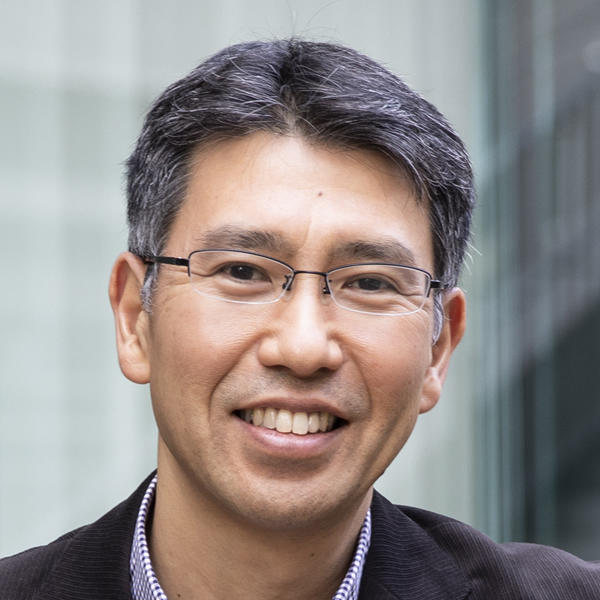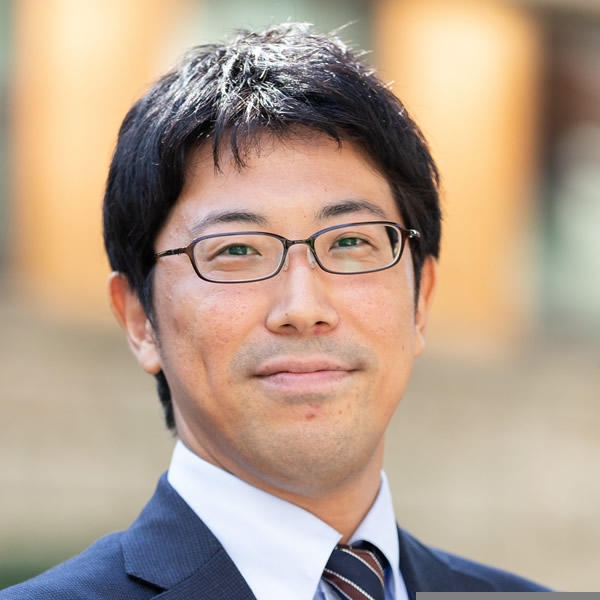読売新聞オンライン タイアップ特集
ニュースを紐解く
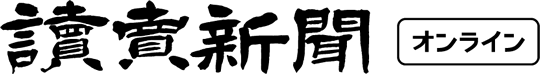
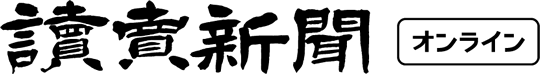
いま、世界で、日本で何が起きているのか。
政治、経済、教養、科学など話題のニュースを上智大学の教授が独自の視点で解説します。

「問いを立てて考える」本来の哲学が
いまこそ必要とされている
寺田 俊郎 文学部 哲学科 教授
意外な本がベストセラーに

昨年の年間ベストセラーは『漫画 君たちはどう生きるか』(マガジンハウス刊)でした。戦前に吉野源三郎によって書かれた児童小説を、その発表から80周年にあたる一昨年に芳賀翔一がマンガ化したもので、原作の小説のほうもベストテン入りを果たしています。
ご存じかと思いますが、同書は中学生の主人公、通称・コペルくんが、学校や家庭や、あるいは友人との交流の中で出会うさまざまな出来事を通して、法学士である叔父さんの教えも受けながら、生きる上で大切なことを学んでいくという内容です。マンガになったとはいえ、説教めいていて敬遠されそうなこの本が大ヒットしたことは、やはり驚きです。
これについて、だれもが漠然と疑問や不安を感じながらものが言いにくい、そんな昨今の世相が、戦争前夜だった執筆当時のそれと似ているから、という指摘があります。私も同感する部分はあるのですが、実証的な研究抜きに分析を試みることはやめておきます。
それより私が同書をあらためて読み直して感じたのは、この本がとても「哲学的」だということ、そしてそれが多くの人の心をとらえた一因ではないか、ということでした。といっても、いわゆる哲学的な、深遠なテーマばかりが取り上げられているわけではありません。
少年時代にだれもが抱くようなコペル君の疑問や悩みに対し、叔父さんは自分の考えを述べはしますが、そこで終わらない。どんな偉人の言葉・思想であっても、自分自身の体験、そこで感じたことを出発点にそれについて自ら考えるのでなければ、その真の意味は理解できないのだと、自ら考え続けることを強く促すのです。
よく名言や教訓、あるいは理想や理念などが「人生哲学」「経営哲学」などのように「〇〇哲学」と呼ばれることがありますが、それらはいわば哲学の副産物であって、哲学の本質は、それらを導くために問いを立て、考える行為そのものにあると、私は考えています。その意味で『君たち~』は、本来の意味での哲学にいざなう本といえるでしょう。
昨年の出版界ではほかにも、『考えるとはどういうことか:0歳から100歳までの哲学入門』という新書がベストセラーになり、『ニューQ "新しい問いを探す哲学カルチャーマガジン"』という雑誌が創刊されるなど、この国で私の思う「哲学」が求められていることをうかがわせる出来事がありました。もし、そうだとすると、その理由は何なのでしょうか。
苦手な哲学を日本人が必要とする理由

あらためて振り返ると、昨年は財務省による公文書改ざんを筆頭に、政治・行政の深刻なモラルハザードがクロ−ズアップされた1年でした。また、差別的・ヘイト的発言、弱者を切り捨てる妙な「自己責任論」などが、ネットだけでなく一般メディアにも流布するようになってしまいました。正義、公正、弱い者への思いやり、あるいは民主主義や社会的公平といった、私たちが当たり前に信じてきた価値が、音を立てて崩れ去った年といっても過言ではないでしょう。むろんこれは、徐々に進んでいた事態が一気に表面化した、ということなのだと思いますけれども。
実は日本人は、自ら問いを立てて考える「哲学」を、これまで得意にしてこなかった、と私は考えています。空気を読んで和を保つことが重んじられ、下手に正論をもって異を唱えると「理屈をいうな」と非難される、そういう文化だからです。その土台には、同質的な文化の中で、価値観が共有できているという暗黙の了解があるように思います。
いま、そのような了解が思い込みにすぎないことに人々が気づき始めている。そのなかで、多くの人が大きな不安や恐れを感じ、自分の中に秘めていた問い、たとえば生きる意味、自分が社会の中で果たすべき役割、正義とは、公平とは......そんな「問い」たちがアタマをもたげ、自ら答えを求めずにはいられなくなっているのではないでしょうか。また、お互いに空気を読みあい、異論や問いを「理屈を言うな」といって封じる文化は、息苦しいだけでなく、多様な人々の共生を危うくし、創造的な活動を妨げます。そのことにも、人々は気づき始めているのではないでしょうか。
そのような事情も、『君たちは~』のヒット、あるいは前述の新書の人気や雑誌の創刊などの背景にあるように思います。問いを立て考える哲学が必要とされるゆえんです。
子どもにもおとなにも「哲学する」場を
ところで、『君たちは~』の中にこんな一節があります。
叔父さんがコペル君に宛てた手紙の中で、学校の修身(道徳)の時間に教わることは大切だけれど、それに黙って従うだけでは、「ただ『立派そうに見える人』になるばかりで、本当に『立派な人』にはなれないでしまうだろう」と語るのです。
周知の通り、「道徳」が国語や理科などとならぶ一つの教科として、2018年から小学校で、2019年度からは中学校でも教えられることになりました。この改編を強力に推し進めた人々の中には、前述のモラルハザードを引き起こした当事者が含まれていた、という皮肉な事情はさておき、問題は現場での教え方です。文科省の指導要領では、自分で考える力を養うことが謳われてはいるものの、最終的に何らかの形で評価することが求められる以上、「正解」を押し付けて○か×をつけてしまう、そして、「立派そうに見える人」ばかりを育てることになってしまうのではないか、という懸念を抱かずにはいられません。
私はいくつかの小学校と高校で、不定期ながら「哲学する」授業を持たせてもらっています。使っているのは、20世紀後半から世界中で使われており、最近日本でも注目されている「子どもの哲学」(「子どものための哲学」)という手法なのですが、基本的には一つの問いについて、10人ほどのグループの中で対話をします。自分が当たり前と思っていたことに対して、実は多様な考え方があることを発見し、それを楽しめるようになっていくだけでなく、他人の話をきちんと聞き、自分の意見をわかりやすく述べる態度も身についていきます。ちなみに、子どもたちが立てた「問い」の中でこれまでの傑作というと、小学校では「将来の夢は持たなければいけないのか?」、高校では「個性ってそんなにいいことか?」というものです。
このような手法が、子どもたちが自由に考えることを妨げない評価方法の工夫とともに、道徳の授業に取り入れられることを願いたい。そして子どもたちだけでなく、たとえば私が取り組んでいる「哲学カフェ」のように、おとなが気軽に「哲学できる」場も増えていってほしいと思います。それに少しでも役立つことができれば、と願って哲学的対話の活動を続けています。
いま私たちがこのような意味での哲学を必要としていること、そして哲学がこの社会をよい方向に向かわせてくれることは、おそらく間違いないのですから。
哲学の研究と「哲学する」こと

ここまで話を聞いて「あれ、哲学の研究はどこにいっちゃったんだろう」といぶかしく思う人もいるかもしれません。
私は、ふだんは、哲学を研究し、哲学の専門科目を教えています。主な研究分野は18世紀ドイツの哲学者、イマヌエル・カントの哲学です。そのなかでも、とくに実践哲学と呼ばれる分野に関心があります。実践哲学とは、道徳哲学、政治哲学、法哲学など、人間の行為に関わる哲学です。その関係で、近現代の他の哲学者の実践哲学にも関心があります。最近はカントの永遠平和論を中心に研究しています。
そして、もう一つの研究分野に、いちおう、臨床哲学というものがあります。臨床哲学とは、一言で言えば、現実の問題が生じる社会の現場で哲学的に考える、ということです。「いちおう」と言ったのは、臨床哲学は、正確に言えば、哲学の研究分野というよりも、哲学の活動だからです。哲学を研究するというよりも、哲学をやってみる、ということです。哲学カフェを開いたり、学校や企業に行って哲学的な対話をしたりするのは、その活動の一環なのです。もっとも、その活動について学問的に反省して論文を書くこともあるので、半分は研究分野といってもいいかもしれません。
カント哲学の研究と臨床哲学の活動は、ぼくのなかではつながっています。それを説明し始めると時間がかかりそうですが、手短かに言うと次のようになります。
哲学は、要するに、人が生きるなかで出会うさまざまな問いを、立ち止まって、ゆっくり、じっくり掘り下げて考えることです。考えることができる人なら、だれでもできること、きわめてシンプルなことです。ところが、いったん真剣に考え始めると、私たちがふだん当たり前だと思っていたことが当たり前ではないことに気づき、多くの問いがそう簡単に答えの出ない問いであることに気づきます。考えても、考えても、元の問いに戻ってきたり、新しい問いが出てきたりする。途中で耐えられなくなったり、空しくなったりしそうです。そこが難しいところです。それでも考え続けることの意味は、先ほどお話ししました。
過去の哲学者たちがしていたことも、基本的には同じことです。ただ、歴史に名を残すような哲学者たちは、鋭い切り口で問いを立て、驚異的なねばり強さで徹底的に考え、問いを掘り下げ、なかなか常人の行けないところまで行き着くことがあります。そのたくましい思考の展開に、なかなかついていけなくて、哲学書は難しい、ということにもなります。
しかし、彼らとじっくり、ゆっくり対話しつつ考えることによって、私たちが一人では行けなかったところまで行くことができる。過去の哲学者も、その作品も、何か有難いことを教えてくれる先生というより、哲学するための対話の相手だと考えたほうがいいのではないか、と思っています。過去の哲学者とその作品が、私たちの対話の相手であり、ともに「哲学する」仲間であることを伝えることも、哲学研究の専門家の大切な役割だと考えています。
ちなみに、カントの有名な言葉に「人は哲学を学ぶことはできない、せいぜい哲学することを学ぶことができるだけだ」というのがあります。過去の哲学者の思想を学ぶことにとどまらず、「哲学すること」が真の哲学だ、と読むことができます。
2019年2月1日 掲出
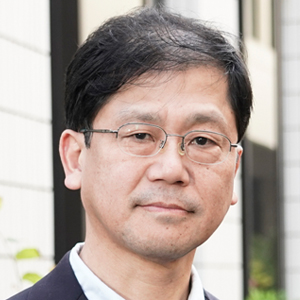
-
寺田 俊郎(てらだ としろう)文学部 哲学科 教授
1962年広島県生まれ。1991年京都大学大学院文学研究科博士課程学修退学、2004年大阪大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。
洛星中学・高等学校教諭、明治学院大学一般教育部助教授、同大学法学部准教授を経て、2010年4月上智大学文学部哲学科教授に着任。
研究分野は近現代の実践哲学、臨床哲学、哲学的対話の理論と実践。日本哲学会、日本倫理学会、日本カント協会、日本応用哲学会などに所属。哲学的対話の活動としては、任意団体「カフェフィロ」、NPO法人「こども哲学・おとな哲学 アーダコーダ」に所属。小・中・高等学校、企業、街角のカフェなどで哲学的対話を実践する。
主な著書に、『グローバル化時代の人権のために--哲学的考察』(共著、2017年)、『哲学カフェのつくりかた』(共著、2014年)、『世界市民の哲学』(共著、2012年)など多数。
[広告]企画・制作 読売新聞社ビジネス局
上智大学の考える未来
上智大学の視点 ~SDGs編~
ニュースを紐解く