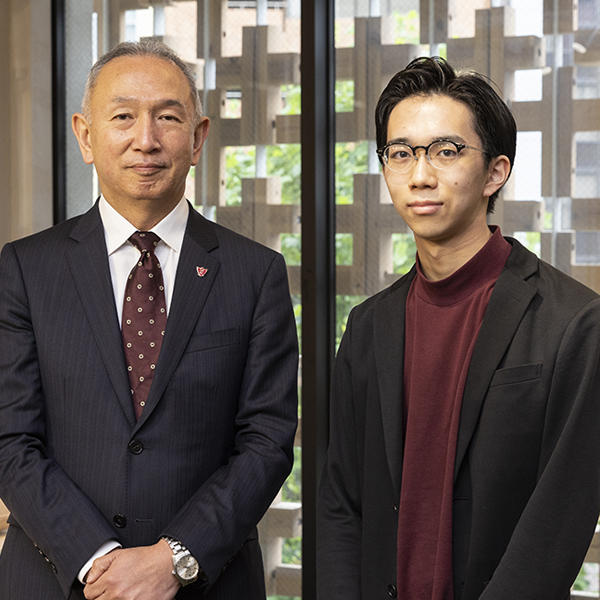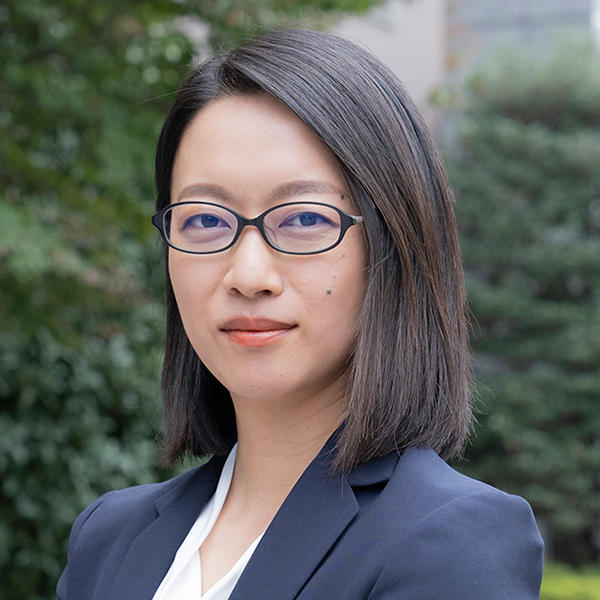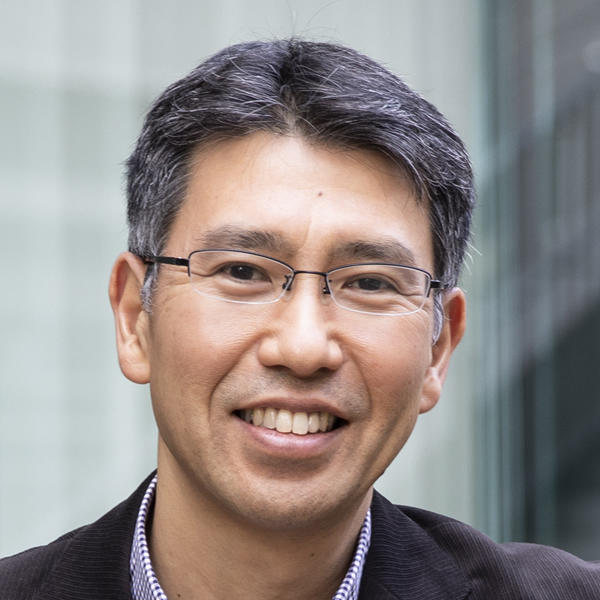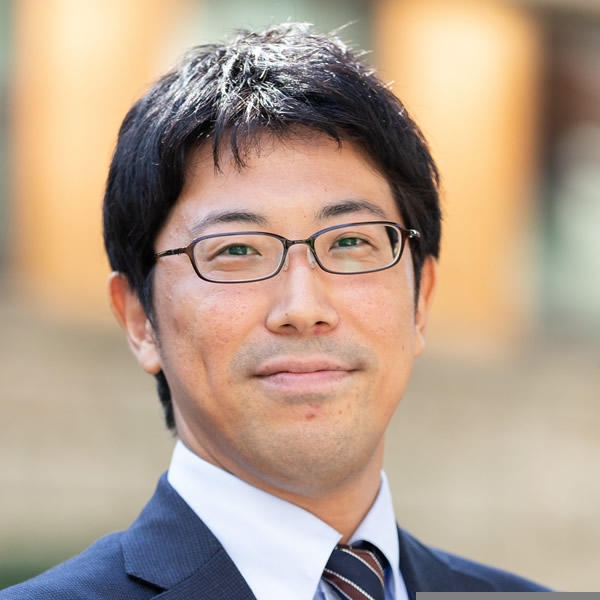読売新聞オンライン タイアップ特集
ニュースを紐解く
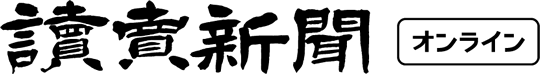
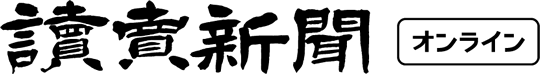
いま、世界で、日本で何が起きているのか。
政治、経済、教養、科学など話題のニュースを上智大学の教授が独自の視点で解説します。

未来を担う人材を育てる
教育改革に世論の後押しを
奈須 正裕 総合人間科学部 教育学科 教授
学力の意味をとらえ直す学習指導要領の改定

この春、2020年度以降に適用される小・中学校の新学習指導要領が公示されました。
小学校の英語教育の拡充やプログラミング教育の導入など、目につく変更点もありますが、今回の改定が大きな転換といわれる所以は、もっと別のところにあります。
一時期、低下傾向が心配された日本の子供たちの学力ですが、実は現在のところ大変堅調です。それは毎年実施されている全国学力テストはもちろん、「国際学習到達度調査(PISA)」、「国際理科数学教育調査(TIMSS)」の結果などに、はっきりと表れているのです。これは、危機感を抱いた教員はじめ教育関係者、そしてなにより子供たち自身の努力によるものですが、2008年に改定された現行の学習指導要領がうまくいっているということでもあります。
ですから今回の改定は、教科ごとの内容や分量ではなく、教育全体の「質」を変えることに重点が置かれました。
要素的な知識を教え、蓄積させることから、人生の中で直面する多様な問題を主体的・協働的・創造的に解決できる「資質・能力」を身に付けさせることに目標を移すのです。そのために、各教科に特有の見方・考え方を習得させることを重視し、また、子供たちがディスカッションやグループワークを行う「アクティブ・ラーニング」の手法を積極的に取り入れます。
いわば「学力とは何か」を改めて問い、捉え直すこうした改革は、グローバル化、AI化など目まぐるしく変化する現代において、10年後、20年後の日本を担う人材を育てなければいけないことを考えれば、まさに急務といえます。
「ゆとり世代」の先生たちが力を発揮する

欧米の教育は、すでに前述のような方向性に切り替わっていますから、海外の優れた先行事例に学ぶことはできます。しかし、こういった実践の伝統が日本にはないという理解は間違いです。わが国の教育の歴史を紐解くと、たとえば大正デモクラシー期の「大正自由教育運動」をはじめ、草の根的な取り組みの中に数多くの豊かな実践資産を見出すことができます。これらを発掘し、現代的な文脈の中に位置付け直すことで改革を側面支援することは、私たち教育学者の責務です。
それでも、現場での対応は容易ではないでしょう。教員を志す人の多くは、自身が学校でとてもよい体験をし、それゆえ自分が受けた教育に対して非常に肯定的なのです。これはむろん悪いことではありませんが、教育の内容や方法を大きく変えようというときには、先生のこうした意識が障壁ともなりかねません。
その意味で、私が期待をかけているのは、20~30代、いわゆる「ゆとり世代」の若い先生たちです。
文部省(当時)の理論武装の甘さや準備不足もあり、結果的に学力低下を招いたとの批判を受けて頓挫した形の「ゆとり教育」ですが、その本来の目的は、知識詰め込み型の教育を見直し、思考力、判断力、あるいは個性的な表現力を延ばすことでした。つまり、今回の新学習指導要領の理念にそのまま繋がっているのです。その理念を、試行錯誤の段階だったとはいえ、当時の先生たちの懸命な努力を通して肌で感じていた子供たちが、いま先生になってきているわけです。
彼らが自分たちの体験を、新学習指導要領に基づく教育に重ね合わせ、今度こそその理念を活かす道を見つけて、改革を牽引してくれるのではないかと、私は考えています。とにかく、日本の先生の潜在力はすごいですから。
ただ、そうした先生たちの力だけではどうしようもない大きな問題が、一つ横たわっています。
教員の「働き方改革」は不可欠

静岡県吉田町が、公立小・中学校の夏休みを16日程度に短縮するという大胆な案を打ち出した、というニュースは記憶に新しいところです。最大の理由は、先生の残業時間をいかに減らすかという問題でした。
日本の先生の過重労働は、勤務時間を海外と比べてみれば歴然としています。そしてその過剰な労働の多くが、授業やその準備以外の業務に費やされています。先生たちが新しい教育にきちんと取り組みたいと願ったとしても、それに備える時間的余裕が与えられないのでは、改革は「絵に描いた餅」に終わります。
これに対して、吉田町は「夏休みは長いもの」という固定観念をいったん脇において解決策を考えてみた。私はこの解決策それ自体を全面的に支持はしませんが、これくらいの大胆な選択肢も視野に入れるという発想には大きな意味があります。しかし、教育現場の「働き方改革」を本気で実現するためには、やはり先生の業務の中身を、根本的に見直すことが不可欠でしょう。たとえば、放課後や休日の学校外での生徒の行動については、担任教師ではなく保護者が第一に責任を持ち、さらに地域社会がそれをサポートするという、ごく当たり前な姿に戻せないか。もちろん、こうした見直しは学校だけでできることではなく、残念ながら時間もかなりかかりそうです。
ただ、その気になればすぐにも着手できる分野もあります。たとえば部活動は、顧問としての監督・指導が、時間的に先生たちの大きな負担となっている一方、生徒数の減少により、一つの学校が多種多様な部活を維持することも難しくなりつつあります。そこで、学校が部活を手放し、これをクラブスポーツのような形で地域が引き受けて、周辺の学校の生徒たちだけでなく高齢者なども参加できるようにすれば、先生の労働時間削減に加え、子供の選択肢も増え、高齢者福祉や地域の活性化にもつながる。実際こうした試みを始めている自治体もあります。
繰り返しになりますが、日本の将来を担う子供たちを育てるためには、新学習指導要領に沿った教育は不可欠であり急務です。教育現場だけでなく、保護者をはじめ国民一人一人が、この改革の意義を考え、前提となる先生の「働き方改革」と併せて、世論として後押ししていただきたいと願っております。
2017年10月2日 掲出

-
奈須 正裕 総合人間科学部 教育学科 教授
1961年徳島県徳島市生まれ。1985年徳島大学教育学部卒業、1992年東京大学大学院教育学研究科博士課程教育心理学専攻を単位取得退学。博士(教育学)。神奈川大学助教授、国立教育研究所教育方法研究室長、立教大学教授などを経て2005年より上智大学総合人間科学部教育学科教授。全国各地の小中学校をフィールドとして、カリキュラムと授業に関する実践開発的な研究を進めている。
中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会、教育課程企画特別部会、総則・評価特別部会、幼児教育部会、中学校部会、生活・総合的な学習の時間ワーキンググループ、小学校におけるカリキュラム・マネジメントの在り方に関する検討会議、小学校段階における論理的思考力や創造性、問題解決能力等の育成とプログラミング教育に関する有識者会議、2020年代に向けた教育の情報化に関する懇談会等の委員として、新学習指導要領を巡る議論に関わってきた。
主な著書に『「資質・能力」と学びのメカニズム』(東洋館出版社)、『教科の本質から迫るコンピテンシー・ベイスの授業づくり』(図書文化社)、『シリーズ 新しい学びの潮流(全5巻、編集代表)』(ぎょうせい)、等。
[広告]企画・制作 読売新聞社ビジネス局
上智大学の考える未来
上智大学の視点 ~SDGs編~
ニュースを紐解く