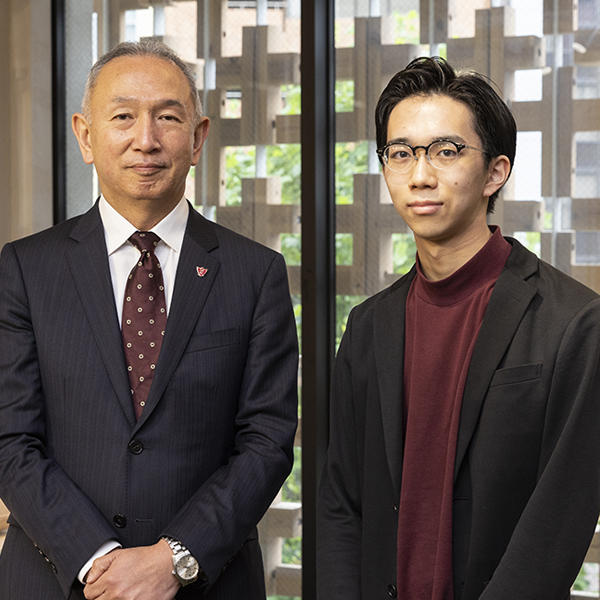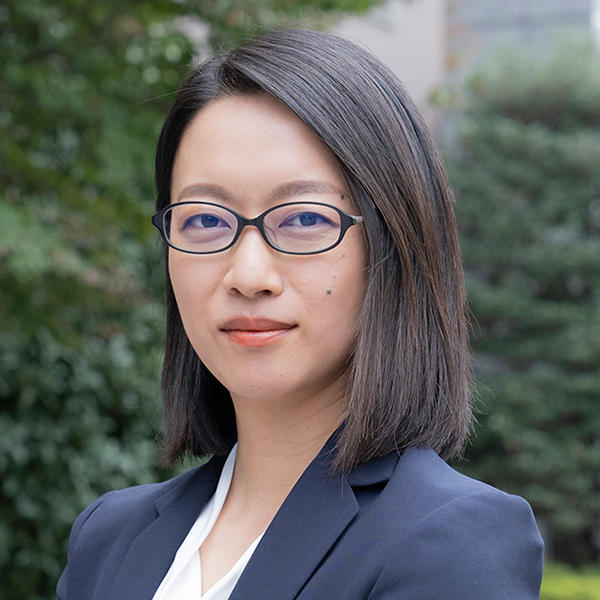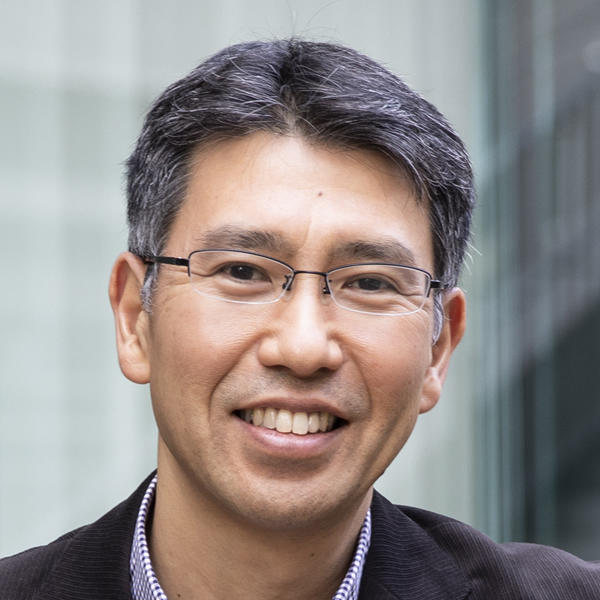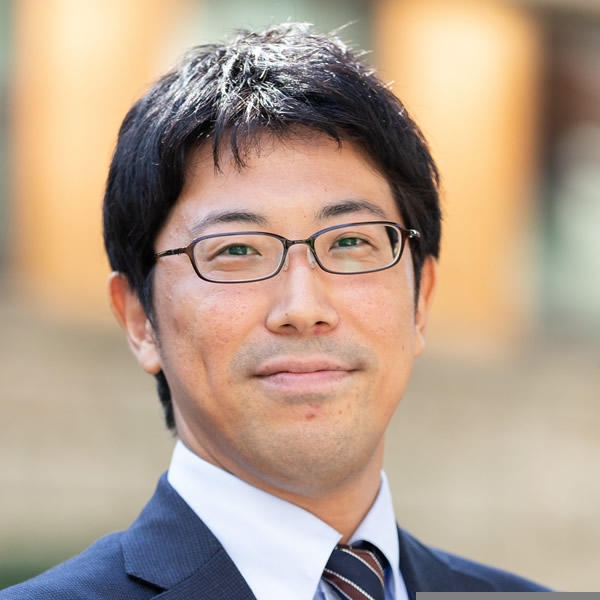読売新聞オンライン タイアップ特集
ニュースを紐解く
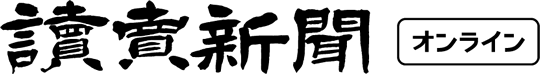
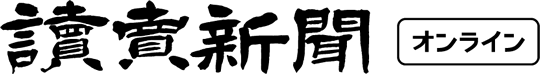
いま、世界で、日本で何が起きているのか。
政治、経済、教養、科学など話題のニュースを上智大学の教授が独自の視点で解説します。

技術がつくる障害が障害でなくなる未来
カギはIoTと人工知能
矢入 郁子 理工学部 情報理工学科 准教授
車いすに乗らない日本人

あるアメリカ人留学生が発した「なぜ日本人は車いすに乗らないの?」という素朴な疑問の言葉は、昔から感じている私の疑問と全く同じでした。
自国の大学院で車いすユーザーの支援を研究テーマにしていた彼女は、1秒に数センチのペースで、それでも必死に歩いている高齢者を町で見かけ、ショックを受けたのだそうです。
彼女は他にも、車いすで満員電車に乗るのが困難なので医療用の杖を使って必死に通勤・通学する若者たち、それを当たり前と受け止めて足早に通り過ぎる乗客たちの姿にも違和感を覚えたようです。
アメリカ人たちは特に、体重が増えてヒザが痛いというだけでも車いすを使い、それを当たり前として普通に働き、車いすと一緒にご近所から地球の裏側まで飛び回っているように私の目には映ります。
逆に、日本では今でも、高齢者や病気の方々が車いす生活になってしまうことへの恐れを口になさいます。
「なんとか死ぬまで自分の足で歩きたい」と。
そして、車いすユーザーの方の多くが、初めてお会いした際に「病気でまったく足が動かないものですから」などとご自身の状況を説明くださいます。
どちらも日本の車いすユーザーの方がこれまでどのような状況に置かれてきたのかを物語っていて、心が痛みます。
少なくとも東京では最近、車いすユーザーの数が増えたように感じることがあるのですが、そこには多くの場合、後ろで車いすを押している方の姿があります。老若男女ともに自立して一人で移動している車いすユーザーの姿は驚くほど少ないのです。
研究のために電動も手動も区別なく車いすを乗り回し、その快適さを知っている私としては、手指が衰えて電動車いすのレバーを握れなくなる日まで、自立して移動したいと思うのです。家族と一緒に出かける時でさえも。
押しやすく漕ぎにくいタイプの手動車いすが保険適応で無償レンタル対象となる事情、家族が付き添いをしなければならない事情があるのはわかるのですが、車いすが、誰かが押してくれていることで初めて周囲がその利用を承認する「大人用のベビーカー」といった位置づけで定着してしまうのではないかと、少々心配になっています。若年人口が減って、車いすを押してくれる手がなくなる日はもうすぐ来てしまうのです。
情報がバリアフリーをつくり出す

車いす利用が増えない根本的原因は、公共交通機関の混雑や、車いすで利用できるタクシーが少ないなど多数ありますが、歩道や施設のバリアフリー化が進んでいないこともその一因です。
バリアフリー化工事の代わりに、バリアの存在とそれを避ける方法を情報として提供するシステムなら、スマホなど個人用情報機器がこれだけ普及している日本ですから、大きなコストやインフラ整備の手間もなく作れます。
ITシステムを使って、車いすユーザーや、視覚に障がいをお持ちの方、ベビーカー利用者に対して、その人の体力や使っている機器の性能ごとに適切な情報を適切な形で伝え、スムースな移動をサポートすることは、技術的にはもはや難しいことではありません。
国産の準天頂衛星の利用が進めば、位置情報もより正確なものとなります。
私がいま取り組んでいるのは、スマートフォンの加速度センサーを使って車いす走行時の振動などを測定・解析し、その結果を道の凹凸や勾配、つまり走りやすさの情報として書き込んだ地図を作るというプロジェクトです。これは、車いすの方だけではなくすべての通行者、そして歩道のバリアを減らしたい道路行政の担当者などにも、有益なものになるはずです。
また、現在の人工知能ブームの発端となったディープラーニング技術も利用して、車いす走行時の振動データから歩道のバリアを高精度で推定する技術についても研究しています。さらに、漕ぎ方のパターンの変化から疲労などの身体的負担を推定する研究も行っています。腕につけるタイプの心拍計のデータがあれば、より詳細に身体的負担を地図に可視化することもできますよ。どこでヒヤッとしたなどの心理的な負担も。
障害が「不自由」ではなくなる日

ITは、ものづくりの形も変えつつあります。
たとえばSNSは、特殊なものをほしい人と、それを作って提供できる人をつなぐ場にもなります。市販品が利用できない、満足できないといった特別なニーズを持つユーザーにとって、これはとても便利な環境といえます。
さらには近年、3Dプリンタが製造技術に革命を起こしました。おかげで、成長に合わせて何度も作り直さなければならない子供用の義手や義足の高性能化と低価格化が、夢から現実のものとなったのです。
現在熱い視線が注がれているのは、IoTと人工知能(AI)ですね。
急速な進化を続ける通信技術と画像認識技術の融合は、例えば視覚に障がいをお持ちの方の生活を一変させるに違いありません。もちろん、画像認識した周辺環境の情報を移動中の方の集中力を邪魔することなくどう直感的に伝えるか、といった難しい課題は沢山ありますが、脳研究などとの融合で乗り越えていくことでしょう。
一方、音声認識技術は十分に実用化されていて、しゃべることで機器の操作も入力もできますから、操作パネルのサイズやボタンの配置の制約を受けずに、サービスを自由にデザインすることができます。ネットワークに接続できる環境さえあれば、ユーザーの傍らにある端末だけで事足りることがますます増えていきそうです。近い未来には例えば、高速で移動するユーザーにさえ、複数のネットワークに途切れることなく接続しながら寄り添い、邪魔することなく実世界のあちこちに配置されたセンサーを通して取り込んだ情報を時々刻々伝え、暇なときには話し相手にもなってくれる、そしてときにはユーザーがちょっとぎごちなく接している相手との間に入ってなめらかに二人を結びつけてくれるような役割ができる、そんなシステムが実現されていくことでしょう。さらには家中の日用品が必要に応じてしゃべる、メガネをかけると音が見える。そうなればきっと、視覚や聴覚に障がいをお持ちの方も、高齢者も子供も、体の不自由な人も元気な人も、みんなが便利に暮らせるのではないでしょうか。
私自身も研究者として、「あんなこともできる」、「こんなこともできたらいいな」と近未来の理想の姿を頭の中に描きながら、みんなが健康的に暮らせる世の中を作っていくことに、微力ながら貢献していきたいと思っています。
2017年9月1日 掲出

-
矢入 郁子 理工学部 情報理工学科 准教授
1994年東京大学工学部産業機械工学科卒業。1996年同大学院工学系研究科産業機械工学専攻修士課程、1999年同機械工学専攻博士課程修了。博士(工学)。同年、郵政省通信総合研究所(現国立研究開発法人情報通信研究機構)に研究官として入所、主任研究員、研究マネージャー等を経て、2008年より上智大学理工学部情報理工学科准教授。2012~2016年ヒューマンインタフェース学会理事、2017年より人工知能学会理事。
工学的観点だけでなく、政治経済・社会福祉・教育・地域研究などの社会科学的な観点も取り入れた学際的な立場から社会のニーズ・シーズを捉え、新しい情報通信サービスやシステムを提案している。
[広告]企画・制作 読売新聞社ビジネス局
上智大学の考える未来
上智大学の視点 ~SDGs編~
ニュースを紐解く