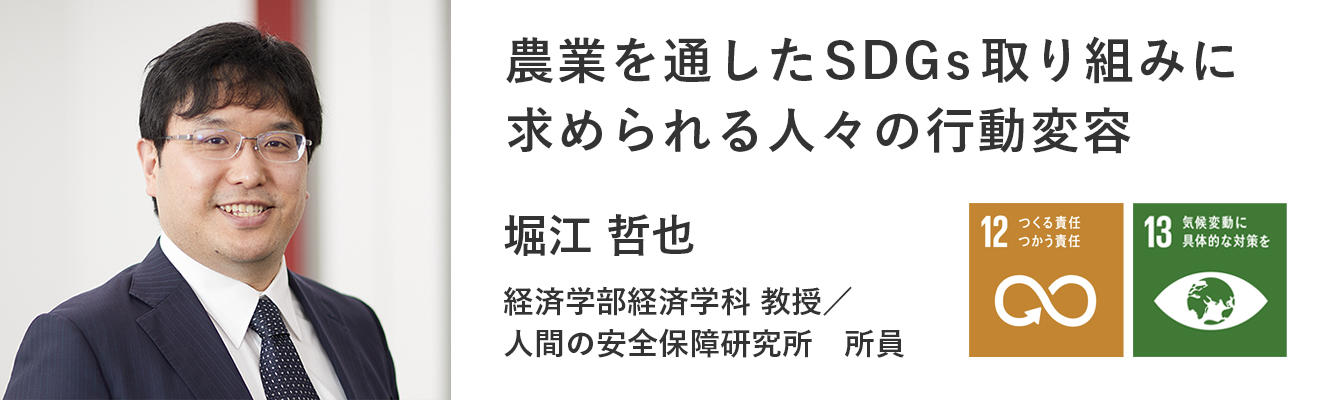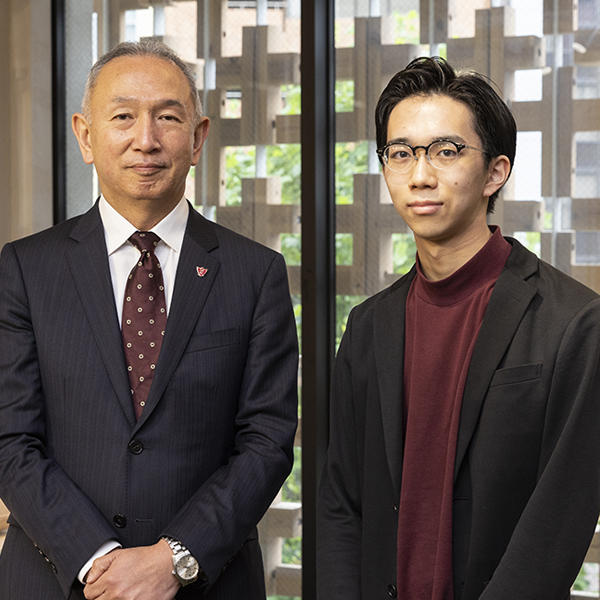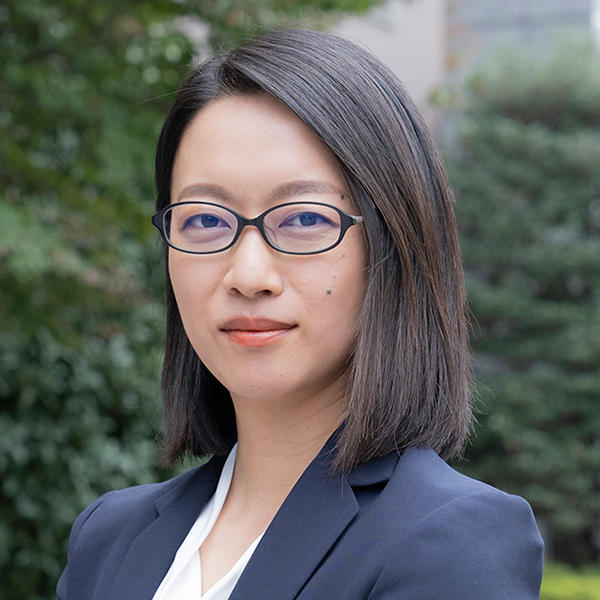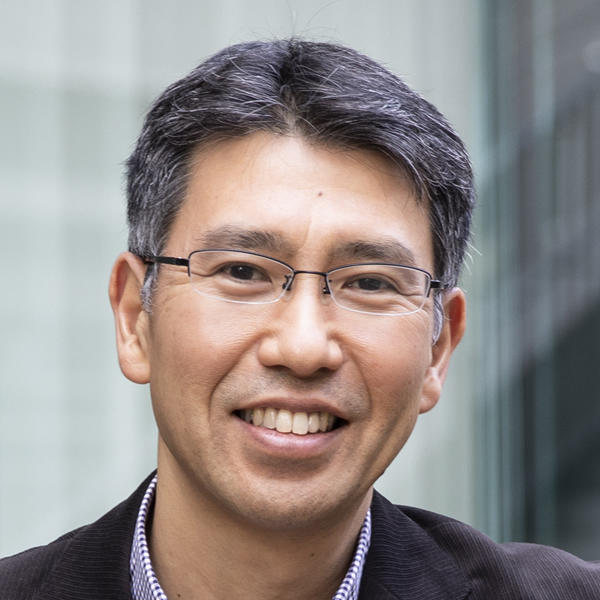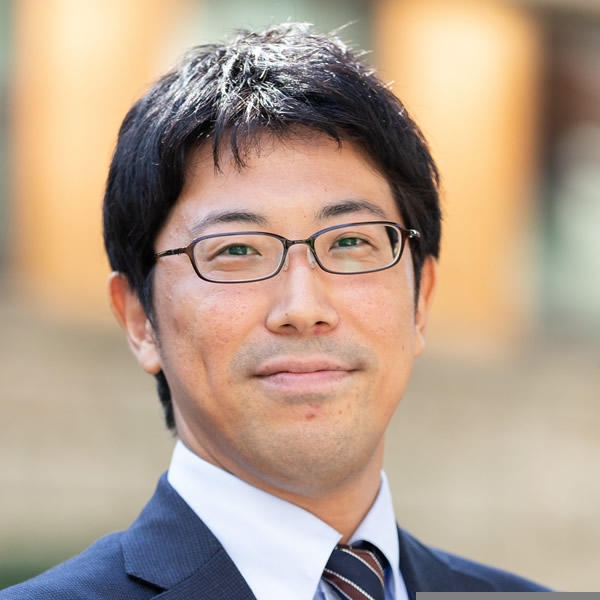読売新聞オンライン タイアップ特集
上智大学の視点
~SDGs編~
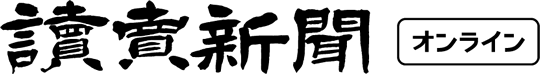
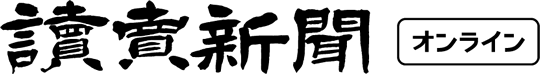
「SDGs」は、2015年9月に国連総会で採択された「持続可能な開発目標」の略称。2030年を達成期限とする、各国が取り組むべき17の目標とその具体的な評価基準169項目が定められている。そこで、上智大学のSDGsにかかわる取り組みを、シリーズで紹介する。

農業を通したSDGs取組に求められる人々の行動変容
農業生産による環境負荷がもたらす人間社会と生態系への影響

ロシアによるウクライナ侵攻という衝撃的な出来事は、グローバル化が進んだ現代の「食料安全保障」について、改めて考えさせられる契機となりました。世界有数の食料輸出国同志の戦争の影響は、日本人の食卓にも、食品価格の高騰という形でこの秋にかけてじわじわと押し寄せるのではないかと予想されています。
戦争のような極端な社会事象が起きなくとも、食品の需要が普段と変化していない状態で供給が減少すると価格高騰は生じます。たとえば、気候変動が進む過程において、異常気象の発生頻度と強度が年々増加しています。この異常気象は、季節外れの高温や低温、日照不足、異常な降雨量や強風などを含んでいます。日本だけではなく世界各国において、毎年のように異常気象による災害が生じていますが、災害の水準にまで達さなくとも、異常気象は農産物の生産量と品質の減少を引き起こします。たとえば、2021年に、日照不足により農産物の価格が全体的に上昇し、レタスのような葉物野菜の価格は最高で例年の4倍ほどになったことは日々の記憶に新しいと思います。
異常気象の頻度と強度を増加させないためには、気候変動の進む速度を抑制することが重要です。通常、温室効果ガスを直接的に排出する電力部門や製造業部門や、エネルギー消費を通して間接的に排出するサービス部門が、温室効果ガス抑制政策の対象部門と考えられます。実は農業部門もこれらの部門と同様に温室効果ガスを排出しています。実際、2021年に発表されたIPCC第6次評価報告書によりますと、世界全体で排出される温室効果ガスの1割を農業部門が占めています。たとえば家畜や稲作は、メタンガスや一酸化二窒素を排出しているのです。また、機械や施設の利用を通して、化石燃料や電力が用いられますので、二酸化炭素も間接的にも直接的にも排出されているのです。
農業部門は温室効果ガス排出以外にも、農薬や化学肥料の多投、および土壌の流出等によって、農地周辺だけではなく、湖沼を含む河川流域および海の生態系にまで悪影響を与えます。こういった点においても、農業部門は他の産業部門と同様に、環境汚染を引き起こしている部門と言えます。こうした環境負荷をできる限り軽減した農法を採用した、環境保全型農業への転換が、いま強く求められています。このことは、SDGsのゴール12に掲げられた「つくる責任、つかう責任」の実現であり、またゴール13、14、15の、気候変動への具体的な対策、陸の生態系の保全、海の生態系の保全などいくつものゴールにかかわる取り組みとなります。
必要なものは技術開発だけではなく行動変容

環境保全型農業は、必ずしも技術的に難しいわけではありません。たとえば稲作における温室効果ガスの発生を抑えるためには、田植え後の夏の時期に水田から水を抜き、土を乾かす(これを中干しと呼びますが)期間を通常よりも一週間程度延長し、14日以上行うと水田からのメタン発生量を約30%削減できます。窒素やリンの水への流出の抑制のためには、農薬や化学肥料の投入量を減少させればよいのです。
このように技術的に簡単なことであっても、実際に農家が慣行型農業から環境保全型農業へと容易に農法を変化させるわけではありません。環境保全型農法は、慣行型農法と比べ、農家に対して必要な労働投入量と収穫量減少のリスクの両方を増加させる可能性があります。それゆえ、新たな1単位の収穫量に必要となる追加的な機会費用(生産費用を含む)が上昇します。このことは、環境保全型農法で育てた農産物(環境保全型農産物と呼びます)について、農家が受け取りたいと考える価格を上昇させます。このことは供給曲線を上方向に移動させ、環境保全型農産物の市場価格を上昇させます。この価格を見た消費者は、環境保全型農産物よりも安価な慣行型農産物(慣行型農法で育てられた農産物)が代替物として存在しますので、環境保全型農産物への需要を抑えます。このことは、環境保全型農産物の需要曲線を下に移動させ、その市場価格も下がります。この価格は慣行型農産物の価格よりは高止まりするかもしれませんが、農家にとっては魅力的な価格とはなりません。そのため、農家にとっては環境保全型農業を行うインセンティブは低下し、それに取組む農家数が減少します。
このような状況にある環境保全型農業を、どのようにしたら普及することができるのでしょうか。農業の技術的な部分を所与としたときに、農家と消費者の両方の行動変容をどのように誘発するのかということが、環境経済学における重要なテーマとなります。
行動変容を起こさせるために必要なこと

農家が環境保全型農業に取り組み、消費者が保全型農産物を購入する、という「行動変容」を引き起こすには、どうしたらいいのでしょうか。一般的な経済政策として、行動を変えた人にその程度に合わせて補助金・減税・クーポンを与える方法と、変えていない程度に合わせて課税をするという、2種類の手法があります。また行動を変容した農家やその農産物に対して、政府が認証を与えるという方法もあります。環境保全型農業に関しては、国レベルでは環境保全型農業直接支払交付金と呼ばれる補助金が存在しています。しかし、その額は農家の行動変容を誘発するには十分に高くはありません。そもそも国の財源は限られているため、補助金の増額を期待することは難しいと考えられます。また、税金の導入も現段階では難しそうです。さらに、認証については、国による有機JAS認証や、地方自治体によるエコファーマー制度や特別栽培農産物認証によるといった自治体による取り組みもありますが、その効果は、今のところ限定的です。
その結果、日本ではたとえば、化学肥料と農薬の使用をゼロにする環境保全型農業である、有機農業に取り組んでいる耕地の全耕地面積に占める割合は、土づくりなど転換作業中のものを含んでも、2017年時点では0.5%に留まっています。これは、有機先進国であるオーストリアの23.4%やEU全体の平均の7%と比較すると低く、世界平均の1.5%よりも低い数字です。
消費者に対しても補助金を与える方法は考えられますが、財源の制約を考えると、やはり現実的な方法ではありません。現在、有機JAS、エコファーマー、特別栽培農産物といった認証を通し、その農産物が環境保全型農産物であるという情報を与え、購買意欲を刺激していますが、やはりその効果は限定的です。実際、2018年には日本人一人あたりの年間有機食品消費額は1408円であり、世界トップのスイスの39000円、アメリカの15000円などと比較しますと1ケタ少なく、世界平均の1638円よりも少ないというのが現状です。
行動変容を誘発する第3の道

そこで注目されるのが、「ナッジ(Nudge)」と呼ばれる手法です。ナッジとは本来は「(行動を促すために)わきから小突く」という意味です。これは、行動変容に関わる意思決定について迷っている人に適切な情報を提供して、「さあ、あっちへ行きましょう。」と社会にとって望ましい意思決定に導く方法です。
たとえば農家は、環境保全型農法を行うことによって収穫量が減少するリスクを懸念しています。しかし、そのことについての正確な情報を必ずしも持っているわけではありません。たとえば、先ほどお話した、稲作における温室効果ガスの発生を抑制する、中干しを通常よりも1週間延長するという方法は、稲を植えた後に軽くひび割れる程度に土地を乾かすこととなります。そのため農家は、土地のひび割れによる稲の根切れの可能性を心配するのです。たとえ「干す」といっても、根切れが起きそうなほど過度に土を乾かす必要はなく、心配であれば水差しを途中でしても良いのです。そうすることによって、収穫量が減ることを避けることができます。温室効果ガス発生の抑制をしたいと思いつつも収穫量の減少リスクを恐れていた農家にこの情報が伝えられると、行動変容が起きる可能性があります。
また、些細なことで行動変容が起きる可能性もあります。たとえば、同じことを伝えるにしても、違う伝え方をするだけで行動変容が起きることがあります。「これから、それをすれば得をするよ。」と伝えるよりも、「今それをしていないことは、損をしているよ。」と伝えることが行動変容の誘発に効果的なことがあるのです。また、現在存在している補助金の水準を変えずに、補助金を受けるために必要な書類手続きを簡素化するだけでも、行動が変わる可能性もあります。
どのようなナッジによってどの程度の農家や消費者が行動を変容させるかということは、まだ明らかではありません。ここまでに述べたナッジによる政策には、補助金や税金と比較して、社会全体にかかる費用が低い可能性もあるという利点もあります。その観点からも、この分野における研究は、今後ますます重要になります。現在私は、これらのことを、環境保全型農業の先進県である滋賀県をフィールドとし、滋賀県と連携して、滋賀大学、尾道市立大学、農林水産省政策研究所の研究者と共に実験に基づいた研究を行っています。
持続可能な社会に向けて、数理的分析、データを用いたシミュレーション分析や統計学的分析によって得られた科学的根拠に基づく制度設計は、日本だけではなく世界全体で導入され始めています。その中でも、人間や組織の行動を解明する行動科学である経済学に依拠したナッジを用いた制度設計とその研究は、今後ますます進んでいくと思われます。
2022年4月1日 掲出

-
堀江 哲也 経済学部経済学科 教授/人間の安全保障研究所 所員
大阪府出身。神戸大学経済学部卒業。同大学院経済学専攻博士前期課程修了。米国ミネソタ大学大学院応用経済学研究科Ph.D. (Agricultural and Applied Economics)取得。上智大学環境と貿易研究センター・特別研究員、上智大学大学院地球環境学研究科・助教、長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科・准教授、上智大学経済学部経済学科・准教授を経て、現在、上智大学経済学部経済学科・教授。他に上智大学人間の安全保障研究所・所員、農林水産省政策研究所・客員研究員、早稲田大学環境経済・経営研究所・招聘研究員を務めている。The Asian Association of Environmental and Resource Economics 理事。
専門分野:環境資源経済学、生態系経済学、農業経済学、食料経済分野における実証的分析。
研究領域:気候変動対策、農業環境政策、生物多様性保全政策
主要な研究:
"Optimal Strategies for the Surveillance and Control of Forest Pathogens: A Case Study with Oak Wilt", Ecological Economics, Vol.86, No.1, pp.78-85, 2013(共著)
"Adoption of Environmentally Friendly Agricultural Practice and Concern about Externality", Presentation at Chinese Academy of Agricultural Science(共同発表・2019)
"Success and Failure of the Voluntary Action Plan: Disaggregated Sector Decomposition Analysis of Energy-related CO2 Emissions in Japan", Energy Policy, (近刊・共著)
[広告]企画・制作 読売新聞社ビジネス局
上智大学の考える未来
上智大学の視点 ~SDGs編~
ニュースを紐解く