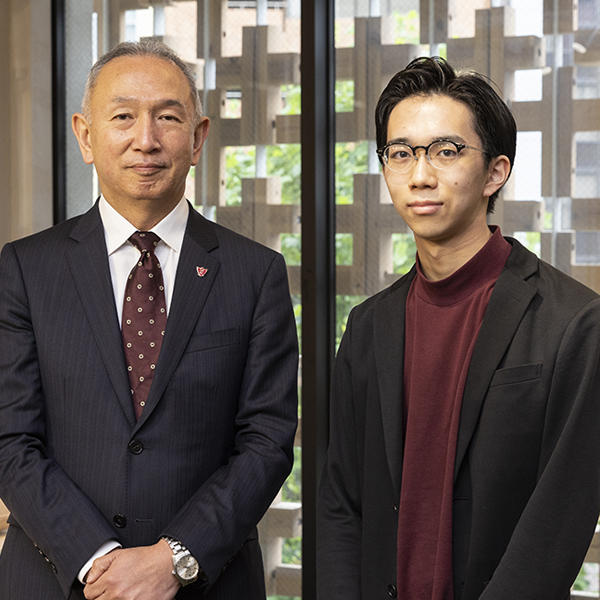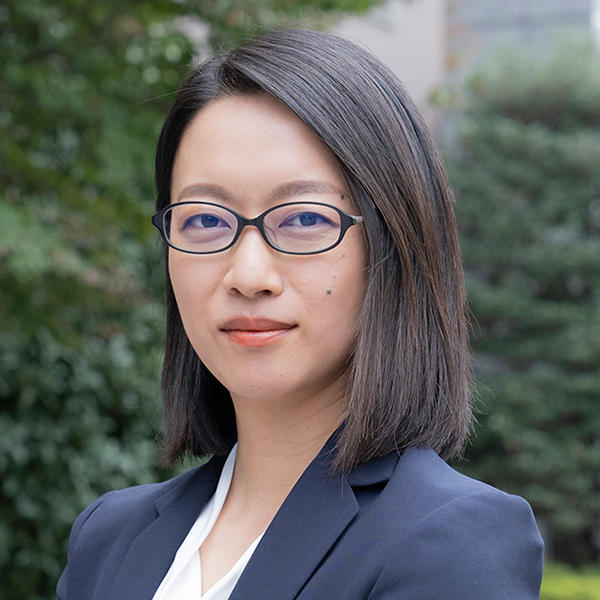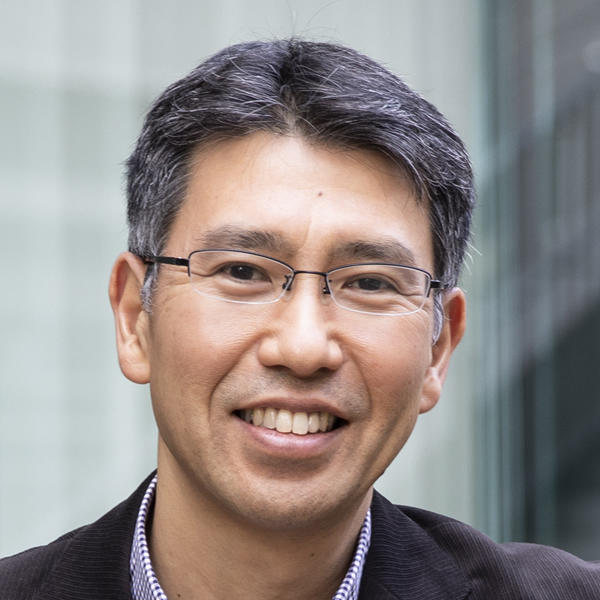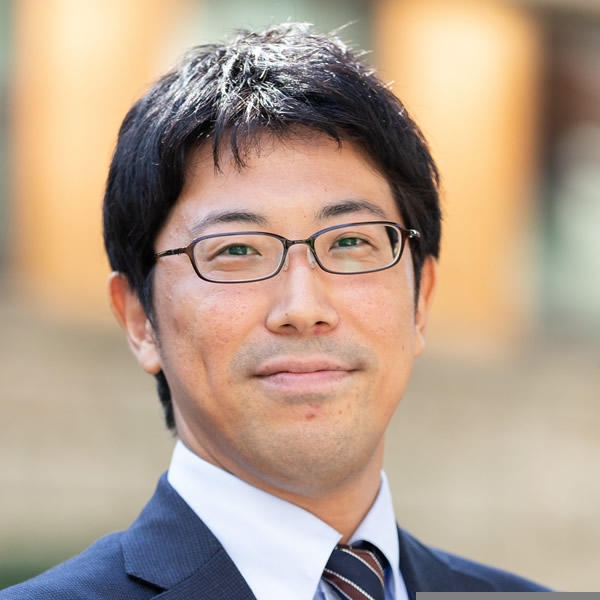読売新聞オンライン タイアップ特集
ニュースを紐解く
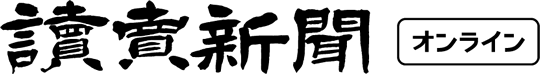
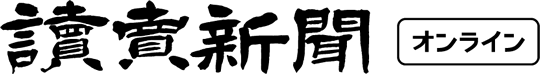
いま、世界で、日本で何が起きているのか。
政治、経済、教養、科学など話題のニュースを上智大学の教授が独自の視点で解説します。

間違いに目くじらを立てるより
変化する日本語そのものに関心を持って
服部 隆 文学部 国文学科 教授
言葉は「なしくずし」に変化する?

先ごろ、文化庁による平成29年度「国語に関する世論調査」の結果が発表されました。そこでは、たとえば「借金をなしくずしにする」の意味として、本来の「少しずつ返していく」を選んだ人はわずか19・5%、「なかったことにする」を選んだ人が65・6%に達するなど、言葉の意味の認識の変化、世代間の新語の浸透の違いといった現代日本語の状況が示されています。
「日本語ブーム」といわれた一時期は、この種の調査結果が発表されるたびに、ニュースだけでなくワイドショーなども大きく取り上げていました。そのころに比べると、今回のメディアの扱いは地味で、視聴者の関心が低くなってきているのではないかと感じつつ、一方ではこれまでの取り上げられ方を改めて振り返る必要があるのではないかとも考えています。
というのも、ブームの当時はテレビ番組を中心に、言葉を「正しいか間違いか」といった二つの枠に押し込めようとする傾向が強く、視聴者の興味は煽られて高まりながらも表面的なところに留まって、言葉の本質への関心や理解から遠ざかってしまうのではないかと危惧していたからです。
言葉遣いのあり方を決める最大の基準は、いうまでもなく、その言葉を使う人がお互いにスムーズに理解し合えるかどうかです。辞書に載っていないとしても、6割を超える人が共通に認識している意味を「誤り」として排除するだけでよいのか、ケースごとによく考える必要があるでしょう。また、文法的な誤用と見えても、たとえば俗にいう「ら抜き言葉」のように、自然な言語変化ととらえられるものもあり、その差は紙一重です。
言葉の望ましい未来を考えるときに大切なのは、言葉がそもそも、「誤用」も含んださまざまな言語変化の中で鍛えられてきた「歴史的存在」であると理解することです。そのためには日本語の歴史を紐解く必要がありますが、実はこれがなかなか楽しい作業でもあります。
話し言葉と書き言葉がからみあう複雑な日本語の歴史

日本語の文法書を最初に出版したのは日本人ではなく、室町時代に来日したポルトガル人宣教師たちでした。それは当然で、日本語を母語として自然に修得する日本人に文法書は無用のもの。しかし彼らはそれを外国語として学ぶ必要があったわけです。ちなみに江戸時代になると国学者たちの文法研究が始まりますが、それも当時の話し言葉ではなく、平安以前の「古典語」を読み解くためでした。
先の宣教師たちが遺した「キリシタン資料」と呼ばれる資料群は、当時の日本語の話し言葉の様子を知る貴重な手がかりになっています。それを見ると、話し言葉は、室町時代にはかなり現代語に近づいていたことがわかります。一方、紙の上に残る書き言葉には、古典語の文法に従った文体がまだ残っており、その状況は江戸時代でも同様でした。その結果、明治時代初頭には、現代語とほとんど変わらない話し言葉と、それとはかけ離れた書き言葉という2種類の日本語が存在することになったのです。
しかし、欧米諸国に対抗するための近代化の要請は、日本語にも及びます。そこで、欧米の言語に倣い、話し言葉と書き言葉を一致させようという「言文一致運動」が起こり、明治時代の後半には、近代の口語文法に従った新しい書き言葉が新たに誕生します。なお、従来の古典文法に従った書き言葉も、時代に応じた簡略化を経て、「明治普通文」という名のもと公文書などに使われ続け、小学校の高学年では「言文一致体(口語体)」とともに教育されました。
「言文一致体(口語体)」を支える口語文法は、多彩な方言が存在する日本の津々浦々で通用する標準語をつくる取組みの中で整えられていったものです。その過程では様々な試行錯誤があったようで、過去の否定表現では、明治37年から使用された第一期の国定読本では「~しなかった」ではなく「~せなんだ」が採用され、それを日本中の子供達が学んでいました。現在と同じ「~しなかった」に統一されたのは、明治43年以降の第二期国定読本からです。
このように、現在の全国共通語の基盤となった標準語は、いわば日本の言語文化を支えるインフラ(社会基盤)として作られたまだ百年ほどの歴史しか持たない言語です。私たちは、先人達の努力に感謝しつつ、さらに日本語に磨きを掛けていかなければなりません。
日本語独特の文字づかいとICT(情報通信機器)の発達

ところで、日本語のもっともわかりやすい、きわめてユニークな特徴は、その文字づかいでしょう。表意文字(漢字)と表音文字(ひらがな・カタカナ)の併用を行うだけではなく、かなり頻繁に使われるアルファベットも含めると4種類の文字を駆使しているのです。ひらがな・カタカナがまだ生まれていなかった『万葉集』の時代にも、すでに漢字は表意文字としてだけでなく表音的(万葉がな)にも使われており、両者の併用という方法は、文献でたどれる日本語の歴史の初期から存在します。
明治時代には、こうした複雑な文字づかいが近代化の弊害になると考え、漢字を廃止し、欧米にならって「ローマ字」のみで表音的に日本語を記述しようと主張した人たちがいました。これは実現しませんでしたが、実はいまになって日本人は、かなり頻繁にローマ字で日本語を書いています。ただそれは、仮名漢字変換のためキーボードでローマ字を入力する作業の間だけであって、実際の文字として打ち出されることはありません。明治時代の漢字廃止論者の人々には、なんとも皮肉な状況と言えるかもしれません。
いずれにせよ、IT機器を使用して文章を書く際に、細かい変換操作を必要とする日本語は、機器の発達の影響を強く受けやすい言語だともいえます。前述の4種の文字に「顔文字」や絵文字などを加えて、SNSやメールなどで展開される独特な言語表現は、「打ち言葉」と呼ばれることもあります。やがて消去されることが前提のデジタルデータとしてしか存在しないこれらの言語表現が、果たして資料として将来の研究のために遺されうるのか。研究者としては大いに気がかりなところです。
そこで改めて思うのは、言葉は日常生活だけでなく、時間や空間を超えたコミュニケーションにとっても大事なものだということです。地域・世代間の意思疎通はもとより、過去からそして未来に向かって時代を隔てた知恵の伝達を行うために、私たちは日本語のどこを守り、どんな変化を受け入れていけばよいのでしょうか。
日本語は、それを母語とする人間にとって「空気」のような存在です。あるのがあたりまえの存在ですが、ひとたび日本語が無くなると、私たちは自由に考え、表現することができなくなります。そして、自分を取り巻く日本の言語文化も壊れていってしまうのです。
日本語の未来は、私たちが日々どのように日本語と付き合っていくかにかかっています。その未来を見極める目を養う第一歩として、日本語の歴史にもっと興味をもって、触れていただけたらと思っています。
2018年11月1日 掲出

-
服部 隆(はっとり たかし)文学部 国文学科 教授
1960年埼玉県生まれ。1983年上智大学文学部国文学科卒業、1985年上智大学大学院文学研究科国文学専攻博士前期課程修了、1989年同博士後期課程満期退学。文学修士。国立国語研究所非常勤研究員、福岡女学院大学講師、助教授を経て、1998年4月上智大学文学部国文学科専任講師として着任。2000年4月同助教授、2007年4月より現職。2017年4月より文学部長。専門は国語学。日本語学会、日本近代語研究会、計量国語学会、日本語文法学会等に所属し、明治時代における国語・国語学の成立史を中心に研究している。
主な著書・論文に、『明治期における日本語文法研究史』(2017年)、「品詞分類の方法と歴史」(『品詞別学校文法講座第一巻 品詞総論』、2013年)、「言文一致論の歴史」(『国語論究第11集 言文一致運動』、2004年)など。
[広告]企画・制作 読売新聞社ビジネス局
上智大学の考える未来
上智大学の視点 ~SDGs編~
ニュースを紐解く