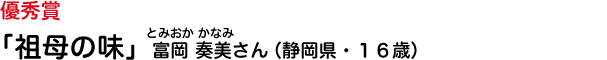
祖母の味を、私は知らない。
忘れてしまった、と言った方が正しいだろうか。病を宣告された十年前のあの日から、祖母は料理から遠ざかってしまったから。
あの日、祖母を病院から連れ帰った母は、話があるのだ、と私に言った。
ばあばは、ゆっくりだけど、色々なことを忘れていってしまう病気であること。だから家族、もちろん私も、いつかは忘れてしまうであろうこと。それでも、ばあばは何も悪くないから、優しく接してあげてほしいこと・・・。
祖母は、認知症だった。
月日が過ぎて、小学校二年生だった私が、高校二年生になった。お昼ご飯、と手作りのお弁当を作ってくれるのは、母である。ウインナーに玉子焼に、今日も素朴で優しいおいしさが、小さな箱に詰まっている。
今日のお弁当はおばあちゃんが作ったものだと友達が教えてくれた。良いじゃん、と私は言ったけれど、おばあちゃんの作る料理は味が薄い、とぼやいていた。
少し寂しい。白米の上の梅干しをかじる。そういえば祖母は何やら色々漬けていた人ではなかったか。らっきょうにしそジュースに・・・。今はどちらも好物なのに、なぜあの頃味わっておかなかったのだろう?
家に帰って母にその話をして、私は母から「祖母の味」の在り処を聞くことができた。
祖母の病気が分かって数年後、正月に祖父母の家で寿司を食べていた時のこと。もちろんその場には私もいて、母はしじみの味噌汁を作っていた。母の作る味噌汁は我が家では定評があって、中でもしじみの味噌汁は、五臓六腑に染みわたる味だ、と父が言うほどだ。その母の味噌汁を、祖父が久しぶりに飲んだ。私には聞こえなかったのだが、その時、祖父の口からはこんな呟きが出たそうだ。
「あぁ・・・ばあばの味だなぁ」
そうか、そうだったんだ、と私は思った。幼い頃から、祖母に料理の下ごしらえから後片付けまでを手伝わされていた母。特にレシピなどは持たず、調味料はいつも目分量で、でも出汁や下味にはこだわって、手を抜かなかった祖母。鍋に醤油をぐるぐると注ぎ、時には味見もしない母の料理がおいしいという事実を、私は魔法のように思っていたけれど、そうじゃない。すべて、祖母から受け継がれた「味の記憶」だったのだ。
忘れたと、もう知ることができないと思っていた祖母の味。だがそれは、いつもそばにある母の味だった。味はその人の人となりを表すと思う。素朴な優しさ。祖母はそれを絵に描いたような人だった。
毎日少しずつ、少しずつではあるが、できることが少なくなっている祖母。しかしその中でも母と私の名前は、まだ覚えている。最後までずっと、覚えていてくれたらいいなと思う。祖母のことが、私たちは大好きだから。
そんな願いを込めて、今日も私は、母の味の向こうに祖母を見る。
![]()



