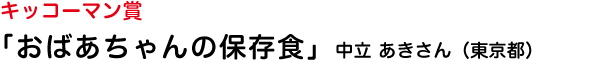
祖母は昼食後すぐに「ごはんの支度をせな」と言った。年に数度しか会う機会はなかったが、祖母の「ごはんの支度」という言葉は何度もきいた。
祖母はいつも台所に立っていた。彼女について思い出すのは、いつも背中だ。その小さい背中を丸めて、台所中を鰹や昆布の出汁の香りでいっぱいにしていた。
しかし彼女らの毎日の食事は老夫婦のささやかな食卓そのもので、質素といってもいいくらいだ。
あとになって知ったのだが、その日食べる数品のためだけに祖母は台所に立ち続けていたわけではなかった。
祖母は、ただひたすらに「ストック」を作り続けていたのだ。
それは漬物や果実酒、佃煮、ジャム、それに味噌やケチャップといった調味料にいたるまで、保存がきくとされているありとあらゆる種類のストックだった。
台所の収納スペースには大小の瓶がぎっしりとならび、祖母の手書きのラベルが貼り付けてある。
祖母は常にその瓶の中身を絶やさないように、またそれらが痛んだりしないように細心の注意をはらって暮らしていた。
一人暮らしをして、数十分で料理を済ましてしまうことに慣れていた私は、なぜ一日のほとんどを料理に費やすのか、祖母に聞いてみた。祖母はそのときもやはり台所にいて、料理の手を休めずに言った。
「もし明日私が死んでしまっても、こうしていろんなものを置いておけばおじいちゃんはずっと私のごはんを食べて暮らせるやろ」
祖母は笑って、冷蔵庫に密閉容器につめた煮物をしまった。
私は夫婦愛への感動と、祖母がいなくなってしまった日を想像して涙が出たが、照れくさくてテレビを見るふりをした。
祖母の作る保存食は、どれも数百円で買ってこれるものばかりだった。便利な現代では、電子レンジであっためさえすれば、どんなに料理が苦手な人でもあたたかい料理を食べることができる。祖母が言う不吉な「明日」がやってきたとしても、然して祖父が食事に困ることはないだろう。
祖母は、それでも、自分の料理を、祖父に食べさせたいのだ。
祖父は寡黙な人で、祖母の料理に感想を言うことなどまずなかったが、外食を好まなかった。仕事をしていたころも、まっすぐ帰ってきた。祖母の料理を愛していたのだろう。
結局祖父は祖母よりも先に亡くなってしまって、祖母は保存食作りをやめた。祖父の葬儀のあとで、祖母は、「おじいちゃんが一人でご飯を食べずにすんでよかった」と言った。このときばかりは、私はテレビに逃げられずに泣いた。
それから数年を経て、私自身が妻になり、母になった。夫と娘とならんで祖父母の墓前に手をあわす。祖母がいなくなった台所には、まだまだたくさんのストックがあった。幼い娘は慣れないスプーンで、祖母が何年もまえに拵えた味噌でつくった味噌汁をおいしそうに飲んだ。祖母の思いが、見えないなにかで紡がれていくのをそっと感じた。
![]()



