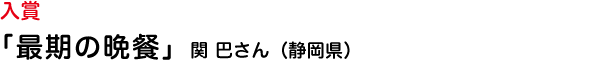
その日、私は風邪で学校を休んでいた。けだるい体をいたわるように布団の中にもぐり込み、一日うつらうつらと過ごした。「ピーポーピー」「トーフィー」と道を行くお豆腐屋さんのラッパの音が聞こえ、「ああ、もう夕方なんだ」と思ったとき、「おー、具合はどうだ、何か食べたいものないか」父が帰ってきた。「今日は、学生諸君が来ているから、お母さんが何かおいしいもの作ってくれるよ。できたら一緒に食べよう」そう言いながら私の額に手を当て「熱はもうないようだな」とほっとした様子で部屋を出て行った。
そのころ大学の教師をしていた父は、故郷を離れて苦学をしている学生たちの面倒をよくみていた。学生たちは、父が不在の時でも、まるで我が家へ帰ったかのようにやってきて、本を読んだり、議論をしたり、私の勉強を見てくれたり、ゆったりとくつろいだ時間を過ごしていた。そんなとき、母は乏しい食材の中から工夫をしては、手料理で暖かくもてなすのだった。戦争が、激しさを増してきた、小学校四年生の頃のことである。
台所の方から何とも言えない香ばしい香りが漂ってきた。私はその香りに誘われるように、起き上がって半纏を羽織り、茶の間へ行くと、数人の学生が父を囲んで談笑していた。そこへ、母が湯気の立つ大きな丼を運んできた。さっきのあの香ばしい香りだ。「これ、静岡のおじいちゃんから届いた八頭芋よ。皆さんどんどん召し上がってくださいね。お砂糖を使わないでお醤油とおかかの出汁だけで煮てみたの。どうかしら?」と確かめるようにみんなの顔色を伺っている。
お醤油の適度なしょっぱさと香ばしい香りに包まれたそれは、ほくほくと口の中で甘くとろけるように広がっていった。まるで大地からの贈り物のように、かすかな土のにおいがした。「おいしいっ」みんながうなった。私はそれまでの空腹を一気に満たすかのように夢中で食べた。他にどんな料理があったかさえ目に入らなかった。おいしかった。
突然、学生の一人が、箸を置き姿勢を正して、「先生お世話になりました。奥さん、いつもおいしい食事をありがとうございました」というと、他の学生も一斉にそれにならい、深々と頭を下げた。「みんな、命を大事にするんだよ」父が言った。母が、横を向いて割烹着の裾でそっと目を押さえている。「うん?何か変だぞ」私はわけがわからないまま、しかしいつもとは違う緊張した雰囲気を感じていた。その日を最期に、学生たちは学業半ばで南の空へ飛び立って行った。そして、二度と日本の土を踏むことはなかった。
文字通り「最期の晩餐」となったあのときの「八頭芋」のとろけるような甘さと香りは、若くして散った学生たちへの思いと共に、私にとって決して忘れることのできないものとなった。
![]()



