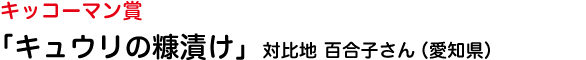
子供の頃のあだ名は「キュウリ夫人」だった。母のキュウリの糠漬けが大好きで、それさえあれば、何もいらないという変わった子供だった。
嫁入り道具には、母から分けてもらった糠床を一番に入れた。以来三十年間、糠床をかき混ぜ、キュウリを漬け続けてきた。
そんな習慣も三十一年目の四月のある日を境に止まってしまった。五十三歳になったばかりの私は、入浴中にくも膜下出血になり、救急車で運ばれたからだ。幸い緊急手術で一命を取り留めた。手術は成功したものの、さまざまな後遺症が危惧された。
検査の一問一答が始まった。名前、年齢、簡単な計算を問うものだ。ついに答えられない日がやってきた。それは好物の質問だった。
キュウリの糠漬けと答えようと思ったのに、キュウリが出てこない。なんだっけ、なんだっけ。思い出そうと焦ると頭が痛んだ。
「今日はここまでにしておきましょう」
看護師は無表情のまま部屋を出ていった。
こうして言葉が出ない日が続くうち、もう元の脳には戻れないかもしれないと、すっかり落ち込んでしまった。
入院二週間目の日曜日、夫が手に保冷袋を持って面会にやってきた。冷えた器のふたを開けたその瞬間、
「キュウリだ!」
と私は叫んだ。それも糠漬けだ。
男子厨房に入らずと豪語している夫がまさか、糠漬けを漬けるわけがない。
「買ったの?」
と夫に尋ねると、
「僕が漬けたのだよ。朝晩糠床をかき混ぜてさ」
と言って笑った。
食べやすいように、カットしてあるひと切れを食べてみた。涙がこみ上げてきてよく味わえない。ふた切れ目を食べると、うすい塩味に微妙な甘みが舌にのる。シャキシャキとしたキュウリの歯ごたえと音が味覚をさらに刺激する。
「パリポリ、パリポリ」三切れ目、四切れ目、ついに一本まるまる食べてしまった。
「あぁ、おいしかった。生き返ったわ」
出されたお茶を飲みながら、ふと慣れない台所で、糠床をかき混ぜている夫の姿が目に浮かんだ。胸がいっぱいになってお茶がむせた。
「それにしても、主婦業三十一年目の私よりおいしく漬けるなんて許せないわ」
夫にそう言うと、
「おぉ、憎まれ口が出るようになったか」
と言いながら、カラになった器をしまった。
目には涙が今にも落ちそうになっていた。
「今までの人生の中で一番おいしい食べ物だったわ。ありがとう」
正座して包帯だらけの頭を下げた。
![]()



