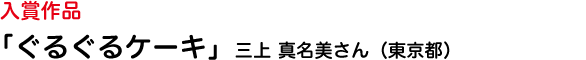
チョコレート生地の、どこにでも売っているような安っぽいロールケーキ。それを母は、薄く切った。動かない左手をケーキの端に添えて。器用な右手で、うすく薄く。
ココア色のスライスを、バターを塗ったボウルに敷き詰めるのは私の役割だ。白い渦巻がきれいに見えるように、一枚ずつ丁寧に。
生クリームをハンドミキサーで固く泡立ててるのは弟。母は片手で、みじん切りにしたバナナを混ぜ込む。左脚をかばう装具に寄りかかって。唇は微笑んで瞳はとても真剣に。
クリームを入れたボウルの蓋になるように、ケーキのスライスをしっかり詰めていく。完成したら、そのまま冷蔵庫で二時間冷やす。ひっくり返すと、ドーム状で不思議な模様のチョコレート・バナナクリームケーキができる。とてつもなく簡単で、とてつもなく美味しい、それが母の「ぐるぐるケーキ」だ。
母はお菓子作りが得意だった。弟と私はいつも、母の作るおやつに先を争って飛びついていた。
わたしの十歳の誕生日には、見事なグランドピアノの形のケーキを作ってくれた。切ってしまうのが惜しいほどのケーキ。
その翌年、母は脳腫瘍で倒れた。ひと月近くも、凄まじい頭痛を我慢し続けていたのだ。病院に運ばれ、緊急手術をしたときには、命が助かるかどうかもわからない状態になっていた。
看病に明け暮れる父が不在の、暗い家の中。弟と私は、膝を抱えて廊下の隅に座り、母の料理で好きなものをいくつも言いあった。もう、食べられないのかなあ。ママのコーヒーゼリー、白玉、ピアノのケーキ……。
ぎりぎりのところで母は生還した。しかし、家に戻ったときには、左手と左脚が動かせない身体になっていた。きれいだった顔は、手術跡を残して歪んでしまっていた。
それでも母は、帰ってきたその日から台所に立った。動かない手を懸命に使って家事をして。私たち姉弟は、奇妙に無口になりながらも、家事をできるだけ手伝った。
でも、きっともう、ピアノのケーキは食べられない。幼心に、変化を受け入れるのには特別な強さが要ることを、はじめて知った。
それをいちばん知っていたのは母だった。
次の年の、弟の誕生日。母は片手でも作れる「ぐるぐるケーキ」を考案して、私たちに食べさせてくれたのだ。
そのときの動悸、跳ね上がりたいような気持ち、頬が落ちるほど爽やかに甘いバナナとクリームの香り、忘れることはできない。
幸せな日々は短く、病を再発した母は亡くなった。そのケーキのレシピを私に残して。
十数年後、弟が結婚した。どこか母に面影の似た、優しく芯の強そうなお嫁さんを連れて来たとき、彼は照れくさそうに笑って、私にこう言った。
「姉ちゃん、うちのケーキの作り方……俺の奥さんに、教えてあげてくれよな」
![]()



