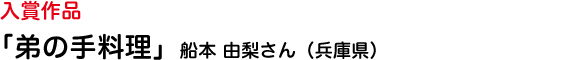
弟は寡黙だった。
寡黙というよりも、両親を避けていたと言えばいいだろうか。
それは、勉強について口うるさく言われていたからかも知れないし、部活を辞めてゲームばかりしていたことで注意を受けたからかも知れないし、成績が悪くて劣等感を感じていたからかも知れない。
確かなのは、年を追うごとに、家族を避けるようになったことだ。
大学生になってからはそれが顕著になり、朝は寝て昼過ぎに行動、深夜に帰宅。
家族と食事をすることはほとんど無かった。
そんな生活を続けて4年、大学卒業後、弟はアルバイトしていた飲食店でそのまま調理スタッフの社員となった。ますます帰りが遅くなり、しまいには近くにアパートを借りて引っ越してしまった。
「ヒロキが何考えとうか分からん」というのが親の口癖で、私が彼の連絡係になることもしばしば。なんせ、親からのメールにも電話にも弟は一切返事しないのだ。
幸い、私のメールには返事が来るので(返事と言っても3回に1回返ってくれば良い方だが)、たまたまお手ごろ価格で入手したドンペリ片手に、弟に連絡をしてみた。
「明日お母さんの誕生日だよ。私はドンペリをプレゼントするけん、あんた料理作ってあげりいよ」
すると、その日は運良く弟からの返事が来た。
「うん」
その後のメールには一切返事が無かったが、ま、いっか。明日来るだけでもよしとしよう。
彼がご飯を作ってくれるなんて、初めてのことだから。
翌日、ヒロキは家に早々と実家に帰ってきた。
「あんた仕事今日無いと?」という母の質問には、頷いて返事をし、何も言わずキッチンに立った。すかさず、私がフォロー。「これからね、ヒロキがご飯作ってくれるんだよ」と親に説明をする。もう、そんな説明まで私にさせんでよ、と言いながらも、内心とっても嬉しい。彼が、親のためにご飯を作るなんて。
10分もしない内に一品目が出てきた。最初はサーモンのお造り。綺麗にカットされていて、美しいオレンジ色。噛むほどにサーモンの脂と刺身醤油が交ざりあって、とても美味しい。あっという間に平らげてしまった。
一緒に食べようという両親の提案には反応せず、彼はその後もせっせと料理を続けた。
パスタ、アサリ蒸しと、ポテトサラダ。親が食べやすいように、全てあっさりとした味付けだ。
一皿食べるごとに母と父は、「おいしい。おいしいよ」と連呼して
時々弟が、「うん」と返事をする。
「ヒロキがこんなもの作れるようになったっちゃねぇ。お母さん知らんかったぁ。ねぇお父さん」
「そうやね。ヒロキ、美味しいぞ」という言葉にも
「うん」で返事。
とってもシンプル。だけど、それは、1年ぶりの、親子の会話。
その日、母は何度も呟いていた。「ヒロキ、おいしいよ」。
何度も、何度も、呟いていた。
![]()



