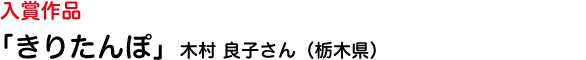
三十年前、夫の両親と同居を始めた頃の私は、圧力鍋でご飯を炊くのが下手だった。ご飯が柔らかすぎて、ふっくらと炊けない。退社して帰宅すると、義父が硬い表情で居間に座っている。「ただいま」と、挨拶しても返事をしてくれない。晩の食事中に急に立ち上がって、
「なんだ、この飯は! 飯の味がしねぇ」
と、ドアをバンと力任せに閉めて、出ていくことが何度かあった。
見かねた義母が、水量は圧力鍋の内鍋に入れた米から一センチの高さになる、と教えてくれた。内鍋には水量線がない。教えられたとおりの水加減で炊いたが、うまくいかない。米をとぐ度に、自分が情けなくて、涙が出た。一旦、米と水を内鍋に入れ終え、蓋をしようとすると、緊張のせいか、入れた水が多すぎるように思えて減らした。減らすと今度は少なすぎたのではないかと、又、水を足した。これを繰り返しては、途方にくれた。
ある日、めずらしく祖母から電話があった。「今日は祭りだ。きりたんぽを作ったがら、飛んで帰ってごい」
義父の怒気を含んだ顔は、もうこりごりだ。帰れるものなら、心底、実家に帰りたかった。
秋田では、きりたんぽはごちそうだ。祭りには無くてはならないものだ。
数日後、思いがけず、母から手作りのきりたんぽが届いた。母の作るきりたんぽ鍋は、箸で持てる硬さのきりたんぽを口に入れたとたん、たんぽに染み込んでいる醤油と具の渾然一体となったスープが口いっぱい広がり、たんぽと共に溶けていく。母の味の記憶をたどりながら、悪戦苦闘した。鶏ガラで出汁をとり、椎茸とネギ、せりを入れ、醤油と酒で味を調えた。その中に切ったたんぽを加え、煮崩れないように注意した。鍋から白い湯気が立ちのぼり、きりたんぽのお焦げの香ばしいかおりが、鼻をくすぐった。
晩酌が終わった義父に、熱々のきりたんぽを出した。義父が丼を持ち上げて言った。
「うまいな!」
なんと義父の目が細くなり、口元がゆるんでいるではないか。
不思議なことに、この日が契機となり、義父は口を利いてくれるようになった。あれほど激怒していたご飯も、「まだ下手だな」と、口調も穏やかになった。
きりたんぽは、義父と私の仲を取りもってくれた。きりたんぽがなかったなら、上手にご飯が炊けるようになるまで、針の筵に座っているような日々を過ごしていただろう。
男性を射止めるには、胃袋を掴めと言われている。男性だけでなく、家族が仲良く暮らすにも、胃袋を掴むのは大事だと、痛感した。
毎年暮れに、実家の兄嫁がきりたんぽセットを送ってくれる。その箱を開けるたびに、今は亡き義父の顔がクローズアップする。飯がまずい、といきり立った顔ではなく、きりたんぽがうまい、と相好を崩した顔が。
![]()



