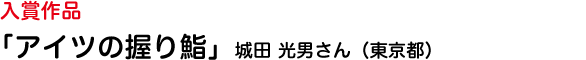
後ろからふいに呼び止められた。振り返ると、アイツだった。イヤな奴に出会ってしまったと運の悪さを呪った。中学時代のクラスメートだったアイツは、当時、いくつもの暴力沙汰で悪名を馳せた粗野な男だった。
「よう、久しぶりやのう」
ちょっと大きめのグレーの背広姿のアイツが笑顔で話しかけてくる。中学を卒業して一年も経っていないのに、随分大人びて見えた。高校には進学せず、地元の鮨店に就職した筈だが、その後のことはよく知らない。
あと30分もすれば年が明けるという浮き立つような夜だったが、懐かしさよりも関わり合いたくないという思いが先に立ち、思わずひるんでしまう。だがアイツは屈託がない。
「ええところで会うたの。今日は大晦日やけん、特別に握らせちゃると親方から言われてのう。店が終わってから、初めて握ったんや」
傍らのベンチに移動しながら、アイツは手にしていた二つの折詰の一つを素早く解き、子どもが手品を演じるように「ジャーン」とおどけてフタを取った。
まだ「回転ずし」もなかった時代、握り鮨は大変なご馳走だったが、折詰の中に並んだそれは、大きさも形も不揃いで、シャリにのった鮨ネタには包丁を入れ直した跡があり、ひと目で素人がこしらえたものだと分かる。
「遠慮せんでええけん、食えや。こっちの折詰は母ちゃんの分やけ持って帰るがのう」
アイツは、初めて握った鮨を母親とつまみながら新年を迎えるつもりだったのだ。
そういえば、ぼんやりと思い出す。何度か学校に呼び出され、どことなく寂しそうにうつむいていたアイツの母ちゃん。
そんな母親と食べる『年越しのご馳走』を食べるわけにはいかないと何度も断るが、アイツは嬉しそうに醤油入れの赤い蓋をはずし、握り一つ一つに醤油を丁寧にかけていく。その大きな手は、ひどく荒れていた。
中学を卒業し鮨店に就職して8か月。まだまだ見習い中で、店の掃除や皿洗いなど雑用ばかりの毎日だが、最近になって酢飯を任されるようになった。年が明けたら握らせてくれると親方は言っている。そんなことを、アイツは問わず語りに語った。
「オレの最初のにぎりを、お前が食うとはのう、思いもせんかったわい」
逆の立場から、私もまったく同じことを思いながら不格好な鮨を一つつまみ、二つつまみしているうちに、除夜の鐘が聞こえてきた。
札幌冬季オリンピックに沸いた1972年が間もなく終わろうとしていた。
正直なところ、アイツの握り鮨が美味しかったのかどうかはよく覚えていない。ただ、やたらと鼻の奥がツンとして、まぶたがじんわり熱くなり、周りの景色がにじんで見えたことだけは確かだ。ワサビ入れ過ぎだろ!
そんなアイツは今、故郷で小さな鮨店を営んでいる。地元ではなかなかの評判の店だ。
![]()



