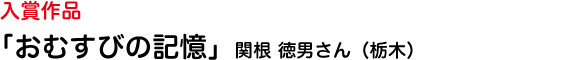
食物独自の香りがなくなると、味覚も失った。抗癌剤治療を開始して五日目のことだ。
入院前に読んだある脳腫瘍患者の手記に「臭覚、味覚がだめになり、すべてクサヤの臭いになった」とあった。私の場合は、食物の風味がなくなり、どれも化学薬品のような刺激臭がした。一気に食欲が失せ何も喉を通らなくなった。
隣のベットに大柄なお爺さんがいた。ほぼ寝たきりだったが、食事のときだけ起きあがり、ベットに正座し、猛烈な勢いで口にかき込んでいた。
「ウチの人はガダルカナル島の生き残りで…」と、付き添いのお婆さんが言っていた。生存本能が食欲の源になっているようだった。
とにかく食べなくてはならない。今後数ヶ月続く治療に耐えられるよう、体力を維持するのだ。治療は医師に任せた。私にできる闘病は「食べる工夫」をすることだと決意した。
病院食は薄味なので、妻が調味料や味の濃いおかずを次々と持ってきてくれたが改善しない。結局、ご飯にみそ汁をかけたり、お茶漬けにして何とか胃に流し込んでいた。
「エミのお小遣いで買ってきたよ」
毎日妻に付いてくる末娘から渡された小さな紙袋には、大福が一つ入っていた。嬉しくて一気に半分かじると、口中に甘さが広がった。お菓子なら食べられそうだ。
一段階クリアしたが、十分な体力維持には主食を食べる必要がある。最大のネックは、ご飯特有の香りが、不快な刺激臭になっていることだ。それを妻に訴えると、周り全体を海苔で覆った「おむすび」を作ってきてくれた。これなら、ご飯の臭気がしない。一口かじると、塩味がした。多めに付けてあるという。うまい。
突然、子供のころ海の家で食べた「おむすび」を思い出した。夏休みになるといつも家族で潮干狩りに出かけていた。潮風の匂い、海苔とご飯の懐かしい香りが、遠い記憶の中から蘇ってきた。
あのころの家族は五人だったが、父、弟、祖母と三人が相次いで亡くなり、母との二人暮らしが十年近く続いた。やがて結婚し、三人の子供を授かると、新しい家族とも「おむすび」を持ってよく出かけた。
私が癌宣告を受けたとき、母は「お前まで、この子らをおいて逝ってしまうのかい」と言った。
小さな三人の子供を置いて逝くわけにはいかない。家族そろって食べた、遠い日の「おむすび」の記憶が、新たな闘病への意欲となった。以後、病院にお願いして、私のご飯は「おむすび」にしてもらった。抗癌剤に適応したのかもしれないが、次々と味覚が回復してきた。
今年の二月。私は還暦を迎えることができた。三人の子供たちは、皆、社会人になっている。次は、孫たちを交え「おむすび」を食べる日を楽しみにしている。
![]()



