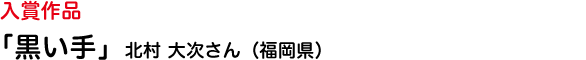
春先になると無性に食べたくなる品がある。ツワブキの炒め煮だ。
毎週末。頬をなでる風に春の気配を感じるようになると、小学生の僕は母に連れられて野山に分け入り、産毛のついたツワの若芽を摘み集めた。下処理のため皮を剥けばアクで手は黒ずみ、石鹸で洗っても数日間は取れない。初めは手伝っていた僕も、細かい手作業と汚れることに嫌気が差し、いつしかその作業は母に任せきりになった。
六センチ前後に切り揃えたツワを油で炒め、だし汁、味醂、酒、醤油でイカと一緒に煮込む。この時期、その品は毎日、食卓に上った。ほろ苦い独特の風味は子どもの舌には大人すぎる味で、正直あまり箸は進まなかった。
忘れもしない中学一年の春、部活の地区大会に持たされた弁当にそれは入っていた。
「その泥色っぽいん、何?」
悪気はなかったのだろう。弁当箱を覗き込んだ友人の軽口に顔が硬直した。なぜか無性に恥ずかしかった。
「弁当にまでツワ入れんなや。つか、その手も汚ねえし」
反抗期のはしりだった。帰宅するやいなや、心無い言葉が口をついて出た。母はハッとしたように両手を後ろに隠すと、「それは悪かったねえ」と翳った表情で微笑んだ。以来、我が家の定番メニューは食卓から遠ざかった。
今なら分かる。七人兄弟の四番目として生まれた母の生家は決して裕福ではなかった。母自身の好物でもあったのだろうが、山野で採れるツワは貴重な自然の恵みだったのだろう。イカ釣り漁師の父と結婚して生活が安定してからも、贅沢とは無縁の人だった。
数年前。野菜直販所で見かけたツワを買い求め、自分で調理したことがあった。皮を剥き、炒めて調味料を合わせる。口に入れてハッとした。舌先に残る何本もの繊維。母の黒ずんだ手は、丁寧に下処理をしてくれていた証だったのだ。思わず電話をかけた。
「あん時はごめん」
照れ臭くて世間話に紛れ込ませてしか伝えられなかったが、やっと言えた。
「何か食べたいもんあるね?」
五月の大型連休直前になると、必ず母が訊いてくる。
「ツワある?」
面はゆさを抑えて素直にそう口に出せる程には僕も成長した。醤油の染みた、ほろ苦い独特の風味をおいしく感じるようにもなった。
「もっとええご馳走でも言やあええんに」
それでも母は声を弾ませる。ここ数年、繰り返されるやり取りを経て帰省すると、駅まで迎えに来てくれる母の指先はやはり黒ずんでいる。もう汚いとは思わない。僕にとって何よりのご馳走を作り出すしらえてくれる美しくて愛おしい両手だ。
![]()



