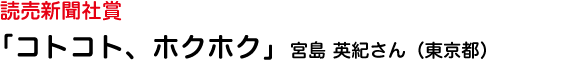
キッチンのかたづけをしていたら、フリーザーの奥から、ストックバッグに入った黒っぽいごつごつしたかたまりがあらわれた。
「はて? これはなにを凍らせたんだっけ」
のんきで忘れっぽい性格ゆえ、いくら首をひねっても、いっこうに思い出せない。そもそも、この黒くてカチカチにかたまった中身は、ほんとうに食べ物なのかという疑念さえわいてくる。
とりあえず、表面の霜をふきとり、しばらく自然解凍してみたところ、思いもかけず懐かしい味が封印されていることが判明した。それは昨年の夏、進行性のがんで亡くなった妻が、生前に作りおきしておいてくれた”つぶ餡”だったのだ。
甘いものを好む私のために、妻はたびたび北海道産の小豆を買いもとめ、良質の三温糖をもちいて、つぶ餡をこしらえてくれた。水色のエプロン姿でキッチンに立った妻が、シャモジを片手にコトコトと両手鍋で小豆を煮ると、湯気とともに、家中にやわらかな甘い香りがただよったものである。
ほどよく煮くずれたつぶ餡は、色つやも良く、これに茹でた大きめの栗をくわえてひと煮立ちさせたところで椀にうつし、ホクホクといただくのが、わが家のささやかな贅沢であった。
結婚して20年、子どもには恵まれなかったが、楽しい会話と笑いがたえない幸せな暮らしだった。とりわけ、食事時には会話がはずんだ。近所にパンダみたいな模様の仔猫が生まれたとか、街においしいタルトの店がオープンしたとか、電車から見た夕焼けがとてもきれいだったとか、日常のささいな出来事のあれこれが、食卓をいろどる無限の話題となった。あわただしい朝食のときでさえ、二人で話に夢中になりすぎて、勤めに遅刻しそうになることがしばしばだった。
それだけに、妻が逝ってしまってからの一人きりの食事は侘しいかぎり。笑いが消えた家のなかの静けさは、怖いくらいだ。
フリーザーに残されていたつぶ餡は、妻が治療の合間に作ったものにちがいない。いったいどんな思いで、妻はキッチンに立ったのだろう。元気になって、またホクホクとつぶ餡を頬張りながら、夫婦で愉快に話をする日が来ることを信じていたのだろうか。
それとも、いつか自分がこの世からいなくなっても、私が好物にありつけるようにと、作りおきしてくれたのだろうか。
私はストックバッグから出したつぶ餡を、いつもの両手鍋にうつすと、コトコトとあたためた。朱色の椀によそうと、あの甘い香りが湯気とからみ合いながら頬をなでる。妻が残していった最後の料理へ、
「ありがとう。いただきます」
と、手を合わせて静かに箸を取った。
口のなかにひろがる妻の味……私は、せっかくの甘さがしょっぱくならぬよう、涙をこらえて箸を動かしつづけた。
![]()



