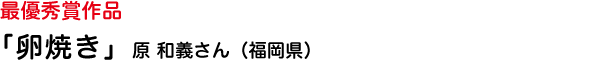
小学校(当時は国民学校)で最後の遠足は楽しみだった。卵焼きが食べられるからである。家では三・四十羽の鶏を飼っていたが、卵は売るためのもので、家で食べられるのは、正月か遠足か病気の時だった。
当時は武器生産に必要な金属回収令が実施されていて、金属の弁当箱は供出されてどの家庭にもほとんどなかった。木製の弁当箱か竹の皮や葉蘭に包んだ弁当で、風呂敷の片隅からぐるぐる巻きにして藁紐で結び、それを背中にかけての遠足だった。
「卵焼きを入れとるけん」という母の言葉も背負って、私は喜び勇んで出かけた。秋晴れのいい天気だったような気がする。学校から目的の海辺までは数キロの道のりだが、わいわいがやがやと歩くのではなく、隊列を組んでの行進状態だった。
昼近く、海岸の堤防に一列に腰を下ろすと、担任のS先生の「昼飯、初め」の号令で、みんな一斉に弁当を広げ始めた。私は「卵焼き」に唾を飲み込みながら、背中の弁当を下ろし、膝の上に置いた。藁紐を解こうとした途端、紐が切れ、葉蘭に包んだ弁当はころころと転がって海の中に落ちていった。涙が滲んだ。岩の上に黄色の卵焼きがへばりついていた。とっさに、私は堤防にぶら下がって、岩の上に降りようとした。
「危ない。止めれ」鋭い先生の声が飛んできた。その途端、大きな波がきて、卵焼きは跡形もなく海の中に消えた。
先生から引っ張り上げられた私は、頭にげんこつを食らった。
「横に座れ。俺の弁当を半分食え」
私がためらっていると、「遠慮せんでもええ。全部食うてもええんぞ」
命令口調だった。木箱の弁当だったが、卵焼きは入っていなかった。三分の一ほど食べたところで、「もう、腹一杯になりました」といって、箸と一緒に先生に返えそうとした。
「のう、和ちゃんや、嘘を言うちゃあいけんぞ。お前の気持ちは嬉しいが、腹一杯は嘘や。もっと食え」
結局、私が半分以上を食べることになった。
それから十年ほどが経った。小倉市(現北九州市小倉北区)の繁華街で、「和ちゃん、和ちゃん」と私の小学校の頃の呼び名が追っかけてきた。振り向くとS先生がにっこりと微笑んでいた。かなり歳を召された様子だったが、昔の面影は残していた。
「おおきなったのう。飯でも食おうか」
近くの市場の大衆食堂に入った。昔話がはずんでいたが、食卓に卵焼きが出された途端、私はぐっと胸がつまった。
先生はそれを察していた。
「何も云うな。何も云うな。ええ時代になったのう。親孝行せえよ」
先生と私は微笑みを交わしながら、卵焼きを口に入れた。
![]()



