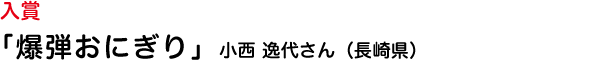
「ありがとねぇ。すまんやったねぇ。」海に出ていた父と母が陸(おか)に上がって来た。『しまった・・・。』私は、つい居眠りをしてしまっていた。
実家は、細々ながら海苔漁師を生業としていた。海苔の収穫期は、真冬と重なる。年明け間もない寒いその晩、時計の針は十二時を回っていた。
海苔は、胞子の状態で牡蛎の貝殻に植えつけられ、栄養豊かな海の中で育つ。それを摘み取り、陸の仕事場に運ぶ。摘み取られた生海苔は、水を加え粉砕し、撹拌される。≪ミス≫と呼ばれる、スノコ状の下敷きの上に、四角い型を置き、一枚ずつにそれを流し込む。続いて、巨大なオーブンの様な窯の中を通し、ゆっくりと時間をかけて乾燥させる。陸の仕事場は、大きな機械がゴーゴー、ジリジリと音を立て、ちょっとした工場の様だった。
私は高校三年生だった。人並みに受験勉強の最中にあった。父と母は、中学しか出ていない。二人とも、暮らしの中で、それを苦にした様子は全くなかったけれど、子供達には、それが当たり前の事であるかの様に進学を促した。
四人の子供達は、それぞれに一人前の働き手でもあった。学校が終わると、これも又、当たり前の様に仕事場へ直行した。長子である私は、更に、母に代わっての家事も担当していた。
その晩は、海上がりの両親に、遅い夕食を用意しておくはずだった。取り急ぎ炊飯器のスイッチを入れてから『少しだけ明日の予習を・・・』と思い、炬燵に足を入れたところで記憶がない。いつの間にか眠っていたのであった。
九州とは云え、真冬の夜の海はとてつもなく冷たい。そこ数日は、まともな睡眠もとらず働き通しの両親に申し訳なくて、自分が情なくて、私は、ただポロポロと泣いた。
父と母の、目立し帽の中の目が同じ様に笑った。「ぬく~かご飯ば炊いとってくれたとやっかい。ご馳走ば食お~やい。」母はそう言うと、粉海苔(こーのりと呼ぶ、海苔を結束した時に両端のギザギザ部分を削り、綺麗に揃えるのだが、その時に出るくず海苔である)を鍋で炒り始めた。焼き海苔の香ばしい香りが一面に広がったと思ったら、しょうゆを大きく三回の円を描き回し入れた。手早く混ぜ合わせると、そのまま炊飯器のご飯に混ぜ込んだ。白黒まだらの粉海苔(こーのり)ご飯だ。ストーブの前では、父が絶妙のタイミングで数枚の海苔を炙っていた。母は粉海苔ご飯を、ソフトボール大ほどのおにぎりにしたあと、炙った平海苔(ひらのり)をパリパリと音をさせて巻いた。爆弾おにぎりが出来上がった。
「うまかね~。」「うまかばい。」父と母は、くぼんだ目を一層くしゃくしゃにしぼませて爆弾を頬張った。私だけが泣いていた。悲しくて、幸せで、おいし過ぎて、いつまでも泣きやむ事が出来なかった。
![]()



