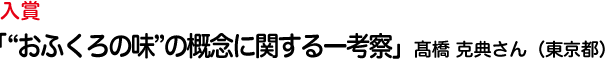
魯山人でもあるまいし――二〇年連れ添った妻にそう言われて、カッとなった。お父さん、いい加減にしたほうがいいよと娘も言う。まるでおれが悪いみたいなことになっている。それでまた腹を立て、とうとうケンカになった。五七歳にもなって、ポテトサラダで夫婦喧嘩はみっともないと思うが、悪いのはおれじゃあない。
夕の食卓にポテトサラダが出てきたから、それをつまみにビールをやり始めたら、
「どうよ、今日の味は」
質問してきたのは妻のほうだ。
「やっぱりポテトサラダだけは、おふくろのほうが上手いな」
訊かれたから素直に答えたまでのことで、他意はなかった。今年で八〇歳になる田舎のおふくろが作ったほうのが、旨いんだからしょうがない。すると、そんなはずはないと妻が言い出した。うちのおふくろに教わったとおりに作っている。だから、少なくとも同じ味のはずで、不味いわけはない――と。
「不味いと言ってない。違うなと言ってるんだ。同じ味じゃない。おれには分かるんだ」
で“魯山人でもあるまいし”となり“お父さん、いい加減にしなさいよ”へと続くわけだ。
世の中のおふくろというおふくろが、みんな料理上手なはずもなく、おふくろの作った料理は、どれも例外なく旨いと、そう言っているわけでもない。ただ、ポテトサラダだけは、どうしたって妻が作るよりおふくろのほうが旨いので、あれはどういうことだろう。
「いい歳して、マザコンなんだよ、お父さん」
「そう、そうなのよ。信州へ帰って、母ちゃんに作ってもらえばいいのよ」
待てよ、以前に同じような光景を見たぞ。
それは祭りの日のことだ。海のない信州安曇野では、鯉を煮付けて喰う慣習がある。
「どうですね、鯉の味付けは……」
母が父にそう訊いた。すると、
「そうさな、旨いには旨いが、やっぱりおふくろの味には及ばんなあ」
父の言葉で、母がみるみる不機嫌になっていくのが分かった。
「おやじ、いい加減にしとけよ」
あのとき、おれは確かにそう言ったっけ。
ばあちゃんの作る鯉の煮付けは、そりゃもう絶品だったけれど、それを言っちゃお終いだぜ、おやじ――という感じだった。
「まあ、おふくろの腹から生まれて、おふくろの作ったものを喰って大きくなったんだから、味慣れしてるってことはあるわな・・・・・・」
いささか反省して取り繕ってはみたが、妻は納得していない様子だった。
「なにが違うのかなあ・・・・・・。じゃが芋にキュウリにハム、お母さんの具材はそれだけだし、熱いうちにお酢も入れてるし、胡椒も効かせてるし――」
夜半、台所でつぶやく妻の声を聞いた。
後日、帰省の折にこの話を聞かせたところ、おふくろはへろへろと笑って、舌を出した。
![]()



