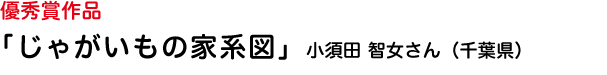
婚約して同居を始めた彼氏を、この五月に初めて実家である青森県に連れて帰った。私から見ると母の母に当たるおばあちゃんは、当年きって九十三歳、一人暮らしはずいぶん長いが、畑や庭の花々と会話を楽しみ、どんな植物でも育て上げる才能を持った人である。
「私の実家に来てみる?」と彼を誘ったきっかけは、おばあちゃんから送られてきた野菜たちだった。ふかしたてのじゃがいもの熱さに大騒ぎしながらぽくぽくふたつに割って、金色にとろけたバターをのせて最後にしょうゆをちらり。実はそれはまだまだ二人暮らしに慣れなくて、ちょっと疲れていた私の手抜き料理だったのだけれど、彼は「これ、旨い!」と顔をほころばせた。その笑顔が嬉しくて、じゃがいもを作って送ってくれたおばあちゃんのことや、私自身も小さな頃から、この何の変哲もないじゃがバターが大好きで、いくつもいくつも続けて食べたことを彼に話した。最後に、もうおばあちゃんも年だから、今年は畑は出来ないかもしれないって言ってるんだ、と付け加えると、すっかり空になったじゃがいもの皿を見ながら彼は、ゴールデンウィークに青森へ行こう、じゃがいもをたくさん植えて帰ってこようぜ、とそう言った。
ほんとうに青森を訪れた私と彼に、おばあちゃんはとてもびっくりしたようだったけれど、彼がおばあちゃんの野菜、特にじゃがいもが好きなこと、だからじゃがいもを植えに来たことを私が話すと、皺だらけの顔を照れくさそうににこにこさせた。初めて扱う鋤や鍬をふるって、おばあちゃんの指導を受けつつ、私と彼は畑を作った。
倉庫にしまわれていた小さな種芋がおばあちゃんの畑に埋められて、やがて芽を出す。おばあちゃんの手に慈しまれてたくさんの実をつけるじゃがいもは、そういえば私たちの家系図にも似ている。おばあちゃんがいて、母が生まれ、私がいて、彼を見つけた。そしてみんながおばあちゃんの家で、おばあちゃんの畑のじゃがいもを、おいしいねと言って食べる。おいしい記憶は、こうして家族に宿って、血となり肉となって私たちの体の中をゆっくりと巡って流れていく。
おばあちゃんの畑に五月の夕陽が落ちていくのを見ていた。いつの間にか私よりもずいぶん背が小さくなってしまったおばあちゃんと並んで、真っ直ぐな畝の出来た畑を見ていた。ありがとう、今年もじゃがいもを送るよ、とおばあちゃんが私と彼に言う。
ううん、じゃがいもが実る頃、また来るよ、おばあちゃん。そうしたら、出来立てのじゃがいもをふかして食べよう。金色のバターを溶かして、しょうゆを落として、熱さに大騒ぎしてみんなで食べよう。
いつか私の子供にも食べさせたい、おばあちゃんの笑顔みたいなじゃがいもの味。おいしい記憶は、きっと小さなお芋のように家族を増やして連なっていくに違いない。
![]()



