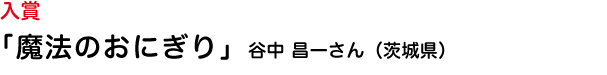
幼稚園の入園を一ヶ月後に控えた三月、娘が事故に遭った。妻と病院に急行し、説明を受けた。頭蓋に骨折があり、少量だが脳から出血している、そして脳全体が腫れている。六時間後にもう一度CTを撮り、出血が止まらないようなら開頭手術を行う、生命の保証は出来ない、医師ははっきりとそう云った。
不安と恐怖の六時間が過ぎた。娘は撮影室に運ばれ、やがて医師が現れた。医師の口からどんな宣告がなされるのか、祈るような気持ちで言葉を待った。
「出血は収まっています。この程度の量なら自然に吸収されるでしょう。このまましばらく様子を見ましょう。」
ひとまず最悪の事態は免れたが、娘は昏々として、意識不明の状態だった。
二日後、「パパ・・パパ・・」と、うわごとで私を呼んだ。
「あきちゃん!パパだよ。パパいるよ。」
私は、娘の手を握り、顔を近づけ、必死に呼びかけた。娘は薄く目を開けていたが、その目は澱んで、目の前の私を捉えてはいなかった。「パパだよ。パパだよ。」何度呼びかけても、声が届いている様子はなかった。そんな日が何日か続いた。このまま意識が戻らなかったら。戻っても後遺症が残ったら。不安に苛まれた。小さな体で、ひとりで闘っている娘が不憫だった。私と妻の全意識は、娘の容態に向かい、食べることすら忘れた。
そして、それは何の前触れもなくやってきた。娘が目を開いたのだ。パチッ、と音がしたように思えた。娘の目は生気と感情を取り戻し、私の姿をしっかりと捉えた。そして、ニッコリと笑ったのだった。『助かった』そう確信した。あきは、ラッキー・ガールだ。胸の中にじわっと喜びが拡がった。
「あきちゃん、なにか食べたいものある。」
妻が聞いている。「おにぎり。」「わかった。」云うなり妻は、病室から駆け出していった。おにぎりなら下の売店に売っている。しかし妻はなかなか戻ってこなかった。私には解った。生還の祝いのおにぎりである、出来合いで済ますわけにはいかないのだ。
戻ってきた妻は、アルミホイルに包んだ小さなおにぎりを四つ取り出した。娘に二つ、私と妻で一つずつ。一週間の空腹を満たすには、あまりに小さな醤油のおにぎりだった。
フフッ、フフッ、と笑いながらしばらくおにぎりを眺めた。ごはんの温もりが指先に伝わってくる。醤油の香りがふわっと漂ったとき、堪らず口に入れた。ちょっとしょっぱくちょっと甘いしょうゆのおにぎりを噛みしめた。おいしかった。
「おいしいね。」笑顔でおにぎりを食べながら目からは涙があふれてきた。
今でも、つらいこと、大変なことがあった時に、妻は云う。「あれ、食べようか。」
不寝不食で心を合わせて娘を看たあの日を思えば、乗り越えられないものなど無いと思わせてくれる、小さな魔法のおにぎりなのだ。
![]()



