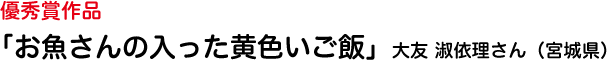
私の中のおいしい記憶、それは母が作ってくれた『卵かけご飯』だ。ご飯の上に生卵を落とし、刻みネギを振りかけた、一見何てことのないものだが、母が用意してくれたそれは、ドロっとした食感を得意としなかった私のために白身は味噌汁用に使い、黄身だけを落とし、さらにしらす干しをのせたもので、幼い私は、「お魚さんの入った黄色いご飯」と言って、歓んで食べていたことを思い出す。
土・日もなく、寝る間も惜しんで、働き詰めの母であったが、幼い私の世話も手を抜くことなく、仕事に出かける前には必ず、食事の支度をしていってくれた。むろん手の込んだものなど準備することはできなかっただろうが、一緒に過ごす時間が少ない分、私を思う気持ちを食事に込めたい、そんな思いで用意していってくれたのだろう。しかし、あの日はよほど時間がなかったのかもしれない。いつも台所に準備してくれているお昼ご飯がこの日は何もなかったのだ。
釜の中にはご飯が炊いてあった。冷蔵庫をのぞくと生卵もある、ある。「お魚さんの入った黄色いご飯を今日は私が作るんだ!」。食事が用意されていなかった寂しさはすぐに忘れ去り、大人になった気分で、「ご飯の支度に挑戦!」という思いだったに違いない。確か五、六歳の頃のことだったと思う。茶碗にご飯をよそり、生卵を割る。しかし、卵を何度割っても、お魚さんも出てこなければ、ドロっとしたものが黄色のお目目と離れない。試しに少しだけ食べてみるが、とても美味しいと言えるものではなかった。「もう一回!もう一回!」、繰り返しご飯をよそり、卵を割ってみても、結果は同じだ。いつも歓んで食べていた母が準備してくれるあの『お魚さんの入った黄色いご飯』とは大違いだった。
夏の日の入りは遅いと言えど、7時を過ぎれば夜の気配を感じさせる。しかし部屋の中は真っ暗だ。「電気もつけないで、どうしたんだろう・・・?」、仕事から帰ってきた母が大急ぎで中に入ってみると、台所にはご飯の上に生卵を落とした茶碗が五つだったか、六つだったか並べられ、電灯の明かりがこぼれる奥の部屋の押入れの中で、浴衣を着た私が泣きはらした顔で寝ていたというのだ。
「あのね、何度やっても、ママの作ってくれるお魚さんの入った黄色いご飯にならないの。だから悲しくなって、浴衣を着て泣いていたの・・・」。母の気配を感じると、私はすぐに飛び起き、そう言って母にしがみついた。幼い私は、卵を割れば、ネギもしらすも、その上醤油味までも付いてくると思い込んでいたというのだから、何とも滑稽だ。
私の口の横についていたご飯粒を取り、むしゃむしゃしながら、「今夜は一緒にお魚さんの入った黄色いご飯を作ろうか」と言って、母は私をぎゅっとしてくれた。卵を割ると、ほくほくのご飯に母の温もりが染みわたる。何てことのない卵かけご飯かもしれないが、私にとってはとっておきの味であった。
![]()



