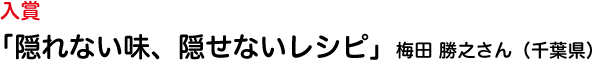
アメリカの競馬関係者だかゴルフ関係者だかが、イギリスへ視察に行った時の会話。
「どうしたら、こんな芝生が育つのですか?」
「え~と、まず水をやります。伸びたら刈ります。そして、また水をやります」
「それだけ?」
「はい。それを三百年繰り返したんです」
母は料理が苦手だった。下手というより知らなかった。戦中戦後に女手ひとつで育ち、小学校を終えると実家の農業を手伝っていた。趣味も化粧ッ気もなく、用事がなければどこにも行かなかった。県外に出たのは、片手さえ余る位であったろう。
父は家畜商だったのだが、思い立って精肉店を開き、そこを母が切り廻していた。
元来苦手なところに店番が加わったものだから、献立に困ると商売物が食卓へ向った。中でもモツ煮込みは多めに作っておけば加熱するだけで済み、重宝だったらしく度々拵えていた。我が家に屯する近所の親父たちも、煮込みの鍋を茶菓子代わりにつつきつつ、「肉はすぐ飽きるけどモツはいいよなぁ」などと、場所柄を弁えない発言を重ねていた。
それが尾ヒレ付きで広まったものか、人寄せの場に煮込みを頼まれるようになった。料理には無関心と見えた母もやはり嬉しかったようで、他所様へ持って行くのだからと、いつにもまして手間暇をかけていた。
そのうち作り方を訊く人が現れ出した。母の答えはいつも決っていた。
「なるべく新しいうちに茹でます。煮立ったらお湯を捨ててまた茹でます。もう一回お湯を捨てて、それから醤油で煮ます」
「それだけ?他に何も入れないの?」
「はい。醤油と水だけ」
それは、悩んだ末に辿り着いたレシピではないと思う。きっと、それしか考えつかなかったのだ。冬にはしもやけでぷっくり膨れる手を、年中冷たい水に浸して下拵えをし、愚直に何度もお湯を捨て、煮込みを作っていた。
外で酒を呑む歳になり、私は母の煮込みが他と違うのを知った。他より旨いとか不味いとかではなく、違う料理だった。また、御歳暮や御中元にやたらと醤油が届く訳も知った。おそらく、モテる男が女性に口紅を贈るのと同様、使ってくれているのがわかり、さらに「少し返してもらえるから」だったのだ。
やがて父が死に、母は眼を患い店に出なくなった。それでも、後継ぎの兄が下拵えするモツを煮ていた。たまに帰省してそれを食べる私に、見えない眼を向けていた。
その母が亡くなって十二年になる。今でも私は呑みに行くと、必ず煮込みを注文する。そして、必ずがっかりし、心の中で言う。
「煮込みなんて簡単なんだ。新しいうちに茹でる。湯を捨てて、また茹でる。もう一度湯を捨てて、醤油で煮る。それだけなんだ」
明日も私は煮込みを注文し、多分がっかりする。その後で、ひそかにほっとするのだ。
![]()



