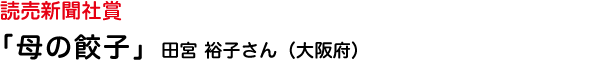
母の作る餃子の味は、独特だ。どこに行っても同じ味の餃子は食べられない。
結婚して、家をでた姉と私が帰省すると、「どこかへおいしいものでも食べにいく?」と父も母も聞いてくる。でも私たちが一番食べたいのは、どんな豪華な外食より、母の作った餃子だったりする。
皮の中身はひき肉とニラとキャベツだけ。味付けは塩胡椒のみ。でもどこの餃子よりもおいしくて、ご飯がすすむ。あんな餃子はほかでは食べたことがない。
「お母さんの餃子って、なんであんなにおいしいのかな。」姉と話し合ったことがある。私が「お母さんって、別にそんなに料理上手ってわけでもないし、あの餃子だって適当に作ってる感じなのにね。」というと、姉が「あの適当な感じがいいんだと思うな。うまくやろうと思えば思うほど、絶対に作れないよ。」といった。なるほど、たしかに、具はみじん切りではなく、適当に切り刻んであるので、ざくざくしている。そしてそれらはスプーンでさっさっと交ぜられてるので完全に混ざってはいない。そして塩胡椒を適当にふりかける。さらに焦げ加減は絶妙。結果、具それぞれの味がしっかりして、それに皮の焦げがジューシーに絡み合って、いい感じ。
娘二人からお手製餃子をリクエストされると、母はちょっと嬉しそうに、「なんか緊張するわあ。うまく作れるかな。」といいながら台所に立つ。「うまくやろうと意気込まなくていいって。あの適当な餃子が食べたいねん。」というと、「なんやの、それ。」といいながら笑う。
出てきたちょっと焦げた餃子はやっぱりとてもおいしい。姉と、「やっぱりこの具が混ざりきってない感じとか、最高だねえ。」と言いながら食べる。山のように出てきた餃子はあっという間になくなっていく。
私たちがまだ学生だったころ、母はフルタイムでパートにでていて忙しかった。パートに出たきっかけは姉の私立中学進学だった。「うちは残してやれる財産はないけど、学歴だけは、本人が頑張るかぎりつけさせてやりたい。学歴はお金に勝る財産になりえる。」母はそういっていた。結局、私も姉も中学高校と私立に進み、最後は大学院まで進学させてもらった。
一日パートに出て、夕方帰ってきて急いで夕食を作る。そんな忙しい日々の中で、母のざつな餃子は作られていたのだ。
なぜかそんな餃子が、本当に本当においしいのだ。
六十を超えて、娘二人を嫁にだした母は今、自分が若いころに行けなかった大学に、通っている。相変わらず忙しい毎日の母である。いつまでも元気で、私たちが帰る時は、餃子を作って迎えてほしいものだ。
![]()



