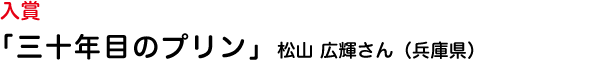
僕が幼ない頃、家の近所に全国チェーンで有名な洋菓子店ができた。
その店は喫茶室も有り、その時代には珍しいフルーツパフェやプリンを食べさせていた。
僕はまだ若かった母に連れられて、その店に行き、プリンアラモードというデザートを初めて食べた。
その美味しさは、この世の物とは思えないほど美味しく驚いた。
僕はそれ以来寝てもさめても、プリンをもう一度食べたくてたまらなかった。
母にそれを訴えると、
「また、今度ね・・・・」と言うだけでなかなか実現しなかった。
その当時としては、高価なものでそう何回も、その店に行けるものでない。
僕が何度も言うので、母は自分がプリンを作ってあげると言いだした。
当時、正確なレシピもなく母は見よう見まねで作り始めた。
出来上ったプリンのような物を食べた時、
「まずい!」 と僕は正直に言ってしまった。
それはカラメルソースもかかってなく、甘い茶椀蒸しのようだった。
母は悲しそうな表情をして、それ以来二度とプリンを作らなかった。
それから三十年が過ぎた。
ある日の事だった。
中学生の娘が
「今日は父の日だから、私が何か作ってあげる」 と言ってくれた。
僕の母も家に来ていて、家族で食事会をする予定にしていた。
食事が終ると娘がプリンを持って来てくれた。
「私が作ったプリンです・・・・どうぞ」
僕のプリン好きを、娘が覚えていてくれた。
ひと口食べると、僕は思わず
「うまい!」と言った。
それ程、娘の作ったプリンが美味しかった。
「本当?それはよかった」
娘は僕の母と顔を見合せると笑った。
「じつはねえ、本当はそれ、おばあちゃんが作ったんよ」
「えっ? どういう事・・・・」
僕は尋ねた。
娘は昔、僕が幼かった時に、母が作ったプリンをまずいと言った出来事を母から聞いていた。
「それをおばあちゃんが、ずっと気にしていて、私にプリンの作り方を教えて欲しいと」
そうだったのか、母はその事をいつまでも気にしていたのか・・・・・。
僕は申し訳ない気持ちでいっぱいになった。
「美味しいよ。このプリン、ほんまに美味しいよ」
僕は心の底から、三十年分の感謝を込めて言った。
母は恥かしそうに笑っていた。
![]()



