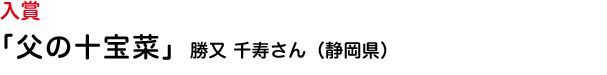
私が小学校へ上がったばかりの頃の話だ。
母は体を壊し遠く離れた東京の病院で入退院を繰り返していた。
育ち盛りの私たち三姉妹の食事は、親戚のおばさんが作ってくれることが多かったが、おばさんが来れない休みの日は父が台所に立った。
父はとにかく色々なものをごっちゃに炒めた。野菜がメインであったが、ちくわや前日に残った一品料理なんかも一緒になり、冷蔵庫の中のありとあらゆるものが大皿に乗った。それが父の定番だった。
この謎の料理の正式名称を知ることになったのは、日曜日、母の病室へ行った時だ。
父は母の病室に私たちを連れて行くと、まずタバコを吸いに病室から一度出る。その隙に私たちは、父に内緒のありったけのニュースをここぞとばかり母に話すのだ。
その日、父が作る料理の話題をふったのは母だった。
「お父さんは何を作ってくれるの?」
「よく作るのはねー、野菜とかウインナーとかいためたやつ。イカとかうずらの卵とかね、上に何かとろーっとしたものがかかってるの。」
「そうそう、この前はお刺身のまぐろが入ってたんだよねー。」
「入れるものも味もいつも違う。でも何かおいしい!」
三人の声がかしましく病室に飛び交う。すると母が含み笑いをしながら小声で言った。
「それは八宝菜っていって色々なお野菜やお魚なんかを入れたお料理なの。お父さん、この前の電話でお母さんに言ってた。『オレの八宝菜はおまえのよりもスゴイぞ。八どころじゃない。十入れてるから十宝菜だ。』って。でね、『あんたたちは大事な宝物だから、いっぱいの宝を食べさせるんだ』って。」
その途端、病室は心地よい静寂に包まれた。私たち姉妹は、それぞれが違う父の八宝菜を思い浮かべ、みんな満ち足りた気分になったのだ。
母の一言で気づいた。父子で囲む食卓がちっとも寂しくなかったのは当然だということに。にぎやかな食材たちと父の愛情が私たちのお腹も心もいっぱいにしてくれていたのだから。
しばらくして病室に戻ってきた父にお調子者の姉が言った。
「お父さん、すごいじゃん!十宝菜なんて発明しちゃってさ~。」
にやにや笑う母と私たち姉妹を前に、父は一瞬キョトンとした顔を見せたが、照れながら、でも、しっかり両手でVサインをした。
母が退院してから父は全く料理をしなくなった。父も母も亡くなった今、あの十宝菜は完全に幻のレシピだ。
今でも私は、嫌なことがあった時、くじけそうな時、父の十宝菜を思い出す。
キラキラ光った食材たちは私の心の中で宝として輝き続け、私を強くする。
![]()



