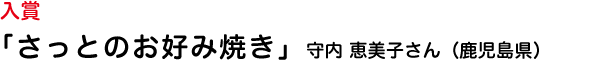
「ピンポーン」チャイムの音に今頃誰だろう、といぶかしく思う。
早出の勤務を終え、子どもが学童保育から戻るまでのほんのわずかな時間、慌しく夕食の支度をしていた時だ。エプロンで手を拭きながらドアを開けると思いがけず子どもの保育所時代の親仲間で今も交流のある彼女― “さっと”が仕事着のまま立っていた。
「どうしたん?」の問いに笑顔で「残り物で悪いんやけど良かったら食べてくれへん?」と包みを差し出しす。受け取るとほっこりと温かい。そしてなんとも言えない-いい匂い。
「ほんま売れ残りで悪いんやけどさあ、ご飯の足しになるかなと思て」
思いがけない出来事に私はその包みを持ったまま言葉が出ない。代わりに勝手にぽろぽろと大粒の涙があふれてくる。お礼さえ言えず玄関で立ったまま泣いていた。
そんな私の肩をぽんぽんと叩き、じゃ、私もご飯作らなあかんから帰るわ、と明るく手を振って帰っていく彼女の後姿にやっとありがとうと叫んだ。
離婚して一年。生活を支えるために早朝からときには遅くまで働く日々。自分で選んだ道なのに時間のゆとりがなくなるとそれは同時に心のゆとりまで奪う。
でも泣き言は言うまい、といつも馬鹿みたいに笑っていることを自分に課していた。彼女とも逢えばお気楽な世間話しかしてこなかった。なのに彼女が届けてくれた自分の店のお好み焼きと焼きそばのぬくもりは私の胸を突いた。「売れ残り」と言ってわざわざ遠回りして届けてくれたその気持ち。
それまでも「頑張ってね」という励ましは周囲からたくさんかけてもらっていた。それ自体はとてもありがたいことなのだが自分が苦しいときは素直に受け取れず「これ以上何をどう頑張れっちゅうねん」とひがんでしまう時もある。
だがお好み焼きの温もりは彼女の無言の優しさを私に伝えてくれた。
その晩「さっとのお好み焼きはやっぱりおいしいなあ」と言いながら分け合って食べた食卓には久しぶりにゆったりとした笑顔があふれた。
あれから十年以上時がたち子どもたちは成長した。相変わらず生活のために働きづめの日々ではあるが今が一番幸せだと思う。
今でも私はときどきあの包みを受け取ったときの温もりを思う。その記憶はいつでも私の心もほんわかとあたたかくする。
そしてそのたびに、自分もさりげない優しさで誰かを支えられるような存在でありたい。
そう思うのだ。
![]()



