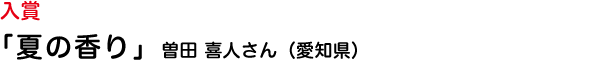
梅の実がたわわに実り、辺りにさわやかな香りが漂う頃、父親はにわかに落ち着きをなくした。陽が昇る前に起きだしては、川を見に行った。
私の家庭は明治時代から続く酒屋を営んでおり、父親はトラックに日本酒、ビール、味噌、醤油、油など、お得意さんから注文を受けた商品を積み込み、山間部を回った。
取り立てて趣味のないまじめ人間の父親が唯一楽しみにしていたのが、川を買うことだった。「川を買う」と聞いた都会の人たちは、どういうことか想像がつかないかもしれないが、この地方では当たり前のように通じる言葉である。つまり、川の一区画を買い、その区画に入ってきた鮎を自由に獲ることができる権利なのである。父親が早朝起きだして、川を見に行っていたのは、どの辺りの川を買おうと品定めをしていたからだった。
水の流れ、広さ、深さ、そして、最も重要になるのが、魚影の濃さである。鮎はなわばりを持つため、太公望たちが、囮を用いて友釣りをするのが一般的であるが、川を買う者の楽しみは、友釣りとは異なる別の漁法が存在する。それは、「ひっかけ」とよばれるものだ。
父親は、毎年この引っかけがしたいために、川を買っていた。いったん川を買えば、ひと夏中楽しめた。谷川の水が集まる清流は、どこまでも透明で、若鮎の腹部に陽が反射してキラキラと光りを放った。
酒屋の定休日がやってくると、父親は「おい、行くぞ」と一言いい、私を連れ出した。引っかけ専用の短い竿と網、そして、飯盒と食材を袋に入れ、足早に出かけた。
そこには、いつもと変わらぬ清流が私たちを迎えてくれた。初夏の谷川の水は、低温で肉がついていない私の身体にしみた。ちゅうちょしている私を無視するかのように父親は、清流の中に溶け込んだ。私も決心し続くと、水メガネを通して、別世界が広がった。鮎が身をくねらせ、水の中で群れをなして跳ねていた。私は、針を構え何度も竿を引いた。しかし、なかなか鮎は引っかかってくれない。そうこうしているうちに父親は、十匹程も引っかけた。「鮎の泳ぐコースを予測して、鼻っ柱に来た時、一瞬で竿を引くんだ。」と言い残し、また鮎を追いかけた。私が、タイミングを見計らって竿を素早く引くと鮎が針にぶら下がった。私は、水の冷たさを忘れていた。
獲った鮎は内臓を出し、米に醤油を加え飯盒で炊いた。また、火に網をのせ、ひれに塩をまぶした鮎を塩焼きにした。それ以外にも父親自慢の料理があった。それは、内臓を出した鮎の腹に赤だし味噌を突っ込み、塩焼きと同様に薪で焼いた。鮎飯は、若草の香りを漂わせ、夏の訪れを感じさせた。塩焼きや味噌焼きは、香ばしさと身の豊かさで自然と笑みがこぼれた。父親は鮎を口にし、「最高だろ」といつも得意げに話した。
今年も幼少の思い出と共に夏がやってくる。
![]()



