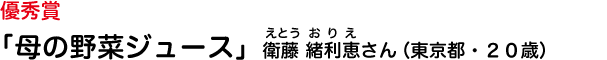
ある時は苔のような緑色。またある時は、赤みを帯びた薄い橙色をしていた。さらさらとゆるい液状の時もあれば、妙に固くて、コップをひっくり返しても落ちてこない時もあり、そんな時は仕方なくスプーンで掬って口に運んでいた。
それが母お手製の野菜ジュースだ。
味はといえばこれがまた不味く、家庭用のミキサーでかき混ぜられただけの舌触りはざらざらしていて、時には粉砕しそこねたブロッコリーの茎などが喉に引っかかることもある。母曰く、それらの大物は「当たり」らしかった。
毎日欠かさず朝食と一緒に出されるその野菜ジュースが、私はどうしても苦手だった。時間が経つと、コップの中で野菜カスと水分が分離する見た目からして、爽やかな朝の天敵としか思えない。
「やっぱり今日もあるの?」
文句を言うと、母は「もちろん」とわざと意地悪そうに笑ってみせた。
トマトにレタスにホウレンソウに茹でたブロッコリー、きな粉、いりこ、そして牛乳。多少の入れ替わりはあるものの、これが基本の材料だ。
これらを無理矢理ジュース状にしただけなのだから、味が悪いのも当然だ。
ジュースを一気飲みしたら洗面所にダッシュして歯磨き。僅かな間でも、その最悪な後味を感じたくなくて、息まで止めていた。
そんな私なので、高校を卒業し、一人暮らしが決まった時は、何よりも最初に野菜ジュースから解放されることを喜んだ。
しかし家を出て少しして、私は食卓から野菜ジュースがなくなったことを聞いた。その代わりに、ごく普通のサラダが添えられるようになったのだという。何も私がいなくなった途端にやめることないのに。もちろん、私はそう思った。
「なんでやめたの?」
「せっかく作ってるのに、みんな文句しか言わないし。やる気なくなっちゃった」
文句なら私だって散々言ったのに、そんな今さらなことを母は言った。
大学一年の夏休みに帰った我が家では話に聞いた通り、もう野菜ジュースは出てこなかった。野菜ジュースのない朝にすっかり慣れた弟は、眠そうな顔をして納豆を混ぜている。
「本当にあれ出てこなくなったんだね」
キッチンを見れば、すっかりお役御免になったミキサーに埃防止の布きれが被せられていた。
「だって、あれ、食うの遅くて朝バタバタしてる姉ちゃんの為に作ってたんでしょ?」弟がさらりと口にした言葉に、私は思わず何も言えなくなった。
比較的口が小さい私は、確かに他の家族に比べて食べる速度が遅かった。そんな私が少しでも焦らずに食事が出来るように。野菜ジュースは母の私に対する優しさだったのだ。
「やっぱり今日もあるの?」
「もちろん」
いつかの母との会話を思い出す。
あの日の食卓にあったのは、温かい朝食と、相変わらず美味しくない野菜ジュース。それと、母の愛情だったのだと、今なら分かる。
現金なことだけれど、思い出とは美しく思えるもので、今になってみればあのジュースも意外と美味しかったような、そんな気もしてくる。
![]()



