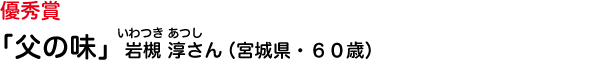
父の十七回忌を終え、八十七歳になる母と二人で、ある寿司屋を訪れた。「こんなどごに入ったごとない」と母は怪訝な顔をして私を見上げた。母の背中を押して暖簾をくぐると、若い職人の威勢のいい声が響き渡った。戸惑いを隠せない母をカウンター席に座らせ、親方に「先日は大変ご馳走になりました。今日は約束通り母を連れて来ました」と声をかけた。小柄な親方が、ちらっとこちらを見て破顔した。私が一礼すると全てを悟ったかのように眼光を鋭くして頷いた。母は父が亡くなってからずっと一人暮らしだった。昨年、不調を訴えた母を、近くに住んでいる姉が病院に連れて行った。医師は「まだ認知症ではありませんが、ちょっと鬱が進行しているかもしれませんね」と診立てた。姉が毎日、母の家を訪れて家事の世話をしているが、母の一人暮らしは今も続いている。
親方が皿に盛られた干瓢巻と稲荷鮨を持って来た。母の前に置き「先代の時に随分と贔屓にしていただいたようです。うちの自慢の味です。食べてみてください」と、深々と頭を下げた。母は親方のあまりに謙虚な姿に驚き、目を白黒させて「いやいや、そんなご丁寧に」と、やおら席から離れ、親方以上に頭を下げた。私は母の手を取り元の席に着かせ「まあ、その干瓢巻を食べてみて」と声をかけた。母は慈しむように小振りに切られた巻物を一つ手に取り、口にした。
「うめんなぁ。死んだ爺ちゃんの味だなぁ」
「そうか・・・・・・母さん、この店がわかる」
「そりゃあ、きまってる。あさひ鮨さんだべ」
母がきっぱりと即答した。親方がすかさず母の元にやってきて「ありがとうございます」と、嬉しそうにまた頭を下げた。
私は高校三年の時、父と大喧嘩したことがある。「俺はあさひ鮨の大将のような寿司職人になりたい。だから親爺、紹介してくれ」と父に言うと、父は顔を真っ赤にして「馬鹿言え、お前がなれるわけがねえ。朝三時に起きて飯炊き三年だぞ」と怒った。父に連れられて、一度だけ寿司屋に行ったことがあった。以来、父が持ち帰る寿司の折り詰めが楽しみになった。中でも干瓢巻は、我が家では大人気だった。翌日に食べても美味しかったからだ。結局、私は父の言葉に折れて大学に進学した。
「私は先代の味を知らないんです。外で十年以上も修行させられて、帰って来た時には、親爺はもう店に出ていなくてね。だから先代の味を知っているお客さんを大事にしています。米や海苔、砂糖、醤油、酢は当時とは全く違います。先代の味は越えられません」
数日前に、もしや、と思い訪れた私に、親方はそう胸の内を語ってくれた。
少し元気になった母が、帰り際に「いがったごど、今日は爺ちゃんの味に会えました。おしょうしなっし」と礼を言うと、親方は
「いづでもきてくだいん」と目を細くした。
母の目尻から一筋の涙が流れていた。
![]()



