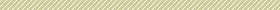分断ではなく共に喜び合う関係から
福島に豊かな暮らしを広げていきたい
 小松 理虔さん
小松 理虔さん
テレビ局の報道記者から看板が通じない上海へ
田中 このたびは2018年大佛次郎論壇賞の受賞おめでとうございます。受賞作となった『新復興論』を拝読し、今の福島の現場や生活に根ざした言葉が紡がれた「名言集」であると感銘を受けました。
小松 ありがとうございます。素人として福島の被災地に入り、気づいたら復興の内側にいたという状況です。そこで、廃炉まで相当な時間、下手をしたら100年以上かかることを考えた時、孫やひ孫の代まで「福島の記憶を伝えなくてはいけない」という切迫した思いで執筆したのが本書でした。
田中 生まれはいわき市小名浜ということですが、法政大学に進学したのはどういう経緯からですか。
小松 歴史が好きで社会の先生になりたいと思っていました。できれば名の知れた大学に行って親を喜ばせたいと考え、東京六大学の一つである法政大学文学部の史学科に入学しました。
田中 歴史がお好きなんですね。関心分野はどのあたりだったのですか。
小松 昔から三国志が大好きでした。そのため、三国志の舞台に留学しようと四川省の成都大学で半年間学びました。そこで目にした人たちは、これから豊かになるんだという自信がみなぎり、決して裕福ではないのにどうしてこんなに楽しそうなんだろうと衝撃を受けたことを覚えています。
田中 意外な関心分野ですね。思ってもみませんでした。しかしかつての中国がどのように見えたか、よくわかります。私も1986年に研究のために北京大学で暮らした時に同じように感じました。ところで、卒業後はどのようなキャリアを歩まれたのですか。
小松 福島のテレビ局から内定をもらい、報道の世界に入りました。しかし、地元ではテレビ局員というだけでちやほやされることも多く、このままでは勘違いして駄目になるという危機感を抱くなか、会社の看板が通じない世界で挑戦したいと思い始めました。自分はもっと違った世界で羽ばたけるという妄想を抱き、約3年間働いたテレビ局を退社して上海に渡りました。
田中 それはまた大きな選択をしましたね。驚くようなことばかり。それで、上海ではどのような仕事をされたのですか。
小松 手始めに日本語学校で日本語教師をしているうちに、上海のローカルな面白さを知っていきました。その面白さを外に伝えようと、現地の日本語情報誌に自分を売り込んだところ、そこで働くことになりました。好きなテーマの企画に関わらせてもらったり、スポンサーを自分で見つけたりしていたら、2年目から副編集長に。他にも上海進出をめざす経営者や芸能人の現地ガイドを務めたこともありました。当時の上海は、本当にやればやるほど認められる世界で、万博やオリンピックを控え、人も街もどんどん成長していく熱気がありました。
田中 実は私も上海で衝撃的な出会いがありました。北京大学に行く前に上海外国語大学に滞在することになっていたのですが手違いで迎えが来ず、上海港で途方にくれていた時、人民服を着た新聞記者に助けてもらいました。庶民が暮らすれんが造りの古い町並みを案内してもらい、初日から中国に魅了されました。食事をご馳走になった後、黄昏時に弾いてくれたバイオリンの音色は忘れられません。その方は、文化大革命のために大学に進学できなかったけれど立派に活躍している人でした。
小松 素敵な思い出ですね。本当に中国の人は思い詰めたりせずにはつらつとしていると思います。自分と誰かを比べないし、好き嫌いもはっきりしている。翻って僕ら日本人は小さい頃から「個性が大切」と言われながら、結局周りの視線を気にして自分と誰かを比べている。中国ではそんな価値観が揺らぎました。

専門性と社会のつなぎ役として活躍できるのが法政らしさ
田中 日本ではできない貴重な経験をしましたね。しかし戻っていらした。上海から福島に戻ったのはなぜですか。
小松 同じことを地元でもやってみたいと思いました。というのも、上海滞在時、路地裏の洗濯竿がかけられた通りや小さな食堂などの写真をブログにアップしていたところ、ヨーロッパやアフリカに住む方々から多くのアクセスがあったんです。ローカルなものは、広くはないけれど国籍を問わず深く刺さると気づかされました。「当たり前のように感じる地元の風景も、外者の目線で楽しんだら世界に刺さるかもしれない」と思ったら急に帰りたくなったんです。これは外に出たからこそ気づけたことです。
田中 きわめて法政らしい柔軟性や国際性を身につけて帰っていらしたんですね。
小松 僕も記者クラブで「君は法政らしい。見ただけでわかる」と言われたことがあります。自覚はありませんでしたが、フットワークの軽さやチャンスへの嗅覚、明るく思い詰めない感じが法政らしさだと社会に出て感じました。専門性だけに特化せず、専門性と社会のつなぎ役で活躍できるのが僕は法政らしさだと思います。
田中 現実にそういう卒業生は多いんです。これからの時代にはもっと必要とされると思います。それで、福島に戻っていらしてから、まず何をされたんですか。
小松 「仕事」と「やりたいこと」を分けようと思いました。そこで製造業や工場が多い地元で材木屋や蒲鉾工場で朝8時から夕方5時まで働きました。その後5時からもう一つ活動をしようとポジティブにとらえ、アフターファイブを徹底して活用するスタイルを「晴耕雨読2.0」と名付けました。
田中 ちょうどそのころ震災が起こりましたね。震災当時は何をされていたのですか。
小松 中国から輸入材を扱っていた材木屋さんで働いていました。その一方で、「UDOK.」というアフターファイブの自分たちの活動スペースを持とうと、3月12日に契約書にサインする予定でした。夢の城が手に入るまさに前日、あの震災があったのです。
田中 運命的でしたね。
小松 まさか自分の暮らす場所で災害が起こるとは思わなかった。人生も大きく変わりました。今まで2回しか会っていなかった彼女が暮らす新潟に避難したのですが、出迎えてくれた彼女の両親に「結婚を前提でおつきあいしています」と言う流れになり、そのまま結婚(笑)。大切なものを得た一方で、東京の親戚宅に避難していた祖母の認知症が進行してしまいました。
田中 高齢者にとって避難は非常に大変な体験だったでしょうね。
小松 祖母に避難を勧めた僕も自責の念にかられました。高齢者の健康を守ることの大変さと大切さを痛感し、今は高齢者福祉に関する取り組みも行っています。失ったことで得られた問題意識は生かしていきたいと思っています。現在、フリーランスとしていろいろなことに取り組んでおり、生産者の情報発信やプロモーションの方法にも関わっています。現場を見ているうちに絶対に読者に届けたいというネタにも出会えるので、雑誌やインターネットでのライター業にも生かしています。
知ろうとすることが自分の生活を豊かにさせる

田中 そういった様々な活動をされるなかで『新復興論』を書かれたわけですね。私も今ちょうど石牟礼道子論を書いています。水俣には石牟礼道子が現れた。彼女が『苦海浄土』を書いたことで水俣病がより広く知られるようになり、裁判闘争が続けられ、ユージン・スミスが写真を撮り、ありとあらゆることが動き始め、今でも続いています。福島にも小松さんが現れたこと自体が表現の一つだと思います。メディアがその役割を放棄してしまっている今、小松さんはコミュニケーターでもコーディネーターでもあり、地元と様々な背景の人を結びつける媒介者でもありますよね。
小松 僕もまさか本を書くとは考えてもいませんでした。自分自身、震災を通じて「発見されたように」感じることがあります。
田中 本の中で「復興というのは元に戻すことではない」とありました。
小松 「はじまりの美術館」の岡部兼芳館長が、原発事故を運命をともにすべき「障害」だとおっしゃった。つまり前の身体には戻れないから一生つきあっていくしかない。元に戻るのではなく、欠けてしまったことを認めて新しい自分を作るという意味も伝えたくて、題名を『新復興論』としました。
田中 「復興は失敗だった」とも書かれました。一番の原因は何でしょうか。
小松 今までの復興が人の心や暮らしの復興につながらなかった点です。慣れ親しんだ風景や町の眺望、暮らしががらりと変わってしまった。
田中 私は最後に書かれていた「私たちは現場のリアリティーに引きずられてしまった。今思い返せば、本当にそこにリアリティーはあったのだろうか」という文章が深く刺さりました。
小松 限られた期間の中で現実的に考えなければ予算や補助金がおりないと迫られるうちに、大切なものが見落とされてしまったと思います。こうした批判的なことも書いたので苦しい思いもしましたし、災害を自分の作品にすることの罪深さも感じました。
田中 書くべきことを敢えて書いたのですね。「いつのまにか関わってくる人が増え、結果的に公共的な存在になる」。これも名言です。これからの日本はほとんどの地域は障害を抱えることになるという意味で、全国的な課題が書かれている気がします。
小松 この本を書いた目的の一つに、福島の本を読みながら自分の地元のことを考えるきっかけになってほしいという思いもあります。
田中 まさにそういう本になっています。「正しい情報だけでは人は動かない。人の心が動くのは、おいしいや面白いや楽しいと相場が決まっている」。これにも共感しました。
小松 データは判断材料としては有力なのですが、それが全てになってしまうと、例えば地元のお年寄りなどからは信頼を得られません。そうなるとせっかくの専門知も無駄になる。専門知と地域の人たちをいかにつなげるかを考え、共に喜び合う空間を作っていくなかで、そこはかとなく情報やデータを示していくことを心がけました。
田中 「間違った発信の中にも正しさは存在している」と書いてありますが、単なるデータだと権威主義になって押し付けになることを気づかされました。
小松 情報発信に関わるなかで、相手の間違いを指摘することで自分の立場を固定してしまう姿を何度も見てきました。相手をいったん受けとめ、顔を見ながら過ごすうちにわかり合えることがある。共通の場を作ると理屈だけではどうにもならないことがわかるんです。興味を持ってくれたら「関わってくれるだけでありがたい」と切り替えていかなければ対話のチャンネルは生まれないのです。
実は僕もかつてはデータ主義でした。でも、データを発信しても、それだけでは伝わらない。意見が同じ人を仲間にして、そうでない人を敵視してしまう分断は福島県にもあらゆるところにある。こうあるべきに縛られず、むしろ他者の考えを変えるのは難しいし時間がかかると認めてしまえば、余裕もできて楽になることに気づきました。そんな失敗を踏まえた軌道修正や方向転換のプロセスをありのままに書きました。
田中 調査の過程で魚屋さんに何度も通った話は面白かったです。知ろうとすることが自分の生活を豊かにするという循環をつかまえたのが素晴らしい。
小松 こんなことを言ったら怒られるかもしれませんが、震災をきっかけにあらためて暮らしと向き合うことで、豊かになったと感じています。復興って自分の興味や関心を犠牲にして公に尽くす面もありましたが、自分の興味や関心をちょっと社会に出してみたら、いろいろな人がつながって暮らしが豊かになった。そうなってみて初めて復興は個人の暮らしをより豊かにしていくことから始めるべきものだと気づいたんです。たとえ震災後の福島だとしても、自分の人生を楽しまないと亡くなった人達に顔向けできない。まずは自分が楽しむ。そのかわり自分が楽しんだことをどんどん社会に発信していく。その結果、少しずつ社会がつながり、何らかの課題が解決できればいいし、できなくてもそれはそれでいい。
田中 本も面白いけれど、お話も面白いですね。
小松 本を書く時は大学で勉強した一般教養が役に立ちました。大学で得た知識をベースにしながら、現場で経験したことを書いただけです。
田中 小松さんの言葉の力はすごいですよ。今度は地域で生きるというのはどういうことなのかというテーマで書いてください。本日はありがとうございました。
『新復興論』(ゲンロン)
https://genron.co.jp/books/shinfukkou/

- 地域活動家 小松 理虔(こまつ りけん)
1979年11月生まれ。2003年法政大学文学部卒業。屋号「ヘキレキ舎」として文筆、 媒体制作、広報PR、イベント企画、各種プロジェクトのマネジメントなど、地域に根ざしたよもやま業。単著『新復興論』で第18回大佛次郎論壇賞受賞。共著に『常磐線中心主義』、震災文芸誌『ららほら』、『ローカルメディアの仕事術』など
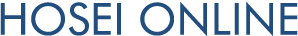




 法学部国際政治学科4年
法学部国際政治学科4年 MAGO MOTORS JAPAN株式会社 取締役
MAGO MOTORS JAPAN株式会社 取締役 現代福祉学部福祉コミュニティ学科1年
現代福祉学部福祉コミュニティ学科1年 株式会社シテコベ 代表取締役CEO
株式会社シテコベ 代表取締役CEO 東芝エネルギーシステムズ株式会社 取締役
東芝エネルギーシステムズ株式会社 取締役 文学部地理学科4年
文学部地理学科4年 スポーツ健康学部スポーツ健康学科3年
スポーツ健康学部スポーツ健康学科3年 国際熱帯農業研究所(IITA) 研究員
国際熱帯農業研究所(IITA) 研究員 フェンシング日本代表
フェンシング日本代表 法政大学大学院理工学研究科機械工学専攻
法政大学大学院理工学研究科機械工学専攻 森岡書店店主
森岡書店店主 水中考古学者
水中考古学者 地域活動家
地域活動家 天領盃酒造株式会社 代表取締役
天領盃酒造株式会社 代表取締役 小説家
小説家 石垣市議会議員
石垣市議会議員 日本近代思想史家
日本近代思想史家 株式会社 プロシップ 取締役会長
株式会社 プロシップ 取締役会長 前橋育英高等学校 校長・サッカー部監督
前橋育英高等学校 校長・サッカー部監督 夕張市長
夕張市長 元税理士
元税理士 プロスキーヤー
プロスキーヤー 法政大学経済学部教授・小説家
法政大学経済学部教授・小説家 特定非営利活動法人ReBit2016年度成人式代表
特定非営利活動法人ReBit2016年度成人式代表 ブルッキングス研究所 シニア・ファイナンシャルマネージャー
ブルッキングス研究所 シニア・ファイナンシャルマネージャー 国連難民高等弁務官(UNHCR)駐日事務所 法務アソシエイト
国連難民高等弁務官(UNHCR)駐日事務所 法務アソシエイト 日本学術振興会特別研究員
日本学術振興会特別研究員 「みんなの孫プロジェクト」代表取締孫
「みんなの孫プロジェクト」代表取締孫 NOSIGNER
NOSIGNER 猿田彦珈琲株式会社代表取締役
猿田彦珈琲株式会社代表取締役 女優・作家
女優・作家 コミックアーティスト(漫画家)
コミックアーティスト(漫画家) 国際レーシングドライバー
国際レーシングドライバー 株式会社ドーム代表取締役社長
株式会社ドーム代表取締役社長 資生堂執行役員
資生堂執行役員 玉ひで主人
玉ひで主人 日立ソリューションズ常務執行役員
日立ソリューションズ常務執行役員 セブン&アイ・ホールディングス代表取締役社長兼COO
セブン&アイ・ホールディングス代表取締役社長兼COO ミサワホーム代表取締役社長
ミサワホーム代表取締役社長 幻冬舎取締役兼専務執行役員/編集・出版本部本部長
幻冬舎取締役兼専務執行役員/編集・出版本部本部長 カルビー(株)代表取締役社長兼COO
カルビー(株)代表取締役社長兼COO フリーアナウンサー
フリーアナウンサー 社団法人アスリート・ソサエティ代表理事
社団法人アスリート・ソサエティ代表理事