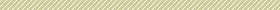ブランドづくりのポイントは企業も大学も同じ
 林高広さん
林高広さん
法政だからこそ身に着いた「起業家精神」
田中 林さんには以前、「アクテアハート」という化粧品のCM出演でお世話になっているんですよね。
林 「美しい50歳がふえると、日本は変わると思う。」というのがテーマのブランドで、モデルではなく、先生はじめ文化人、芸術家の皆さまにご登場いただくという、当時としては斬新な企画でした。
田中 そんなクリエイティブな分野を中心にご活躍ですが、ご出身は経営学部。法政で学んだことはお役に立っていますか。
林 実務というより人間力の面で大いに。たとえば、自分で切り開かなければ次へは進めないという一種の起業家精神は、まさに法政の校風の中で磨かれ、いまに生きています。
田中 そうそう、法政は、いろいろ刺激は与えるけれど、手取り足取りはせず、自分なりに返せばそこはきちんと評価してくれるんですよね。
林 私は兵庫の高校球児で、関西の大学のスポーツ推薦の話もあった。でも、野球はもういい、ただ東京の六大学にはいきたいと思ったんですね。それで、古い歴史にしばられない、開かれた自由さを感じた法政を受験しました。
入ってみると、私の勝手なイメージは裏切られた(笑)。ビルの谷間のキャンパスはなにか殺伐としていて、学生は自由だけれど何かみんなバラバラって感じでしたね。
田中 ミッション系女子校の束縛から解放されたかった私には、その殺伐とした自由こそが期待通りでしたが(笑)。
林 しばらくは悶々として、授業にもあまり出ず、友人と喫茶店にたむろしては、1日中人生についての議論ばかりして過ごしました。2年生になって、これではいけない、自分たちで何か新しいことを始めようじゃないか、と。
田中 自由な議論の中で、社会とのかかわりを自然に考えさせる。それも法政という「場」の力なのかもしれません。
林 といっても、そのとき私の発案でできたのは、喫茶店でコーヒー片手に生まれたから「コーヒー研究会(通称カフェ研)」という、やや安直な名前のサークルでしたが、でも日本初(笑)。
ただ、それまでにないものにしたいと考え、コーヒーの研究はまじめにやりつつ、合宿では体育会の友人をコーチに雇ってスキーやテニスなどを本格的に練習したり、ダンスパーティはナベプロさんに直談判して銀座のライブハウスを借りたりしたんですよ。
田中 その企画力、コーディネート力、交渉力は、間違いなく後のお仕事につながっていますね。
本物だから提供できるリッチ

田中 有意義な学生生活の中、肝心な授業はいかがでしたか(笑)。
林 全然出席しなかったんですが、なぜか結構成績は優秀な学生だったんですよ。ゼミは、三井、三菱など旧財閥系六大企業集団(当時)を扱ったものを選んだ。外資系企業が上陸し始めた時代に、国際化に取り組んだそれら巨大企業に、興味と憧れを持ちましてね。
田中 すでに視点がグローバルだったんですね。ではなぜ資生堂に?
林 実際はかっこ良さ優先で、横文字系の会社を中心に受け、いい感触も得ていました。でも、資生堂から内定をもらったとき、芸術をかじっていた父が、デザインが素晴らしいところはきっといい会社だからと、強く勧めた。私自身も、資生堂のテレビCMが大好きだったので、その一声でつい入ってしまったんです(笑)。
田中 たしかに当時、資生堂のCMは最先端を走っていましたよね。
林 そのルーツをたどれば明治5年、海軍病院の薬局長だった福原有信が銀座で、日本初の西洋調剤薬局を創業。さらに、視察で訪れたアメリカのドラッグストアで、病人が笑顔でソーダを飲むのを見て、これぞ「医食同源」だと、必要な機械一式はもとより、グラス・スプーン・シロップに至るまで直ちに取り寄せて店で提供し、一大ブームとなった。これが資生堂パーラーの始まりです。
田中 新しいものを積極的に取り入れる姿勢はそのときから受け継がれている。
林 それと本物志向ですね。息子の福原信三(資生堂初代社長)は「リッチ」という言葉を使いましたが、これは高級というだけでなく、心の豊かさをも意味しています。物事のうしろにはそれぞれ文化があり、その文化価値を踏まえた「本物」でなければリッチは提供できない、と。
田中 女性の登用など組織づくりの面でも、資生堂は先進的ですよね。
林 商品が化粧品ということもあり、女性の力の活用にはいち早く取り組みました。
ただ、人材のダイバーシティという点ではまだまだです。売上はすでに海外が50%を超えているんですが、海外向けの商品開発や宣伝企画はいまだに日本人スタッフが中心、それでは海外での競争には勝てません。この点の改善を、ここ1、2年で急速に推し進めているところです。

ブランディングもお客さま志向が大切
田中 現在私どもは、大学のブランディングに取り組んでいるんですよ。
林 それは大賛成ですね。企業も大学もブランディングのポイントは共通で、5点あると思うんです。
第一は、思いや志を言葉(コピー)にし、さらにそれを形にするデザインの力。
第二は、革新と伝統の力。普通、順番は「伝統と革新」ですが、私は時代時代の革新の積み重ねがあって初めて伝統が生まれるのだと考えています。
田中 ただ古いものを守っても、伝統にはならない......江戸文化を考えてもそうですね。
林 第三は、自分たちの「美学」を物語にする力、これこそがオリジナリティを生み出します。商品のすぐれた機能も、あるいは大学の歴史や校風や教育内容も、それを物語にできなければ伝わりません。
第四は、やはり自らをグローバルに開く力です。もはやグローバルでないものはブランドにはなりません。
田中 法政はいまや非常にグローバル化が進んだ大学の一つですが、そのことは学生を集める宣伝文句としてではなく、ブランディングの前提として大切なんですね。
林 最後は、お客さまや学生、つまり受け手の立場から発想する力。手前勝手ではダメで、受け手が求めているものを理解できて初めて、いいブランドと認めてもらえるのです。
田中 ブランドは受け手が作る! その発想はありませんでした!
学生に焦点をあてると、あまりに多様なので拡散してしまう気がしていたんです。でも、一方に自分たちの革新と伝統や美学がしっかりあるわけですから、両者の間を往復しながら作っていけばいいわけですよね。
ところで、法政は元々の6学部から、時代のニーズに合わせて15学部に増やしましたが、それとともに大学のイメージが希薄化したことは否めません。学部ごとの個性と全体のブランドをどう結びつけるか、これがまた難しい。
林 弊社も、お客さまの多様化に対応して立ち上げたブランドが100を超え、コーポレートブランドとの間で同様な問題が生じています。ブレてはいけない企業や大学全体の理念はいわば血液で、ブランドは生き物であり進化するものという発想が必要なのではないでしょうか。
田中 たとえブランドが確立しても、それは盤石なものではなく、考え続けつくり続けていかなくてはならないということですね。
今日はたいへん勉強になりました。ありがとうございました。

- 資生堂執行役員 林高広(はやしたかひろ)
1956年兵庫県生まれ。1979年法政大学経営学部卒、資生堂入社。本社推販部、マーケティング開発室勤務後、1991年新会社ディシラの立ち上げにかかわる。2003年本社宣伝部長を経て、2006年ディシラ代表取締役社長就任、2011年資生堂パーラー代表取締役社長、2013年より資生堂執行役員就任、現在クリエーティブ本部長(CCO)として宣伝デザイン、企業文化、資生堂パーラー、ザ・ギンザを担当。
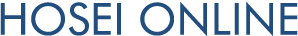




 法学部国際政治学科4年
法学部国際政治学科4年 MAGO MOTORS JAPAN株式会社 取締役
MAGO MOTORS JAPAN株式会社 取締役 現代福祉学部福祉コミュニティ学科1年
現代福祉学部福祉コミュニティ学科1年 株式会社シテコベ 代表取締役CEO
株式会社シテコベ 代表取締役CEO 東芝エネルギーシステムズ株式会社 取締役
東芝エネルギーシステムズ株式会社 取締役 文学部地理学科4年
文学部地理学科4年 スポーツ健康学部スポーツ健康学科3年
スポーツ健康学部スポーツ健康学科3年 国際熱帯農業研究所(IITA) 研究員
国際熱帯農業研究所(IITA) 研究員 フェンシング日本代表
フェンシング日本代表 法政大学大学院理工学研究科機械工学専攻
法政大学大学院理工学研究科機械工学専攻 森岡書店店主
森岡書店店主 水中考古学者
水中考古学者 地域活動家
地域活動家 天領盃酒造株式会社 代表取締役
天領盃酒造株式会社 代表取締役 小説家
小説家 石垣市議会議員
石垣市議会議員 日本近代思想史家
日本近代思想史家 株式会社 プロシップ 取締役会長
株式会社 プロシップ 取締役会長 前橋育英高等学校 校長・サッカー部監督
前橋育英高等学校 校長・サッカー部監督 夕張市長
夕張市長 元税理士
元税理士 プロスキーヤー
プロスキーヤー 法政大学経済学部教授・小説家
法政大学経済学部教授・小説家 特定非営利活動法人ReBit2016年度成人式代表
特定非営利活動法人ReBit2016年度成人式代表 ブルッキングス研究所 シニア・ファイナンシャルマネージャー
ブルッキングス研究所 シニア・ファイナンシャルマネージャー 国連難民高等弁務官(UNHCR)駐日事務所 法務アソシエイト
国連難民高等弁務官(UNHCR)駐日事務所 法務アソシエイト 日本学術振興会特別研究員
日本学術振興会特別研究員 「みんなの孫プロジェクト」代表取締孫
「みんなの孫プロジェクト」代表取締孫 NOSIGNER
NOSIGNER 猿田彦珈琲株式会社代表取締役
猿田彦珈琲株式会社代表取締役 女優・作家
女優・作家 コミックアーティスト(漫画家)
コミックアーティスト(漫画家) 国際レーシングドライバー
国際レーシングドライバー 株式会社ドーム代表取締役社長
株式会社ドーム代表取締役社長 資生堂執行役員
資生堂執行役員 玉ひで主人
玉ひで主人 日立ソリューションズ常務執行役員
日立ソリューションズ常務執行役員 セブン&アイ・ホールディングス代表取締役社長兼COO
セブン&アイ・ホールディングス代表取締役社長兼COO ミサワホーム代表取締役社長
ミサワホーム代表取締役社長 幻冬舎取締役兼専務執行役員/編集・出版本部本部長
幻冬舎取締役兼専務執行役員/編集・出版本部本部長 カルビー(株)代表取締役社長兼COO
カルビー(株)代表取締役社長兼COO フリーアナウンサー
フリーアナウンサー 社団法人アスリート・ソサエティ代表理事
社団法人アスリート・ソサエティ代表理事