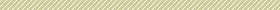アートの力で「サステナブル・キャピタリズム」という新たな価値観を世界の人たちに広めたい
 木村 太一さん
木村 太一さん
将来は自分で事業を興したいという思いで法政大学経済学部へ
廣瀬 本日は、法政大学の卒業生で、アートの力で途上国支援のソーシャルビジネスを展開する「MAGO MOTORS JAPAN株式会社」を、美術家の長坂真護さんと共に立ち上げた木村太一さんを訪ねて、東京・港区のアトリエにお邪魔しています。このアトリエは事業活動の中でどのような役割を担う場所なのでしょうか。
木村 私たちはこの空間を使って、これからお話しする「サステナブル・キャピタリズム」という新たな経済の価値観を、アート作品やプロダクトという形で展示しています。一般公開ではなく希望者をお招きしているため、ここに来て下さる方はこうしたテーマに関心を持ち、ご自身の生活やビジネスにもその要素を取り込んでいきたいと考えている方が多いと思います。そのため、何かの発見や新しい気づきを求めて訪れているという印象を受けます。
廣瀬 非公開ということもあると思いますが、ある程度御社を理解し、関心がある方々というメンバーシップがあり、ある種のコミュニティが形成され、様々な意見や価値観、情報を交換するプラットフォームと言えそうですね。
木村 まさにプラットフォームのような形で、ここで芸術文化に触れ、その先にある社会貢献やサステナブルについて、意見交換を行えるコミュニティとして機能すべきだと思っています。
廣瀬 具体的なお話を伺う前に、これまでの歩みを伺いたいと思います。まず、法政大学経済学部に入学されましたが、高校生の時にどういう考えで大学を選ばれたのでしょうか。
木村 漠然とした夢は持ちつつも、将来これをしたいという具体的な夢は持っていませんでした。ただ、父親をはじめとし親戚には自分自身で事業を作り上げた人が多く、そうした人の背中を見て育ってきたため、将来は自分で事業を興すのだろうというイメージだけは持っていました。そのため経済学部に関心を持ったのですが、法政大学を選んだのは、実は私の家族親族に11名もの法政大学出身者がいたため、おのずと進路は決まっていました(笑)。
廣瀬 そうでしたか。実際に入学した法政大学はいかがでしたか。
木村 広大で自然豊かな多摩キャンパスで、キャンパスライフを友人たちと送ることができたのは貴重な体験でした。こうした環境は都心にはなかなかありません。高校時代、福井県福井市の市街地で過ごしていたため、東京の大学に行くぞ! と憧れて上京してみたら、高校時代より自然豊かな場所で学ぶことになったことに、最初は戸惑う気持ちもありましたが、慣れてくるととても居心地が良くなりました。
仕事をする上で抱いた違和感が新たなチャレンジに繋がる

廣瀬 卒業後、最初の会社はどのような理由で選んだのですか。また、その後も含め、どのようなキャリアを経験されてきましたか。
木村 新卒の際は、将来自分で事業を回していきたいという考えから、「商い」を覚えたいという思いと、海外でのビジネスに関心があったため、地元福井県の商社に営業職として入社しました。ところが、5年目の時に会社が経営破綻してしまい、これが自分自身の人生を考える最初のターニングポイントになりました。会社を畳むというフェイズで、法律家や税理士など様々なフィールドの方と仕事をするなかで、なぜ会社は倒産をしてしまうのか、企業の経営そのものに興味を持ち始めました。そこで東京に戻り、国内大手のコンサルティング会社に転職しました。
廣瀬 新たな職場ではどのような業務に就いていたのでしょうか。
木村 企業コンサルティングでは、果てしなく企業の売上を伸ばしていくか、もしくは果てしなくコストをゼロに近づけるか、大きく分けると2つの視点がありますが、私は後者の業務を担当しました。5年ほどこの業務に就いていたのですが、3~4年目の頃に自分の中で違和感を持つようになりました。企業にとってのコストカットの一番は人。人件費です。毎年企業に向けて「何人減らしました」「来年は何人減らします」という話をするのですが、果たしてこれが社会にとってどのような効果があるのか。終わりのない資本主義の流れを加速しているに過ぎないのではないかと考えるようになりました。
そんな折に、同郷で以前から親しくしていた長坂が、ガーナで1人で活動を始めたことをSNSの発信から知りました。彼の活動に共感し、何とかサポートできないか、連絡をしたのが長坂とのビジネスのきっかけです。ただ、会社を飛び出して2人で活動を共にするという決断はすぐにはできませんでした。
しかし自分がコンサル業界で今後10年20年歩んでいく未来像が描けなかったので、再度転職することを決めました。会社規模の大小を問わず様々な会社を探していた中で、20名ほどの規模のスタートアップ企業に出会ったのですが、そこで働く人たちが、私が思い描いているパッションだったり生きるエネルギーを持っている人たちで、7000名規模の大企業から小さな会社に移る選択に躊躇はあったものの、思い切ってこの会社を選び2度目の転職をしました。結果的にこの経験が大きく、周りで触れ合う人たちが挑戦者で溢れていて、彼らが自身の人生に真っ向から立ち向かう姿を見て、"これだ!"と。自分の人生で挑戦をしないと絶対に後悔するし、挑戦するからこそ社会に新しい価値を産む。この経験があって後に長坂と独立する決断に至りました。
廣瀬 そのスタートアップではどのような仕事を担当されたのでしょうか。
木村 企業とスタートアップを結ぶプラットフォームの運営をしていました。大企業側には、これから新しい価値観、テクノロジーをいち早く低コストで取り入れたいというニーズがあります。一方、スタートアップ側には、最先端の開発や技術を武器にしたいと思っても圧倒的にリソースが足りないという課題があります。そこをマッチングするという業務でした。
廣瀬 そこでの経験は、現在のビジネスの立ち上げに生かされていますか。また、複数社、違う業務に携わってきましたが、何か今に繋がっていますか。
木村 そうですね。3社ともバラバラな職種でしたが、実際に自分たちが起業して、スタートアップという立場になった今、振り返ると点と点が繋がっていたと思います。今後、いろいろな会社と連携して、産業を育てて事業を生み出していかなければなりませんが、特に3社目ではそのヒントになるような経験を積み上げることができました。
スラムで見たアート作品が新たな挑戦への勇気を与えてくれた

廣瀬 現在長坂さんと取り組んでいるビジネスは、ガーナでの活動に共感されたことが始まりだとお聞きしましたが、木村さんが初めてガーナを訪れたのはいつですか。また、実際に現地を訪れていかがでしたか。
木村 長坂の活動を知った後は2年間ほど副業としてサポートしてきました。その後事業が大きくなり、この仕事に専念するために会社を辞め、2022年4月に初めてガーナを訪れました。それまで写真や動画で現地の様子は何度も見ていましたが、現実を目の当たりにして大きなショックを受けました。嗅いだことのない臭い、聞いたことのない金属音、そして見たことのない風景と、五感すべてで初めての感覚を味わいました。愕然としながらスラムを歩いていると、その中心に、長坂が建てた「ムーンタワー」というアート作品がありました。その時すごく勇気づけられました。こんな場所に日本人が足を踏み入れ、現地の人たちと関係性を築き、アート作品を作り上げた事実に、もしかしたら課題解決できるかもしれないと、沈んでいた心に一筋の光が差すような感覚でした。
 野焼きをするスラムの人々
野焼きをするスラムの人々
廣瀬 アートには、100の言葉で語るよりも、そこに存在するだけでインパクトやメッセージを伝えることができる力がありますね。現地の人もそこから何かを受け止めたのかもしれません。長坂さんは世界の様々な場所を旅していたそうですが、そこからガーナに目を向けたのは何かきっかけがあったのでしょうか。
木村 長坂が旅する中で知り合ったアメリカ人の女性から、彼女が農園の経営にサステナブルという視点を取り入れているという話を聞き、「人の健康や環境に配慮したビジネスですね」と伝えたところ、サステナブル経営はもっと奥深いものだと教えてもらったそうです。環境に配慮した商品を作ると、そこにコミュニティが形成され、この自然に配慮したプロダクトは"地球にいいよね"といった文化が生まれます。その文化を通じて、さらに商品が広がり経済圏がつくられる。その経済圏が潤えば潤うほど、同様の農園が増えていく。こうして社会貢献と文化・経済を循環させることができるのだと知り、衝撃を受けたものの、答えが出ないまま2017年に初めてガーナを訪れました。純粋に現地の人たちを救いたいという思いとエネルギーから活動が始まりました。まず取り掛かったのが廃材を使ったアート作品制作でした。現地の人たちが置かれた環境や貧困問題という課題を解決するために、廃材をアート作品に昇華させることで、まず物理的にごみを減らしていく。この文化・芸術を先進国で発表することで、みんなにこの課題を知ってもらいながら、経済圏に変えていけるのではないだろうか。そしてその経済で作ったものを環境に戻していくことで、問題を解決できると考えました。これが私たちの「サステナブル・キャピタリズム」の始まりです。
廣瀬 木村さんが本格的に参加し、ビジネスはどのように動き始めましたか。何か転機はあったのでしょうか。
木村 スタートアップが投資家たちを前に事業プランをプレゼンする「ピッチコンテスト」に長坂が出ていたのですが、決勝を前に私が合流し、コンサル時代の経験を活かしてプレゼン資料を作り上げて長坂とともにプレゼンを行ったところ、まさかの400社の中でグランプリを取ってしまいました。国内有数のコンテストで、グランプリは上場の切符を渡されるぐらいのインパクトがあると言われていて、実際に大手証券会社などから声を掛けてくれたのですが、これが転機になりました。テクノロジーを追求するだけではなく、経済を回しながら社会を良くしていくというポイントが評価されるようになった一つの大きな変化点だったと思います。
スラムの人たちの生活と仕事に新たな選択肢を切り開きたい
廣瀬 現在ガーナで「EV事業」「リサイクル事業」「農業」などを行っています。さきほど伺った「サステナブル・キャピタリズム」の考え方に照らすと、それぞれ根っこでは繋がっているのだと思いますが、ぱっと見た印象でいうと、ばらばらの事業に思えます。どのような判断を経てこうした事業に取り組んでいるのでしょうか。
木村 まずは、目の前の課題だったごみ問題を解決に導くためリサイクル事業に着手しました。さらに大気汚染や土壌汚染が進んでいるため、新たに農園を作っていこうとなりましたが、EV事業は少し背景が異なります。スラムは都市の近郊に作られることが多く、極貧のエリアです。ガーナも例にもれず、都市部から車で15分ほどのところに3万人が暮らすスラム街があるのですが、これが国から見ると国有地なんです。ガーナ政府は、世界からの目も気にしたのだと思います。そのエリアを観光地として開発するといった名目で、2022年7月に軍隊を送り込み、土地の半分を制圧。殺傷力の低いゴム銃を使って強行的に住民を追い出すという出来事がありました。長坂が建てたアートギャラリーも破壊されました。実はこのことがEV事業に取り組むきっかけとなりました。私たちは、スラムの住民に残りの半分もいつ制圧されるかわからないから、スラムを統括するチーフに、都市部から少し離れるが私たちが場所を確保するからそこに一緒に移り住まないか、という提案をしました。しかし自分たちの生まれた町を離れることに簡単に同意はしてもらえませんでした。そこで世界の過去の事例、大手自動車メーカーが工場を作ったら工場周辺に人が大移動したことをヒントに、誇りと将来性をもって仕事に取り組める環境を用意する。彼らの成長を促せる、彼らの誇りにつながるような先進的な事業を起こしたいと考えたのが、EV事業でした。
 日々、電子機器を野焼きして生活するスラムの人々と
日々、電子機器を野焼きして生活するスラムの人々と
廣瀬 スラム街にはおそらく公共交通は整備されていないでしょうから、移動手段を得ることができれば、生活の選択肢、稼ぐ場所の範囲を広げてくれますね。移動手段があれば稼ぐことができる。新しい事業の展開も可能になって、雇用が生まれると、新たな移動手段を購入できる人も増えていく、といった循環がまさに始まりますね。
木村 私たちは今、無償のバスを運行する準備を進めています。移動という手段を提供することで、新たな選択肢も提供できます。そうした費用を、日本の企業にラッピング広告としてバスを活用してもらうなど、メリットを用意することで、協力してもらえるような仕組みを考えています。
廣瀬 現地でのマネタイズなどは、これまでの木村さんのキャリアが役に立ちそうですね。2030年には1万人の雇用を実現するという目標をお持ちですが、今後の展望についてお聞かせください。
木村 まず、国が介入した半分の土地ですが、2年経った今も全く活用されていません。私たちは現在、ガーナ政府にサステナブルタウンの形成を提案しており、一定の評価もしていただいています。しかしネックとなるのが資金です。そのため、これからはファンド形成も視野に、リターンとしてアート作品を提供するなど、独自の金融サービスを作り、その運用益を資金として活用したいと考えています。スラムという資本主義が生み出した一種の"バグ"を、資本主義のシステムを使って是正していく考えです。
廣瀬 長坂さんのアートには、スラムでのごみ問題、それを解決したいと思う人たちがいるというストーリ全体が凝縮されたものだと思います。これまでも、新しい価値を資本主義に取り入れようとした人はたくさんいますが、アートを通し、そのアートの力によって、その新しい価値をさらに拡大していくことで、その循環の輪を無限にしていくという考えは、大きな影響力を持っていると思います。最後に、学生たちにメッセージをいただけますか。
 現地リサイクル工場のメンバーたちと(中心にいるのが長坂氏、その隣が木村氏)
現地リサイクル工場のメンバーたちと(中心にいるのが長坂氏、その隣が木村氏)
木村 挑戦すること、行動すること。これを大事にしてほしいと思います。もちろんリスクはありますが、日本はスラムとは違います。挑戦しても死にはしません。何とかなります。大企業勤めの際の自分の場合、挑戦するリスクは何だったんだと考えると、社会的な評価でした。ただ、今行っていることは大企業の一員であったら決してできなかったことです。もう一つは、今AI革命などと言われていますが、私たちは、サステナブル革命が起きていると感じています。社会に良いことをしようとする起業家を応援する制度が整ってきています。自分の中の違和感に耳を傾けながら、自分の信じる道に飛び込む勇気をもって、新しい人生を歩んでいただければ嬉しいです。
廣瀬 本日はありがとうございました。

- MAGO MOTORS JAPAN株式会社 取締役 木村 太一(きむら たいち)
1988年福井県生まれ。2011年3月法政大学経済学部国際経済学科卒業。商社、総合コンサルティングファーム、スタートアップ企業など3社を経て、2022年9月、美術家・長坂真護などと共にMAGO MOTORS JAPANを設立。先進国が生み出した電子機器の廃棄物が集積し「世界最大級の電子機器の墓場」と言われるガーナのスラム街の過酷な環境の改善を目指し、多様な事業から現地の環境・貧困問題の解決を目指す。2024年3月時点で現地雇用53名。2030年までに1万名の雇用を達成し、スラム撲滅を目指す。
- 法政大学総長 廣瀬 克哉(ひろせ かつや)
1958年奈良県生まれ。1981年東京大学法学部卒業。同大大学院法学政治学研究科修士課程修了後、1987年同大大学院法学政治学研究科博士課程単位取得退学、同年法学博士学位取得。1987年法政大学法学部助教授、1995年同教授、2014年より法政大学常務理事(2017年より副学長兼務)、2021年4月より総長。専門は行政学・公共政策学・地方自治。複数の自治体で情報公開条例・自治基本条例・議会基本条例などの制定を支援の他、情報公開審査会委員などを歴任。
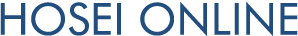




 法学部国際政治学科4年
法学部国際政治学科4年 MAGO MOTORS JAPAN株式会社 取締役
MAGO MOTORS JAPAN株式会社 取締役 現代福祉学部福祉コミュニティ学科1年
現代福祉学部福祉コミュニティ学科1年 株式会社シテコベ 代表取締役CEO
株式会社シテコベ 代表取締役CEO 東芝エネルギーシステムズ株式会社 取締役
東芝エネルギーシステムズ株式会社 取締役 文学部地理学科4年
文学部地理学科4年 スポーツ健康学部スポーツ健康学科3年
スポーツ健康学部スポーツ健康学科3年 国際熱帯農業研究所(IITA) 研究員
国際熱帯農業研究所(IITA) 研究員 フェンシング日本代表
フェンシング日本代表 法政大学大学院理工学研究科機械工学専攻
法政大学大学院理工学研究科機械工学専攻 森岡書店店主
森岡書店店主 水中考古学者
水中考古学者 地域活動家
地域活動家 天領盃酒造株式会社 代表取締役
天領盃酒造株式会社 代表取締役 小説家
小説家 石垣市議会議員
石垣市議会議員 日本近代思想史家
日本近代思想史家 株式会社 プロシップ 取締役会長
株式会社 プロシップ 取締役会長 前橋育英高等学校 校長・サッカー部監督
前橋育英高等学校 校長・サッカー部監督 夕張市長
夕張市長 元税理士
元税理士 プロスキーヤー
プロスキーヤー 法政大学経済学部教授・小説家
法政大学経済学部教授・小説家 特定非営利活動法人ReBit2016年度成人式代表
特定非営利活動法人ReBit2016年度成人式代表 ブルッキングス研究所 シニア・ファイナンシャルマネージャー
ブルッキングス研究所 シニア・ファイナンシャルマネージャー 国連難民高等弁務官(UNHCR)駐日事務所 法務アソシエイト
国連難民高等弁務官(UNHCR)駐日事務所 法務アソシエイト 日本学術振興会特別研究員
日本学術振興会特別研究員 「みんなの孫プロジェクト」代表取締孫
「みんなの孫プロジェクト」代表取締孫 NOSIGNER
NOSIGNER 猿田彦珈琲株式会社代表取締役
猿田彦珈琲株式会社代表取締役 女優・作家
女優・作家 コミックアーティスト(漫画家)
コミックアーティスト(漫画家) 国際レーシングドライバー
国際レーシングドライバー 株式会社ドーム代表取締役社長
株式会社ドーム代表取締役社長 資生堂執行役員
資生堂執行役員 玉ひで主人
玉ひで主人 日立ソリューションズ常務執行役員
日立ソリューションズ常務執行役員 セブン&アイ・ホールディングス代表取締役社長兼COO
セブン&アイ・ホールディングス代表取締役社長兼COO ミサワホーム代表取締役社長
ミサワホーム代表取締役社長 幻冬舎取締役兼専務執行役員/編集・出版本部本部長
幻冬舎取締役兼専務執行役員/編集・出版本部本部長 カルビー(株)代表取締役社長兼COO
カルビー(株)代表取締役社長兼COO フリーアナウンサー
フリーアナウンサー 社団法人アスリート・ソサエティ代表理事
社団法人アスリート・ソサエティ代表理事