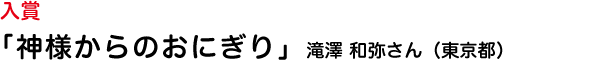
幼い頃、よく母に連れられて町のお祭りに参加し、山車を引いた。母は私に「山車には神様が乗っている」と言い、私はそれを信じていた。
山車を神社まで引き終わると、毎年そこでおにぎりが二つ振舞われた。それは笹の葉を模した紙に包まれた上品なおにぎりで、中身は梅干しとおかかだけだったが、それらが海苔の香りとご飯のほんのりとした甘みが引き立てており、まさに絶妙な味わいだった。その味は大人達の間でも人気だったらしく、
「お祭りで貰えるおにぎりは美味しい」と町で評判になっていた。私はそのおにぎりを、神様からの贈り物だと信じていた。山車の中にいる神様が、私達に優しくてくれているのだと思っていた。
私の年齢が二桁になる頃、私の一家は東京に引っ越した。車で新しい家に向かう際、私は母に、これから行く街でもお祭りでおにぎりが食べられるかと聞いた。すると母は、あのおにぎりはあの町で評判のお弁当屋さんが作ったものだから、まったく同じものは食べられないかもねと笑った。それを聞いて初めて、私はあのおにぎりは神様の贈り物ではなかったのだと知った。
それから更に十年が経ち、大学に進学した私は、毎週のように研究室で徹夜する日々を送っていた。夜十二時を過ぎると、決まって友人達と夜食を求め近所のお惣菜屋さんを訪れた。私達が行く時間にはもうお弁当やお惣菜はほとんど売り切れていて、店内にはおにぎりしか残っていない。しかし大学の近辺には他にコンビニ等はなく、深夜までやっているそのお惣菜屋さんは本当に有難かった。そのお店のカウンターにはいつも無愛想なお婆さんが一人で座っていた。毎週のように通っていたにも関わらず、通い始めて半年を過ぎても言葉を交わしたことはほとんどなかった。
ある初冬の夜、いつものようにそのお総菜屋さんを訪れると、店のシャッターが降りていた。この店が閉まっているのを初めて見たので、私達は驚いて店に近づいた。するとシャッターの前にいつもは無い小さな椅子がちょこんと置いてあり、その上には私達の人数分のおにぎりと、繊細な字で書かれた置き手紙があった。
『今日は体調がすぐれないので早目に店を閉めます。おにぎりが冷えているかもしれないので、温めて食べて下さい』
その手紙を読んで初めて、あのお婆さんが私達のためだけに店を遅くまで開けていた事に気付いた。また同時に、このおにぎりも、そしてあのお祭り後のおにぎりも、やはり神様からの贈り物なのだと知った。
私達は気付かぬうちに、誰かに優しくしてもらっている。そんな当たり前のことに、おにぎりを通して、この年になってようやく気付いたのだった。
![]()



