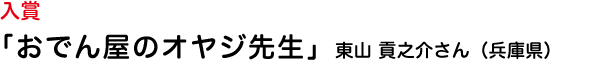
会社の顧問が退職しておでん屋をはじめるという。「人生あと何年生きるかわからない。昔から客商売を一度やってみたかった」
長年、経理一筋で勤めてきた人にそんなことが出来るだろうか、と半信半疑でいたところ、本当にミナミの盛り場で店を開いてしまった。夜七時から翌朝五時まで、これまでの暮らしぶりとはまったく違う昼夜逆転の生活だ。
開店早々、仕事帰りにのれんをくぐると、顧問はすっかりおでん屋のオヤジに変身、仕込みの真っ最中。業務用のおでん鍋には、だいこん、厚揚げ、じゃがいも、こんにゃく、ごぼう天と定番の品がそれぞれのブースの中に規則正しく並んでいる。
「いっぺんこれ食べてみて」。差し出されたのは「だいこん」。「もっと味が浸みなあかん」と一人前に答えると「まだあかんか。おでんはダシが命やからな」と苦笑い。
顧問の信条は昔から亀のようにゆっくり歩むこと。日々研鑽はかかさない。すじ、たこ、コロなど、店を訪ねる度におでんの種類が増えた。一年経つと「だいこん」にはすっかりオヤジの味が浸み込み、ほどよくやわらかく、ほっこりして店一番の売れ筋商品となった。
「ところで、その後、仕事の方はどない」仕事の話になるとオヤジは突然、先生になる。聞かれるままに話していると「そんなことやからお前はいつまでたっても進歩しない」。おでんの仕込みもそっちのけで、まいかけのポケットから伝票を取り出し、その裏に説明書きをしながら教えてくれる。時々、とんちんかんな質問をすると、まるで不肖の息子を叱るように「これがわかるようになってから来い」と突き放された。
しかし、どういうわけか、盛り場ミナミの喧騒の中、おでん屋の一枚板カウンターで聞く先生の話は不思議とすんなり頭に入った。
常連客も年を追うごとに増え、早い時間に訪ねないと客の出入りが多く、忙しくなって先生のレクチャーもしばしば中断した。
ある日、店に行くと閉まっている。風邪でも引いたかと見舞いの電話をすると、体調を崩して入院していた。一カ月ほどして再開した。病み上がりで少し頬がこけていたが、カウンターの中には、いつもと変わらぬ頑固オヤジの姿があった。「あと三年くらいやな」とぽつりと誰に話すともなくいった。
「0を発見したインド人はえらい」。理数科出身で博識、突然、思いもつかないことをいうクセがあるだけに、独り言は何やら予言めいて感じられた。
開店して七年、オヤジは肺がんで亡くなった。
おでんを食べるたびに思い出す。叱咤激励とほっかほかのおでんが、どれだけ心を温かくしてくれたことか。
オヤジと客、先生と生徒として過ごした日々のおでんの味は忘れられない。
![]()



