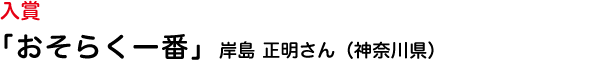
縁側に座っていると遠くの方に鍬を背負って反対の手に麻袋を下げた父の姿がみえる。私が小学校に入ったばかりの頃だから昭和三十五、六年だろう。
犬のピーは繋がれなくても父の後ろをついてくる。よく見ると猫のクロが冬枯れた雑草に身をひそめているし、その周りには放し飼いのニワトリが番いでしきりに畑の土をつついている。
父は終戦後シベリアで抑留生活をしていた為か、酒とジャガイモが大好きだ。気が向くと、かまどの炭火を七輪に移して茹でてあったジャガイモを餅網の上で焼いてくれる。「おやつ」などという言葉を知らなかったこの時分は「こじょはん」と言っていた。多分、「小助飯」と書いたのかもしれない。
ジャガイモは勿論、皮は付いたままで半分に切って塩茹でしたものが、大きな笊に新聞紙がかけてある。それは私が台所から縁側まで運んでくるが結構重い。父の土間を通って台所から焼酎の一升瓶と湯呑茶碗を持ってくる。
縁側から直接、庭に降りられるように置いたコンクリートブロックの上に七輪をセットする。父はもう一度台所に戻って大きな皿と、そして中くらいの皿としょうゆの一升瓶を持って中くらいの皿に上手に注ぐ。
始めに焼くだけの数の茹でたジャガイモを皿のしょうゆに落とし入れ反対側もよく馴染ませる。それから七輪の餅網の上に並べていく。だいたい十個も並ばない、重ねたりしないから。つけたばかりのしょうゆがジャガイモから滴り落ちて、その香ばしい匂いといったらない。繋がれた犬は大騒ぎで遠吠えまでする始末だし、クロもお尻を向けて座っているが尻尾の動きがただならない。ニワトリは寝床に戻ったか。
ジャガイモの表面についたしょうゆが乾くとすぐにアツアツを口に頬張るが、少し大きめのやつはもう一度、付け焼きして少し焦がしたりすると、このとき世界で一番おいしいものは何かと聞かれたらこれだと答えるだろう。おそらく今でも。
父は焼いたジャガイモを犬に放り投げてから、たべるより先に湯呑茶碗に焼酎を満たしてゴクリとのどを鳴らしハーッと息を吐いてから遠くの畑の方を見る。優しい顔ではあったような気がするが何処か遠くにいるような気がしたものだ。
父も亡くなってから十年が過ぎた。いま、私は茹でたジャガイモにしょうゆをたっぷり浸して、オーブントースターに並べて傍らで焼酎のお湯割りを飲んでいる。
![]()



