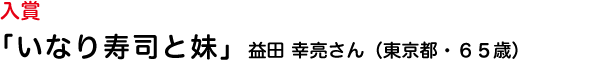
店の扉を開けたら、甘い醤油の香りがしてちらしいなり寿司が目に入った。
酢飯でパンパンに膨らむ三角の油揚げと紅ショウガ、いり卵、エンドウの鮮やかな彩りに腹の虫が鳴く。
突然、店番のおばあちゃんに、「何個ね?ここで食べてゆくと?」と聞かれ思わず
「二個、はいよ(ください)」と応えていた。
そこは大学入試に落ちた失意と、初めて親許を離れる不安で訪れた下宿だった。
老婆と中学生の孫娘の二人暮らし。娘夫婦は熊本市街で居酒屋を営み、殆んど家に帰れないと聞いていた。
いなりを頬張ると、甘煮の油揚げがジュワーと、口いっぱいに広がる。酢飯に馴染んだシイタケとタケノコの食感に浸りながら、おばあちゃんに来意を告げた。
「ああ、あんたがお兄ちゃんかい。よう来たね。待っとったとよ。いなり二つじゃ足らんでっしょ」おばあちゃんは。もう二個、皿に載せてくれた。
案内された私の部屋は青畳のイ草が香り、襖も新しい。隣の三畳間は勉強部屋で、窓に向かって机が二脚並び、本棚まである。おばあちゃんの気遣いに胸が熱くなった。
机に向かっていると孫娘がきて、両手で抱えた教科書や参考書を本棚に並べ出した。
「お兄ちゃん、良子です。今日から宜しく。
私はお兄ちゃんと呼ぶけど、お兄ちゃんは良子と呼んで。妹じゃないけんね」
彼女も隣の机で参考書を広げた。遠慮なくお兄ちゃん、を連発して質問を浴びせ、曖昧な答だと絶対に納得しない。
勉強部屋の二つの机。私は下宿人と言うより、家庭教師なのだとやっと呑み込めた。
毎朝、俎板を叩く音で目覚める。白米、甘酢、具材の煮炊きの香りが順番に漂うと店が開き、おばあちゃんと客の大声で起床する。
私が予備校へ顔を出すのは午前中だけ。良子もニキビの額やうなじに玉の汗を浮かべ、学校から一目散に帰ってくる。彼女が横に座るとブラウスから仄かな匂いが漂った。
毎日、頃合いを見て、おばあちゃんが私にお茶といなり寿司を、良子には紅茶とケーキを持ってくる。おばあちゃんは私がいなり寿司の虜であることを十分心得ている。
「三時のいなりは、お兄ちゃんだけに作る特別料理だよ。私のケーキより何倍も愛情が籠っているんだから」と良子がからかう。
ちらしいなり寿司の絆か、良子は熊本の高校に、私も東京の大学に受かった。わずか一年にも満たない出会いだった。でも、あの四十六年前のおばあちゃんのちらしいなり寿司の味は忘れられない。今は気づいている。良子という妹との想い出が、隠し味として、とても効いていたことも。
もう、おばあちゃんはいないだろう。
良子もおばあちゃんかも知れない。
今も、ちらしいなり寿司を見るたびに、あの頃の全てが蘇る。
![]()



