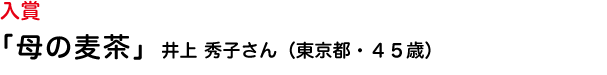
我が家の麦茶が他の家庭とは違う味だと知ったのは、私が小学三年生のときだった。
ちょうどこの頃、初めての引っ越しを経験した私は、完全に心を閉ざしていた。それまでは活発で明るく、友達も多かったのに、引っ越しのせいでガラリと変わってしまった境に戸惑い、なかなかなじめず、結果、ひとりぼっちになってしまった。誰とも言葉を交わせなくなった私は、クラスでも「無口で変わった人」という奇異な目で見られるようになっていった。
初夏の風が気持ちよいその日、遠足で山に登った。当時、母もすっかり変わってしまった私のことをどうしてよいのかわからず、その日も朝から無言でお弁当を作ってくれた。キャラクターの絵入りの水筒に、我が家の夏の定番、麦茶をたっぷり入れてくれて。
「病も気から」とはよくいったもので、この頃の私は顔色も悪く痩せっぽちで、かつての面影は完全に消え失せていた。そして以前なら先頭をきって笑顔で登っていた山道も、中腹あたりでもう息があがって、足もまったく動かなくなってしまった。
「がんばれ。もう少しで休憩だぞ」このとき初めて、担任の先生がそっと背中のリュックを押してくれた。
私のクラスの担任は、年配でベテランの、男の先生だった。頑固そうな顔つきで、実際とても厳しい先生だった。ニコリと笑った顔など見たこともなかった。
休憩時、ひどく疲れてのどもかわいているはずなのに、私は母の持たせてくれた麦茶が飲めなかった。口に運ぶことさえ億劫だったのだ。そんな私の姿をじっと見ていた先生が、ふいに声をかけてきた。
「井上の麦茶、一杯くれ」
私は水筒の赤い蓋に麦茶を注ぎ、震える手でそっと差し出した。するとそれを受け取った先生は一気に飲み干し、クラスのみんなの前で、明るく大きな声でこう言った。
「ああ、うまい!井上の家の麦茶は甘くておいしいな」
「え?井上さんちの甘いの?」「うちのは甘くないよー」「ひとくち飲ませてー」
あっという間に、私のまわりにみんなが集まってきた。先生は私にコップを返すとき、念をおすようにもう一度「うまかったよ、ありがとう」と言ってくれた。
私は、思わず泣きそうになった。いつもと変わらず、おいしい麦茶を作ってくれたやさしい母のことをほめられたからだ。帰宅してこの話をすると、母も黙って泣いていた。
そしてこの出来事をきっかけに、私は徐々にクラスになじんでいった。友達もできた。
子供の頃、毎年夏になると、母は汗をいっぱいかきながら大鍋で大量の麦茶を煮出してくれた。お砂糖の加減は、あくまでそのときの気分次第。味見と称してまだ温かい作り立ての麦茶を飲み干した甘い思い出は、そのまま、母の愛情を投影していたように思う。
![]()



