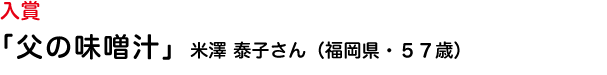
父が味噌汁を作り始めたのは、六十歳で会社を定年退職してからだった。そのころ私は結婚して関西に住んでいたが、母からの電話で「この頃お父さんが味噌汁を作り始めてねぇ」と聞いた時には思わず「うそでしょ」と言ってしまった。なにしろ父は大正生まれの戦中派で『男子厨房に入らず』を地で行くような人だったから、その父が台所で味噌汁を作っている姿は想像もできなかった。
ところが、定年退職を境に父は「これからは家事をする」と家族に“宣言”して、さっそく味噌汁の作り方を母に習い始めた。
①いりこの頭とわたを取って、前の晩に小なべにはった水につけておく
②翌朝鍋を火にかけて、沸騰させないように弱火であくをとりながらだしをひく
③いりこを取り出して、具を入れて煮込み、味噌を入れてひと煮立ちさせる
書けばこれだけのことも、料理音痴の父には『わた』の意味からいちいち説明しなければならず、母は内心厄介なことになったと思っていたらしい。それでも一か月もたつと父は何とか一人で味噌汁が作れるようになり、いつの間にか朝は夫婦で台所に立つのが実家の定番になった。
具も最初はせいぜい二種類位だったのが、しだいに『相性の良い具』を工夫して三種類、四種類と増え、いりこも味噌もあれこれ試してお気に入りのものを使うようになった。子ども達をつれて里帰りすると父は、「近ごろの子供は魚を食べないそうだから」と、近所の魚屋で鯵や鰯をつみれにしてもらい、野菜たっぷりの味噌汁に入れて孫たちに食べさせた。新鮮なつみれ入りの味噌汁は臭みもなく、子どもたちも私も「おいしい、おいしい」とお代わりをして食べた。父は「これさえあればおかずはいらん」と上機嫌だった。
父の味噌汁は、母が病気で料理ができなくなるとますます“進化”して、食欲のない母のためにのど越しの良いにゅう麺と野菜を煮込んだり、つみれや肉団子のボールを入れたりして、主食とおかずを兼ねたようなものになっていった。その後、姉と私が交代で実家の家事をするようになっても、父は味噌汁だけは自分で作り続けた。お椀になみなみとよそわれた、父の具だくさんの味噌汁は、ふんわりとやさしい味がした。
そんな父が倒れて救急車で病院に運ばれたのは、二月の寒い夜だった。急いで駆け付けた実家の台所には、いりこの入った鍋がガス台に置かれ、そばには具の野菜やそうめんがきちんと並べられていた。まさか自分が夜中に倒れてそのまま逝くことになるとは夢にも思わなかった父は、リウマチで痛む手をかばいながら、母のために翌朝の味噌汁の用意をして寝たに違いなかった。
それを見た私たちは悲しみの中にも、父の味噌汁が、最後の最後まで母を大切にし続けた父の、母への最高のラブレターでもあったことを確信したのだった。
![]()



