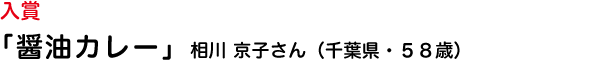
日の当たる土曜日の居間にほんのり甘い刺激的な香りが漂う。大きめに切ったじゃがいもと玉葱、そして少なめの豚肉でコクを増した熱々のルーをかき混ぜていると、一瞬、私は五十数年前の私になっている時がある。不思議なことに、それはいつも祖母の命日である。
私は祖母に育てられた。祖母は、不肖の娘が残していった幼い私と姉を引き取った。昭和三十年代、世は高度経済成長真っ只中。早くに夫を亡くした祖母は、職もなく、生活保護を受けながら隙間だらけのペラペラの木で出来た小さな家の庭で野菜を育てて何とか生活していた。いつも夕食は煮物か、水菜とクジラの肉を水炊きにし、醤油を垂らした鍋だった。田舎育ちの祖母は、調味料といえば醤油しか知らなかった。皿に残った醤油は大切に保存し、最後の一滴も絶対に捨てなかった。「米と醤油と水があれば死なへん」が口癖だった。祖母は、たまに寺の草むしりなんかを手伝い、僅かな駄菓子や卵をもらってきた。卵一つを割烹着に包んで大事そうに持ち帰り末っ子の私にだけ目玉焼きを作ると、大切な醤油を垂らしてくれた。私は祖母に食べさせたくて「お腹空いてへんから、おばあちゃんが食べたらええ」と言う。すると祖母は「おばあちゃんは食べとうない」と言う。香ばしい醤油と半熟卵の甘みが口の中に広がる幸せは今でも鮮明に思い出せる。そんな私も小学校に通うと、給食を食べるようになり、世の中には色々な料理があることを知った。中でも衝撃的だったのはカレーライスだ。他の子供たちはどうだったか知らないが、こんなに美味しくてお洒落なものがあることを知った私は、学校から帰るや否や、興奮して祖母にカレーライスの話をした。祖母は少し困った顔をして「おばあちゃんは、そんな洒落たもん、よう作らん」と言っただけだった。しかし次の日、祖母は、なけなしのお金で、何処かからカレー粉と豚肉を買ってきた。当時、近所では、それしかなかった「オリエンタルカレー」というカレー粉を私に見せ「どないして作るんや」と聞く。「肉と、じゃがいもと玉ねぎを煮て、カレー粉を入れるだけや」と私が言うと「ほんまに、それだけか」と不安そうに何度も尋ねる。無事に出来上がっても「他に何も入れへんのか」と落ち着かない。気づいたら祖母は鍋に醤油を入れていた。どうやら祖母にとって醤油というのは無くてはならない貴重な調味料であると同時に何でも美味しくしてくれる魔法の調味料であったらしい。醤油入りのカレーは、学校で食べた時のようにハイカラではなかったが、私にとっては何だか腑に落ちる味わいだった。
鍋にかけていた火を止めると、いつの間にか娘が横に立っていた。もう三十年以上、私がカレーを作るのを見ている娘は、「はい」と手渡してくれた。
私は、鍋に醤油を垂らす。少しの敬意を込めて。
![]()



