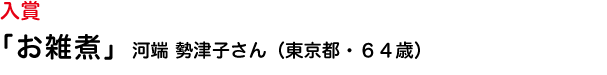
大晦日は一日中料理だ。なます、かぶらの酢漬け、煮豆はもうできている。今日は一口大に切った鰤を練炭火鉢で照り焼きにしていく。紋甲イカは松笠の切り目を入れ、七輪で焼く。ガス台には特大鍋がある。昨夜から水につけてもどした焼き海老が70尾ほど入っている。父母の郷里の鹿児島から取り寄せた雑煮用の海老だ。長さは15センチ以上もある。醤油、酒を加え、ことこと煮て味をととのえていく。割烹着を着た母が小皿にだしを入れ、父に差し出す。味見は2回、3回繰り返され、父が神妙な顔で「よし」と宣言する。
元日は朝から来客がひっきりなしだ。客が入れ替わるたびに、席をつくり、祝い箸、盃を並べる。雑煮を供する。焼いた丸餅、こいも、小松菜を盛り、たっぷりつゆを入れる。海老は椀からはみだしている。海老とつゆだけお替わりという客もいて、母は海老の残り本数を数えながらはらはらした表情を見せていた。夜は親族一同が集まる。ある年には、当時婚約者だった夫もこの席に加えられた。宴のあと、夫は「うちの雑煮はこれにしよう」と言った。
私は結婚してからも毎年里帰りし、大晦日の料理を手伝った。ある年、母は病魔に侵され、もう台所には立てなくなっていた。練炭火鉢も七輪も姿を消していた。私はひとりもくもくと料理を作り続けた。一段落する度に、母の部家に料理を見せにいった。母は痛みと闘っていたのだろうに、口をついて出るのは「丁寧な松笠切り、ありがとう」「鰤の照りがいいね」「主婦業も板についてきたね」と褒め言葉ばかり。雑煮の味も母が「よし」と宣言した。
翌年、母は逝った。数ヵ月後、夫は海外転勤を命じられ、私も子供達とともに海を渡った。海老は国によって、大きさも種類もいろいろだった。二度茹でしたり、煎り付けたり、母の作った雑煮を思い出しながら工夫した。小松菜はホウレンソウや青梗菜になった。真夏のお正月もあった。雑煮の味は少しずつ変化していったかもしれない。それでも22年間、私は海外で海老雑煮を作り続けた。母には遊びにきてほしかった。私の作る海老雑煮もどきを食べてもらいたかった。
今、私は日本にいる。食が豊富に、便利になったのには驚くばかりだ。宅配も充実し、全国の食材が手に入る。苦労することなく、母が作ったのと同じ雑煮を作ることができる。私が母から教わったのは単に雑煮の作り方ではない。脈々と続く人の営みの一環としての生き様である。その生き様を芯とする凛々しさである。凛々しさが子供に、そしてまたその子供にと伝わってほしいと願う。うちの雑煮を海老雑煮と勇断してくれた夫にも感謝している。
![]()



