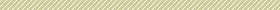〝自分の言葉〟を発見しながら
文学の世界でいろいろな人をあたためていきたい
 温 又柔さん
温 又柔さん
大学で得た「経験を客観的に言語化する力」
田中 温さんは、法政大学の国際文化学部の1期生※でいらっしゃいますね。
温 進路を考えているときに、高校の担任の先生が「法政大学に新しい学部ができるんだけどどうかな?」と紹介してくれたんです。その学部がまさに国際文化学部で、スタディ・アブロード(SA)プログラムで上海に留学できることを知り、中国語の勉強がしたかった私はたちまち心惹かれました。そこでSA自己推薦入試という特別入試で受験し、無事合格したんです。
田中 中国語を勉強したいという気持ちが原動力になったようですね。
温 私自身は3歳から日本にいるのですが、家の中で両親は中国語や台湾語を話していたので、中国語や台湾語をすごく身近に感じて育ちました。中学生くらいまでは「私は中国語ができる」とずっと思い込んでいたのですが、いざ読み書きの段階になると正確にできないことに気づきました。特に文字や文法が苦手で、きちんと学ばないといけないと痛感し、16歳の時から本格的に習い始めました。中国語をしっかりと学びたいという思いが大学選びにつながり、とても幸運でした。
田中 実際に法政大学に入学していかがでしたか。
温 新しくできた学部ということもあって、当時学部長であった川村湊先生を始めとする教授陣がこの学部を盛り上げていこうとすごく意欲的だったのを覚えています。ゼミなんかでも、先生から一方的に指導を受けるというよりは、学生も含めたみんなで「国際文化学」という学問を模索していたような感じがあって、それが個人的には性に合っていました。また、様々な分野の授業に触れることで学問的な用語を知り、そのおかげで、自分がそれまで感じてきた「ささやかな違和感」の正体はこういうことだったのかと分析できるようになっていくのも楽しかったです。
田中 自分の体験を客観的に言語化できる、そして論理的にわかってくる。それはものすごく良い体験ですね。
温 例えば、現代思想の森村修先生から、シニフィアン、シニフィエ、ラング、パロールなどの意味を教わったときは、「言葉と世界の関係は固定的ではなく、恣意的でもっと自由なんだ」と感動しましたし、今泉裕美子先生から「国民国家という枠組みの中でのみ思考していたら見落してしまうものがある」と教わったときもハッとしました。法政大学での数年間の学びの中で、自分の経験を客観的に言語化していく力が養われたと思っています。
田中 学ぶことで自分の内面にあって言葉にできなかったいろんなものを理解し、再解釈、再構築する。まさに、それが本当の意味での勉強ですよね。自分の外にあるものをただ外から持って来て学ぶことにはあまり意味がない。
言語の国境線は実はあいまいなもの

田中 大学卒業後、法政の大学院に進学されましたが、もともと研究に興味があったのですか。
温 学部のときは、川村先生が創作のゼミを立ち上げられたので、そこに参加し、小説と称したものを色々書き散らしました。でも、書きたいという思いが強まれば強まるほど、どう書いたらいいのかわからなくなってきて......正直に打ち明けると、大学院に進学しようと思ったいちばんの理由は、研究というよりも自分についてもっと知りたかったからなんです。「なんで私は日本語をしゃべっているのだろう」とか、「両親は日本語を話さないのに、なぜおじいちゃんおばあちゃんはあんなに流暢に日本語をしゃべることができるんだろう」といった一連の自分に関連する問題を、個人的な文脈ではなく、社会的、歴史的にちゃんと見てみたいと思って、モラトリアム期間を延長しました。卒業すると、まずは国際日本学インスティテュートで1年間学んで、そのあと国際文化専攻の修士課程にうつりました。修士論文は引き続き川村先生が指導してくださったのですが、この頃は司修先生とリービ英雄先生からも大変多くを学びました。特にリービ先生は「日本語は誰のものでもある」ということ身をもって示して下さり、とても勇気づけられました。
田中 小説に向かっていったのはなぜですか。
温 きっかけは中国語の勉強の挫折だったかもしれません。実は、私は中国語を勉強してもなかなか上達しなかったんです。もともと記憶の中に定着していた中国語の情報が足を引っ張ってしまい、どうしてもまっさらな状態で勉強できませんでした。むしろ0から始めた友人たちの方がどんどん上達していくのを横目で見て、限界を感じました。ただそこで、私は中国語がうまくできない分、日本語と自分との関係がすごく密接だということに気づくことができました。台湾人なのになぜか中国語がうまくならず、日本語ができる私ってなんだろう。それを表現できそうな場所が小説だったんです。
田中 エッセイ集『台湾生まれ 日本語育ち』から、芥川賞候補となった『真ん中の子どもたち』で、別の地平を開いたという気がします。エッセイと小説ではどんなところが違いますか。
温 もともと小説を書きたいと思っていまして、小説を二作発表した後に書いたのがエッセイ集でした。「私は何でこんなに小説が書きたいのか」「次はこんな小説を書きたい」といったことを考えるために書いたのが、『台湾生まれ 日本語育ち』。そして『真ん中の子どもたち』は、私の言語との向き合い方を個人的なものとして片付けずに、私のような人間と誰かが手を取り合うための場所を作りたくて書いたというのが、正直な思いです。
田中 書くことによって経験を普遍化したんですね。
温 普遍化というとカッコよすぎるのでちょっとこそばゆいのですが、どちらかといえば自分の非常に個人的な部分を思い切って晒すことで、同じような感覚を持っているかもしれない人たちと連帯するきっかけを作りたかったのだと思います。「私はここにいて、あなたもここにいるよね」ということを確認しながら、作者の名前を忘れて物語の中で主人公たちと戯れながら、作品世界を楽しんで欲しかった。
田中 『真ん中の子どもたち』には3人の登場人物が出てきますが、微妙に背景が違う。私はそこにリアリティーを感じました。ハンガリー出身でフランス語で小説を書いたアゴタ・クリストフを思い出しました。
温 ありがとうございます。光栄です。クリストフの自伝的エッセイ『文盲』には大変触発されたので、田中先生がそう感じてくださったことがすごく嬉しいです。言語は生まれつき与えられているものではなく、外からやってくるという前提があるもの。でも、日本列島にいて日本語が通じる空間にずっと生まれ育ってしまうと、だんだん言葉が血肉化して、自分は日本語と一緒に生まれてきたものだとつい勘違いしてしまう。そういう日本の方ってけっこう多いと思うんですよね。
田中 本当にそうだと思います。
温 言語と言語を隔てる国境線は実はあいまいなものであると、私は私の立場で書いてみたかった。そういう私のような「中間地帯」にいる人に自分がいびつだと思わせてしまう日本の閉鎖的な空気に対して、「あなたたちはここにいていいんだよ」と言いたい。いびつさが輝きなんだと。
田中 考えてみれば、みんなどこか「真ん中」の人なんですよね。
温 その通りです。そもそも、完璧な日本人なんて、実は存在しないと思います。私は、それぞれちょっとずつ中途半端な者同士、「今ここにいること」を分かち合う喜びみたいなものを大切にしたいんです。
「今ここにいること」を分かち合いたい

田中 ご自身のアイデンティティーを今はどのように考えていますか。
温 以前は「台湾人としての私」を獲得したいと思っていた時期もありました。でも、同世代の台湾人とは経験の蓄積が圧倒的に違う。どんなにがんばってもズレが生じてしまうんです。そういう意味で自分は、台湾人そのものにはなりきれない。かといって日本人としてもどこかズレている。こういった中間地点でとまどっている自分の有り様をどうやったら肯定できるんだろうということがずっと自分の課題だったんです。華僑の歴史や、世界各地に散らばった日本人による手記を読んだりしながら考えた時期もありました。
田中 もっと複雑なのは、「台湾人は中国人でしょ」という人が多いこと。小説にも出てきましたね。
温 あれは、大学時代に上海に留学した時の実体験です。「私は中国、台湾、日本の国の間のどこにも入れないんだな」と思いました。
田中 これからは、「真ん中の人」が増えていく時代です。絶対に日本人に関係ないなんて言えません。
温 私は、自分も日本人のつもりで発言しちゃう時があるんです。日本語が一番自分の感性のレベルでしみこんでいるので、例えば「(自分も含めた)日本人は空気読み過ぎだよね」と言ってしまったり。そういうとき、外国人が日本人批判していると受け止められて、日本人の悪口を言わないでくださいって反発されたり。でも、私は私みたいな日本人もいるということ、じわじわ浸透させたい。文学をとおしてそれができたらなと思うんです。
田中 文学というものは、自分の中の言葉と外の言葉がずれているからこそ様々な表現を模索して成り立っていくものですよね。
温 その伝えるための言葉はよそから覚えたもの。その言葉で相手に橋渡しできるか。言葉は「今ここにいること」を分かち合うためのものだと思います。そしてその言葉を学びたくて、読んだり書いたりしている。
田中 自分のことを表現するために言葉を探す。手っ取り早いのが本なんです。
温 本は自分ではないものになって世界を味わうためのものですよね。
田中 そう。本を読んでいる時は自由でいられる。私は本を読み過ぎて成績が落ち、読書を自分に禁じていた時期もありました。また、書くことでも言葉を発見していくことができますよね。自分の思いを言語化していくことはとても大切なことです。次回作も大いに期待しています。
温 はい、ありがとうございます。私は語学習得に失敗した「真ん中の子ども」ではありますが、これからも文学を通して、いろいろな人同士が出会う場をつくれたらなあと思っています。
※国際文化学部の開設年...1999年

- 作家 温 又柔(Wen Yuju/おん ゆうじゅう)
1980年台北生まれ。3歳より東京在住。台湾籍の日本語作家という立場から言葉とアイデンティティーをテーマとした創作を行う。中国語と台湾語を織り込んだ自身のテキストを朗読を通して表現する活動も大切にしている。
著書に『来福の家』(集英社)、『たった一つの私のものではない名前 Kindle版』(葉っぱの坑夫、2015年、エッセイ集『台湾生まれ 日本語育ち』(白水社)などを刊行。2017年4月に発表した『真ん中の子どもたち』(集英社)が、第157回(2017年上期)芥川賞候補となる。
- 法政大学総長 田中 優子(たなか ゆうこ)
1952年神奈川県生まれ。1974年法政大学文学部卒業。同大大学院人文科学研究科修士課程修了後、同大大学院人文科学研究科博士課程単位取得満期退学。2014年4月より法政大学総長に就任。専攻は江戸時代の文学・生活文化、アジア比較文化。行政改革審議会委員、国土交通省審議会委員、文部科学省学術審議会委員を歴任。日本私立大学連盟常務理事、大学基準協会理事、サントリー芸術財団理事など、学外活動も多く、TV・ラジオなどの出演も多数。
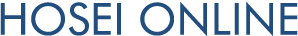




 法政大学 理工学部経営システム工学科専任講師
法政大学 理工学部経営システム工学科専任講師 法政大学 キャリアデザイン学部教授
法政大学 キャリアデザイン学部教授 法政大学 GIS(グローバル教養学部)助教
法政大学 GIS(グローバル教養学部)助教 法政大学社会学部メディア社会学科准教授
法政大学社会学部メディア社会学科准教授 法政大学GIS(グローバル教養学部)准教授
法政大学GIS(グローバル教養学部)准教授 法政大学デザイン工学部都市環境デザイン工学科教授
法政大学デザイン工学部都市環境デザイン工学科教授 文学部英文学科教授
文学部英文学科教授 手妻師
手妻師 法政大学社会学部准教授
法政大学社会学部准教授 法政大学現代福祉学部教授
法政大学現代福祉学部教授 法政大学常務理事・副学長
法政大学常務理事・副学長 法政大学デザイン工学部教授
法政大学デザイン工学部教授 法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科教授
法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科教授 京都大学総長
京都大学総長 法政大学法学部教授
法政大学法学部教授 探検家・編集者
探検家・編集者 法政大学スポーツ健康学部3年
法政大学スポーツ健康学部3年 立教大学総長
立教大学総長 法政大学情報科学部客員教授
法政大学情報科学部客員教授 法政大学キャリアデザイン学部教授
法政大学キャリアデザイン学部教授 法政大学社会学部教授
法政大学社会学部教授 作家
作家 南開大学周恩来研究センター特別顧問
南開大学周恩来研究センター特別顧問 社会活動家/法政大学現代福祉学部教授
社会活動家/法政大学現代福祉学部教授 NPO法人ファザーリング・ジャパン代表理事
NPO法人ファザーリング・ジャパン代表理事 世田谷区議会議員
世田谷区議会議員 シンガーソングライター
シンガーソングライター 法政大学経済学部教授
法政大学経済学部教授 法政大学経営大学院 イノベーション・マネジメント研究科教授
法政大学経営大学院 イノベーション・マネジメント研究科教授 法政大学国際文化学部教授
法政大学国際文化学部教授 元国立市長
元国立市長 法政大学大学院政策創造研究科教授
法政大学大学院政策創造研究科教授 曙ブレーキ工業代表取締役社長
曙ブレーキ工業代表取締役社長 法政大学法学部国際政治学科教授
法政大学法学部国際政治学科教授 法政大学社会学部社会学科教授
法政大学社会学部社会学科教授 聖学院大学学長
聖学院大学学長 政治学者
政治学者 小説家
小説家 経営学部経営学科教授
経営学部経営学科教授 キャリアデザイン学部教授
キャリアデザイン学部教授 イノベーション・マネジメント研究科教授
イノベーション・マネジメント研究科教授