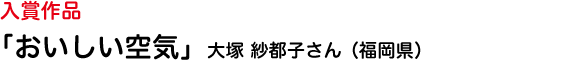
九州は福岡、さらに田舎の、田舎の、日本茶販売店。喫茶カウンターを併設した、茶葉量り売りのお店で、唐突に怒った顔。さらに横柄な態度で、初老の男性客はやって来た。乱雑に椅子を引くから、フロアの床が傷付くような音がしてギョッとする。しかし「いらっしゃいませ」と言うしかない。
「お茶をくれ。」
「どのようなものをお探しでしょうか。」
「家で、ずっと飲んでたお茶なんだ。同じものを探しているが、俺が買ったもんじゃないから、どこの何てお茶か分からねえんだ。俺はな、博多まで探しに行ったんだよ。上等なデパートの店員でも、見つけられなかったんだよ。博多まで行って、結局、何も買わずに手ぶらで帰ってきたんだ。まあ、こんな店じゃどうせ無理だろうな。」
椅子の上で大股を開いてふんぞり返り、喧嘩を売るように捲し立てる。残念ながら店番は私だけ。愛想だけのアルバイト。
とりあえず、出来る限りの特徴を聞き出して、試飲を勧めてみた。家庭での常用としてよく売れるものから、贈答に用いられるものまで、一通り入れていく。深蒸し茶、白折、玄米茶、抹茶入り・・・・・・それから少し高い玉露。大学生だった当時の私が店番の時に裏でガブガブ飲んでいた高級玉露。試飲用の小さな湯呑みで一杯ずつ出す度に、彼はこぼした。
「この間お袋が死んだんだ。」
「死んだから、何のお茶か分からねえんだ。」
「毎日飲んでたんだよ。」
勢いをなくしていく言葉と共に、彼自身も小さくなっていくように見えた。まるで、母親に置いていかれて拗ねている子供のようだった。彼は怒っているのではなく、悔やんでいるのだと気付いて、私は正直な気持ちを伝えた。
「もし、お母様が使用していたお茶の葉を見つけても、私が入れると違うものになると思います。お母様が亡くなられたから、そのお茶は、もう、飲めないんだと思います。」
怒らせてしまうかもしれない、と思った。けれど、彼は少しの間ぽかんとして、急にニッコリ笑うと「そうか。」と言った。
母親が、子供に入れるお茶。彼が探していたのは、親子の間に流れるおいしい空気だった。それは、もう失われてしまった。
「いかがですか。少しでも味や香りの近いものはございましたか?」
「じゃあ、これをもらおうか。」
彼は、グラム五百二十五円の白折をお買い上げ。ありがとうございました。
![]()



