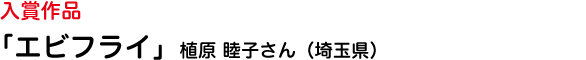
「ママ、覚えている?」
嫁ぎ先から久しぶりに帰ってきた娘が、台所でエビのからをむきながら話しかけてきた。たぶんあのことだなと思いながら、「なに?」とわざと答えた。娘が「たっくんがさ、・・・」と話し始める。
もう二十年も前の話だ。五才の息子は、友達三人とスイミングスクールに週一回通っていた。スイミングの帰りに、夏はアイス、冬はピザまんや肉まんを食べながら帰ってくる。そのおこづかいとして、毎回百円を渡していた。
四月の私の誕生日が近いある日、「ただいま!」と大きな声がして、「ママ。早く早く食べて。熱いうちに食べたほうがおいしいって、お店の人が言ってたよ」と、息子は転びそうな勢いで、息を弾ませながら帰ってきた。「どうしたの?」と声をかけながら、息子の差し出したビニールの袋を見た。そこには大きなエビフライが一匹入っていた。
「プレゼント。お誕生日のプレゼントだよ。ママが大好きなエビフライだよ」と、大きな目を丸くして、顔全体で、早く早くと、私がエビフライを口に入れるのを待っている。
「あーおいしい」声がふるえて涙が出そうなのを、ぐっと堪えて大きな声で言うと、「ほんと、おいしい?よかった!」息子はホッとした顔で水着の入ったリュックを置いた。小さな頭をなでながら、自分がアイスを食べたいのを何回がまんしたのかな、友達が肉まんを食べているのをどんな顔してみていたのかな、と思うと、また胸が熱くなった。
あんなにかわいい笑顔で無邪気だった息子も、中学に入ると口数も少なくなった。高校生になると、父親と意見が合わなくなり、家ではあまり笑うこともなく、自分の部屋にこもってばかりいた。高校三年生の三者面談の時、教育大学に行きたいと思っていることを聞かされ、びっくりした。六月に部活を引退してからは、毎日朝から夕方まで図書館に通い勉強していた。私はなんて声をかけていいか分からず、おにぎりを作ったり、お弁当を作ったり、ただただ彼の努力が報われることを祈っていた。
息子も今は二六になり、夢を実現させ、毎日教壇に立って頑張っている。大学の四年間親元を離れて過ごしたことで、息子は家族の大切さが分かったのかもしれない。初任給が出たから・・・・・・、ボーナスをもらったから・・・・・・と、いつも食事に連れていってくれる。その度に私はエビフライを食べる。池袋で食べたエビフライ、銀座で食べたエビフライ、どのエビフライも値段が高くとても美味しい。 でも、私にとって一番のエビフライは、駅近くの売店の特大エビフライ。あのエビフライだ。
「ママ、あの時幸せだったでしょ」という娘の声に、私はただうなずくだけ。
![]()



