読売新聞社と中央公論新社は、キッコーマンの協賛を得て、「あなたの『おいしい記憶』をおしえてください。」コンテストを開催しています。笑顔や優しさ、活力などを与えてくれるあなたの「おいしい記憶」を、私たちに教えてください。
主催/読売新聞社、中央公論新社 後援/文部科学省、農林水産省 協賛/キッコーマン株式会社 協力/読売KODOMO新聞
第6回
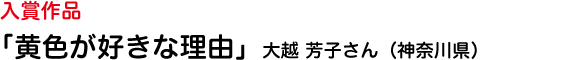
その人は、大きい鞄を持って立っていた。記憶の薄い遠い親戚の伯父さんだと思い、
「こんにちは」
と私は小声で挨拶をした。
奥の方から嬉しそうな母の声が聞こえた。
「お帰りなさいでしょ」と・・・
外国航路の船員だった父は、出航すると三、四ヵ月は、家を留守にする。
そう、その人とは、私の実父。
その日の夕方、母が入院した。
あまり会話もしたことのない、突然の訪問客というような父と、二人だけの生活が始まった。
明日は、遠足。
「お弁当はどうしよう」の一言がいえず、
「おやすみなさい」
と仰々しく頭を下げ、布団を敷いて寝た。
翌朝、座卓の上にお弁当らしき包みがあり嬉しさより安堵した。
緑がふんだんにある丘で、緊張の時だ。
蓋を開けると、真っ白い御飯の上に、甘い甘いいり卵の黄色が一杯で、その甘さの引き立て役が甘辛いお醤油の香りがする茶色。そして、ちょっとだけ鮮やかな桃色も。
すると、仲良しのあっちゃんが、
「遠足はおにぎりだよ。お箸で食べるお弁当は大変そうだね」
と真剣な顔でいった。
私は心の中で「ふん」と思いつつも、納得した。
美味しかった。嬉しかった。走りたかった。走って、走って。
門扉の向こうに、心配そうな父の顔を見付けた。
「黄色い卵が美味しかったよ」
父を喜ばせたくて、元気よく精一杯大きい声でいった。
「お母さんに会いに行こう」
ゴツゴツした大きい手が、私の手を握る。
母の隣りには、大事そうに黄色い産着に包まれた赤ちゃんがいた。
数日後、学校から帰宅すると、父の姿はなく
「お父さん、帰っちゃったんだぁ」
といってしまった。
何かちょっと変。
だって、ここがお父さんの家だから・・・
「これからは、三人でお留守番だね」
と母がやわらかい声でいった。
![]()



