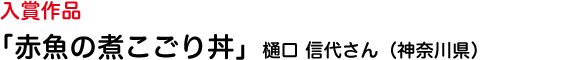
「ただいまー。母ちゃん、今日のおかず何?。」 夕方、私は遊んで帰ると、いつも、台所にいる母の所へ行った。「あんたの好きな赤魚」 「やったあー!!」 私は、母の腰に巻き付いて、大はしゃぎしたが、赤魚の煮付けだと、わかっていた。というのも、赤魚の煮付けの日は、家の近くまで来ると、プ~ンと、甘辛い醤油の香りが、漂っていたからだ。知っているのに、なぜか知らないふりをした事を思い出した。赤魚の煮付けで、大喜びした訳は、赤魚の煮付けの残り汁を、ひと晩置いて出来る煮こごりだった。
赤魚の煮付けの翌朝、母は、私にだけ煮こごり丼を作ってくれた。(いつの間にか、母と私の間で、煮こごり丼と呼ぶようになっていた) 炊き立てのごはんを丼に入れ、そのごはんで土手を作り、真ん中に玉杓子くらいの大きさのくぼみをつける。その中に、鍋に出来た煮こごりを 壊さないように玉杓子で掬い入れる。そして、鍋の底に張り付いて、しっかり味の染み込んだ生姜のスライスを添える。「はいよ。」と、母が、私の前に煮こごり丼を置くと、私は、まず、大きく息を鼻で吸い、香りを嗅ぐ。すると、頬の内側が、ギューっと締め付けられ、よだれが口の中で、いっぱいになる。私は、熱々ごはんの土手と、煮こごりの接している部分が、程良くとけ始めたところを、大スプーンで壊して絡め、口に運ぶ。一気に甘辛い醤油の香りが、体に広がり、よだれが少々垂れるが、気にしない。食べていると、「ゆっくり、よう、かんで食べんさいよ。」と母が声を掛けるくらい、煮こごり丼に無中だった。丼めしというと、大食いのイメージがあるが、私は、親が心配するくらい少食で、魚も苦手だったのだ。
ふと、久しぶりに、田舎で一人暮しの母に電話をしたくなった。「母ちゃん、元気?あのさぁ、煮こごり丼のこと憶えちょる?。」「あー、よう、憶えちょるいね。あんたぁ、煮こごり丼の時だけ、目の色を変えて食べよったけえ。」と、母は懐しそうに言った。母と話しているうち、急に、煮こごり丼が食べたくなった。「母ちゃん、赤魚の煮付けの作り方と、分量を教えてくれる?。」 すると、母は、「目分量じゃったけえ、よう、わからんのんよ。」と、困った声で言った。
そういえば、母は、料理の味付けをする時醤油や酒の一升ビンを脇の下に抱え、右の親指で、ビンの口を半分くらい塞ぎ、直接鍋に適当に入れていた。砂糖や塩も、壺から玉杓子で適当に掬っていた。
おふくろの味は、目分量と勘という隠し技が、おいしさの秘訣かもしれないと思った。
![]()



